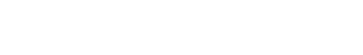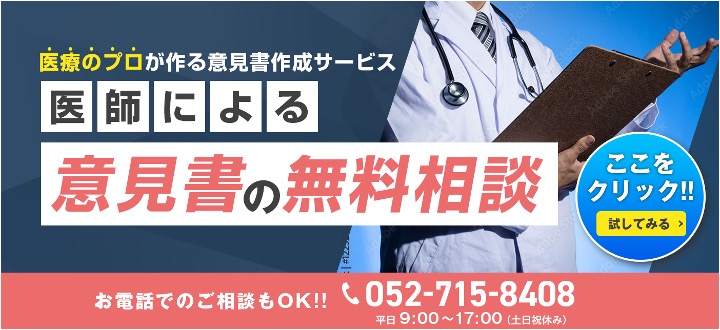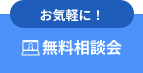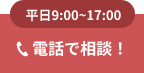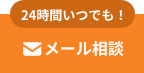後遺障害14級の慰謝料費用相場|慰謝料を増額する要因やポイントとは?

交通事故の被害により後遺障害等級14級が認定された場合、被害者は将来にわたる痛みや不便さに対する慰謝料(精神的苦痛への補償)を加害者側に請求できます。
本記事では、後遺障害14級に関する慰謝料請求に関する法的基準ごとの相場比較や増額のポイント、請求可能な他の損害項目、医学的証拠の重要性を解説します。
あわせて、医師が弁護士をサポートする専門サービスの内容と強みのご紹介もするので、交通事故による慰謝料請求の対応をする弁護士の方はぜひ参考にしてください。
目次
後遺障害14級とは?
後遺障害等級は1級(最重度)から14級(最軽度)まであり、後遺障害14級は交通事故によるケガが治療後も残ってしまった比較的軽微な後遺症に対して認定される等級です。
眼や耳、歯の欠損、聴力低下、外貌の醜状痕、手足の指の障害、局部の神経症状など比較的軽度な障害が該当し、細かく1号から9号に分類されています。
例えば、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)は典型的なケースで、むち打ち症(頚椎捻挫)による首や腰の慢性的な痛み・しびれ等で他覚的所見に乏しい場合に認定されることがあります。
後遺障害14級が認定されると事故被害者は後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できますが、症状が残っていても後遺障害等級が非該当と判断されてしまうと、こうした将来分の補償は受けられません。
また、実務上でも14級が認められるか否かで賠償額には大きな差が生じるため、まずは適切に14級の認定を受けることが重要になります。
関連記事:後遺障害14級の示談金75万円の内訳と増額のポイント
後遺障害14級の慰謝料相場と算定基準の比較
交通事故が原因で後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料額は、どの算定基準を適用するかによって大きく異なり、一般に次の3つの算定基準が存在します。
- 自賠責基準 – 自動車損害賠償責任保険(強制保険)で定められた最低補償基準
- 任意保険基準 – 各任意保険会社が社内で用いる独自の基準(非公開だが自賠責基準より高額で弁護士基準より低額とされる)
- 裁判基準(弁護士基準) – 裁判所で認められる水準に基づく基準。弁護士が交渉する際はこの基準を前提とする
後遺障害14級の慰謝料額も、算出基準ごとに次のような差があります。
| 等級 | 自賠責基準(後遺障害慰謝料) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(裁判基準) |
| 14級 | 32万円 | 約40万円 | 110万円※1 |
上記のとおり、同じ14級でも慰謝料額は自賠責基準で32万円、弁護士基準では110万円と約3.4倍もの開きがあります。
任意保険基準は明確に公表されていませんが、多くの保険会社は最低限の自賠責基準額を少し上回る程度の金額(14級ではおよそ40万円前後)しか提示しないといわれています。
実際、14級認定時に保険会社から自賠責保険による慰謝料と逸失利益(自賠責保険の逸失利益は一律43万円)を足して「慰謝料を含めて75万円が相場ですといった提示を受けるケースは少なくありません。
一方で、裁判基準(弁護士基準)であれば後遺障害14級の慰謝料は110万円と定められているため、任意保険基準に比べても大幅に高額になります。
被害者自身で示談交渉を行うと、多くの場合は保険会社は自賠責~任意保険基準の低い金額で示談を進めようとしますが、弁護士が介入して交渉することで示談交渉の段階から裁判基準での話し合いが行われ、結果的に慰謝料が増額されるケースが多いのが実情です。
したがって、適正な慰謝料を得るためには弁護士基準を前提に交渉することが重要となります。
※1:標準的な後遺障害14級案件の相場。実際の慰謝料は個別事情により増減する。
関連記事:むちうち後遺障害14級の金額相場は?示談交渉と意見書活用のポイント
慰謝料を増額させる要因と実務上のポイント
後遺障害14級の慰謝料を増額させるための要因について、判例や実務上考慮される事項ごとに解説します。
事故状況(加害者の悪質性など)
交通事故の態様が悪質だった場合(例:飲酒運転やひき逃げなど)、被害者としては「厳しい処罰を与えるべき」という感情を抱きやすいです。
しかし、日本の民事賠償制度では制裁的な慰謝料(懲罰的損害賠償)は認められていないため、加害者の過失の悪質性自体が慰謝料額を直接押し上げることは基本的にありません。
とはいえ、事故状況によっては被害者にPTSDなど二次的な精神的損害が生じる場合もあり、その場合は別途治療費や慰謝料の対象となります。
また、加害者側の対応が不誠実で裁判に至ったようなケースでは、裁判官の心証として被害者に有利に働き、結果的に慰謝料額が裁判基準の上限近くまで認められることはあり得ます。
後遺症が生活や職業に与える影響
後遺障害14級は労働能力喪失率5%とされるように軽微な障害ですが、被害者の職業や日常生活によってはその影響が深刻な場合があります。
例えばプロスポーツ選手が事故で慢性的な痛みを負い競技続行が困難になった場合や、手先の細かい作業を職業とする人が指のしびれで仕事を変えざるを得なくなった場合などです。
このように、後遺症によって従前の職業が遂行できなくなったり、身体の複数箇所に後遺症が生じたりした場合には、裁判所が基準額から慰謝料を増額して認めることがあります。
ただし、これらはあくまで例外的な「特殊事情」に基づく増額であり、必ずしも増額が保障されるわけではないため、増額事由に該当し得る事情がある場合は、交渉時に客観的な根拠を示すために、過去の判例などを精査して主張の立証をすることが重要です。
例えば「裁判所基準では後遺障害14級の慰謝料は110万円である」という客観資料を提示し、「御社(保険会社)の提示額はそれに比べて低すぎる」といった形で増額を求めることができます。
また、過去の判例や類似事案の示談例を示したり、医学的・工学的なエビデンス(証拠)を揃えることも説得力を高める一助となります。
関連記事:障害によるしびれが残った場合の法的責任と対応について
後遺障害14級で請求できるその他の損害賠償項目
後遺障害による慰謝料のほか、交通事故の被害者が請求できる損害賠償項目は多岐にわたります。
後遺障害14級に認定された場合に併せて請求可能な主な損害項目として、以下のようなものがあります。
治療費
事故との因果関係があり、社会通念上相当と認められる治療費は全額が賠償対象になります。
通常、被害者に過失がなければ加害者側保険会社が治療費を直接病院に支払うため、示談時に追加請求する必要がないケースもあります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故による傷害そのものに対する慰謝料で、入院・通院期間に応じて支払われます。ケガの程度や治療日数に応じて金額が算定され、こちらも自賠責基準・任意基準・弁護士基準で金額が異なります。
例えば弁護士基準では、むち打ちなどで14級相当の後遺症が残るようなケースの場合、通院期間や日数に応じて別途傷害慰謝料が発生※2します。
なお、この傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は重複して請求することができるため、双方を合算した金額が最終的な慰謝料総額となります。
※2:目安として6ヶ月通院で約50~100万円程度、頻度や入院の有無によって増減
休業損害
休業損害は、治療のために仕事を休んだことで減少した収入に対する補償で、会社員であれば有給休暇を使えず欠勤扱いとなった日数分の給与、自営業者であれば営業できなかったことによる減収分などが該当します。
一般的には事故前の収入を基に1日あたりの収入単価を算出し、それに実際に就労不能だった日数を掛けて計算します。
保険会社に休業損害証明書や収入証明を提出することで支払われ、無職や主婦の場合でも一定の基準で算出されます。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって将来の労働能力が低下したことによる収入減の補償であり、「事故がなければ将来得られたはずの収入」が失われた損害を現在価値に換算して請求します。
計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で表されます。
- 基礎収入:原則として事故前年度の年収
- 労働能力喪失率:等級ごとに定めがあり、14級は5%
- 労働能力喪失期間:通常は症状固定から67歳までだが、14級でむち打ち症の場合は5年程度の事例が多い
例えば14級9号(局部に神経症状)で年収500万円の会社員なら、5%の労働能力喪失が今後5年間続くものとしてライプニッツ係数(5年分:4.5797)を掛けると、逸失利益は約114万円になります。
なお、自賠責保険における後遺障害14級の逸失利益は一律43万円(年収の定めがなく最低保障額として)と算定されますが、弁護士基準では被害者の実収入に基づき柔軟に算定されるため、例えば高収入の方であれば逸失利益額が自賠責基準額を大きく上回るケースもあります。
また、専業主婦や学生についても労働参加率や学歴に応じて基礎収入がみなされ、逸失利益が認められます。
通院交通費
治療のために通院した際の交通費も実費で請求が可能です。
電車やバスなど公共交通機関を利用した場合はその運賃、タクシーを利用した場合は必要性が認められる範囲での料金、自家用車の場合はガソリン代や駐車場代等が該当します。
また、通院距離が長かったり、地方で車移動が必須だったりする場合には「ガソリン代+〇円/1km」の基準で算定することもあります。
入院雑費・付添看護費
入院中の日用品費用(雑費)や入通院時に付添人(家族等)が必要となった場合の費用も請求可能です。
入院雑費は通常1日あたり定額(自賠責は1日あたり1,100円)で計算します。また重傷事故では家族等が付き添った場合の付添看護費が認められることがあります。
以上のように、交通事故の損害賠償請求には多様な項目が含まれます。
後遺障害14級が認定された場合、慰謝料(後遺障害慰謝料+傷害慰謝料)と逸失利益が大きな割合を占めますが、弁護士としては依頼者が適切な賠償を受け取れるよう、治療費や休業損害はもちろん領収証が必要な交通費等も含め漏れのない請求を心がけることが重要です。
関連記事:膝の負傷で後遺障害14級に認定されるケースとは|12級に該当するケースも?
慰謝料請求における医学的証拠の重要性
慰謝料額そのものは等級によって定まりますが、その等級認定や保険会社との交渉の過程で影響することがあります。
そのため、後遺障害14級の慰謝料請求を適切に行うためには、医学的な裏付け(エビデンス)の存在が重要です。
後遺障害の等級を判断する流れ
認定機関(自賠責調査事務所)は、医師の作成する後遺障害診断書や検査結果に基づき等級を判断します。
例えば、頚椎捻挫による神経症状を認定する際は、レントゲンやMRIでの異常所見、神経学的検査結果などが判断材料となります。
そのため、画像上も検査上も異常が確認できず訴えが主観的な症状のみの場合、「他覚的所見がない」として後遺障害を非該当と判断したり、辛うじて14級が認められるに留まるケースが多くなります。
実務上、他覚的所見の有無が12級と14級を分けるポイントにもなっており、裏付けがない場合は「14級止まり」になるか、場合によっては後遺障害自体が認められないリスクがあるため、医師側の協力を得て可能な検査は積極的に受けておくことが重要です。
後遺障害14級認定のポイント
例えばむち打ち症で後遺障害申請をする場合、MRI検査による頚椎の状態確認や、整形外科で神経学的検査を実施しカルテに結果を記載してもらう、といった準備が有用です。
また、治療中の通院頻度も一つのポイントです。あまりに通院間隔が空いていたり治療中断期間が長いと、「症状がそれほど重くなかった」「途中で治ったのではないか」と判断されかねません。
症状固定となるまでは、できるだけコンスタントに通院を継続することが望ましく、明確な基準はないものの、例えばむち打ち症では6ヶ月間で実通院日数が90日以上(目安)あると後遺障害が認められやすくなります。
さらに、保険会社が治療費の支払い打ち切りを打診してきても安易に受け入れず、医師と相談のうえ症状固定まで適切な治療を続けることが、等級認定の土台を固める上で重要です。
医学的証拠の重要性を示す具体例
医学的証拠の重要性を示す具体例として、後遺障害14級からの等級変更事例をご紹介します。
ある事故で被害者の方は左膝の痛みと痺れが残りましたが、当初の自賠責調査事務所の判断では「他覚的所見がない」として14級9号相当と評価されました。
しかし、不服申立て(異議申立て)の際に専門医に依頼して画像資料を精査したところ、受傷直後および経過中のレントゲン写真やMRI画像において脛骨プラトー(脛骨関節面)の不整変形が残っていることが判明しました。
専門医は「この関節面の不整は事故によるもので、痛み・痺れの他覚所見と言える」と意見書で指摘し、その結果「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に相当すると判断され、慰謝料は14級110万円→12級290万円となり、逸失利益の労働能力喪失率も5%→14%へと大きく増えました。
仮に等級までは変わらなくとも、医学的根拠を示すことで保険会社の提示額を裁判基準まで引き上げさせる交渉が可能になる場合も多々あります。
後遺障害14級の慰謝料請求においては医学的証拠を軽視せず、必要に応じて専門医の知見を活用することが被害者救済に直結するといえるでしょう。
関連記事:後遺障害14級9号が非該当となったら|認定されるために必要な内容を整理
弁護士を支援する医療コンサルティング:YKRメディカルコンサルトの活用でできること
後遺症障害の認定における医学的証拠の重要性が高いなか、近年では医師が弁護士をサポートする専門サービスも登場しています。
YKRメディカルコンサルトは文字通り「医療コンサルタント」企業であり、医師が経営する弁護士向け医療情報コンサル会社として設立され、主に交通事故や労災、不動産相続、医療過誤といった分野で、弁護士の依頼に応じて専門医師の知見を提供するサービスを行っています。
法律実務において医学知識が不可欠であるにも関わらず医療記録の専門的内容を法律家が理解するのは難しいという現状に対し、YKRは「正しい医療情報を法律家に提供し、法と医療の橋渡しを行う」ことを使命に掲げ、以下のサービスをご提供しております。
交通事故意見書作成サービス
整形外科医、脳神経外科医、放射線科医など各領域の専門医が複数名で協議し、後遺障害等級の認定や異議申立て、裁判での主張に用いる専門的な内容を短期間で取りまとめ、公的機関提出用の意見書を作成します。
複数の医師が関与し、作成に携わった全ての医師名を記載するため、内容の信用性・中立性が担保されている点が特徴です。
画像評価サービス
放射線診断専門医が依頼案件のレントゲン・CT・MRI画像を適切に読影し、所見をレポートとして提示します。
例えば「MRI上、事故による新鮮な椎間板ヘルニア所見あり」など専門的な見解を示してくれるため、主治医の見落とし補完や他覚所見の発見につながります。
画像データと相談シートを送っていただければ、最短1週間程度で結果報告が受けられる迅速さもメリットです。
弁護士向け医療コンサルティング
弁護士向け医療コンサルティングは、分野を問わず医療に関する幅広い相談をお受けするサービスです。
「この症状で後遺障害等級は見込めるか」「カルテに書かれた専門用語の意味を知りたい」「将来的にどんな治療が必要か」など、訴訟や交渉を進める上で生じる医学上の疑問について、各科の専門医がアドバイスをご提供させていただきます。
Zoomを用いたオンライン相談会も毎週開催しており、無料で専門医に直接相談できる窓口をご用意しております。
交通事故実務において、「医学的なことは専門外だから…」と尻込みしてしまう弁護士は少なくありません。
このような弁護士の皆様に向けて、YKRメディカルコンサルトは医療と法律の架け橋としてサポートさせていただきます。
後遺障害等級の認定に納得がいかない場合に意見書を依頼すれば、新たな医学的根拠を得て異議申立てや訴訟で有利に戦うことができます。
事実、「自分の案件では医学的にどこまで主張できるか分からない」といった場合にセカンドオピニオン的にYKRに相談する弁護士も増えています。
後遺障害14級に関する案件であれば、適切な医学的エビデンスを揃えることで保険会社に医学的反論を突き付け、適正な示談金への増額を促す強力な武器とすることが可能です。
法律のプロである弁護士と医学の力を融合させ、より被害者に寄り添ったサポートをしたいとお考えの方は、まずはお気軽にYKRメディカルコンサルトへお問い合わせください。
まとめ
交通事故による後遺障害14級は、一見軽微な障害等級ではありますが、適切な手続きを踏めば裁判基準で110万円の慰謝料と逸失利益等の補償を受けることができます。
しかし現実には、保険会社から自賠責基準で提示された少額の示談金を提示され、そのまま妥協してしまう被害者も少なくありません。
事故にあった被害者に寄り添い、適正な金額を請求するためには、算定基準の違いを理解したうえで医学的な裏付けを揃え、適正な基準で交渉を行うことが重要です。
YKRメディカルコンサルトは、各分野に精通した医師が診断を行い、専門的な内容を取りまとめた意見書を作成するだけでなく、画像診断によって主治医の見落としや他覚所見の発見も可能です。
さらに、医療に関するご相談を直接していただける窓口もご用意していおりますので、、訴訟や交渉を進める上で生じる医学上の疑問を解消していただくこともできます。
事故によって辛い思いをした被害者に寄り添い、適正な金額の保証を勝ち取りたいとお考えの方は、ぜひYKRメディカルコンサルトの医療コンサルティングをご活用ください。