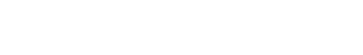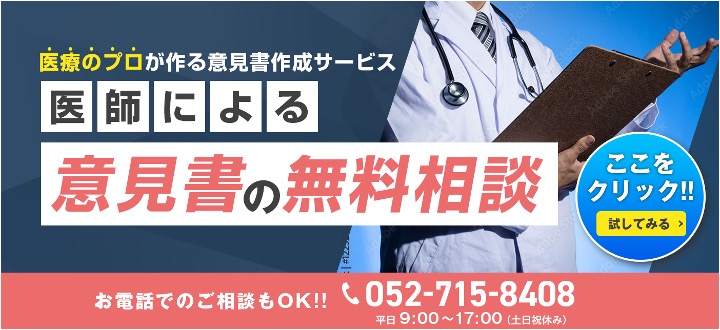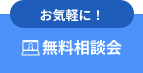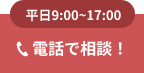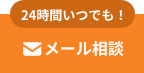後遺障害14級の示談金75万円の内訳と増額のポイント

交通事故で後遺障害14級に認定された場合、示談金として提示される金額が「75万円」前後になるケースがあります。
この75万円という金額の意味や内訳、増額のために知っておくべきポイントについて、交通事故案件を専門とする弁護士の視点から解説します。
慰謝料や逸失利益の相場、保険会社との交渉術、診断書と専門医の意見書の活用法、さらに医師によるサポートサービスの活用まで、専門的な情報を網羅しました。
適切な知識と対策によって後遺障害14級の示談金を適正な水準に引き上げましょう。
目次
後遺障害14級の示談金75万円の内訳と基準の違い

「75万円」という金額は、後遺障害14級に対する自賠責保険(強制保険)の支払い上限額に由来します。
この75万円には、大きく分けて後遺障害慰謝料(精神的苦痛に対する補償)と後遺障害逸失利益(将来の収入減に対する補償)が含まれています。
例えば自賠責基準では、後遺障害14級の慰謝料が約32万円、逸失利益が約43万円とされ、合計で75万円になる計算です。
ただし、75万円というのはあくまで自賠責基準の上限であり、任意保険会社や裁判基準(弁護士基準)では金額が異なります。
任意保険基準は各保険会社が内部的に定めるもので、自賠責基準を下回ることはないものの、それと大差ない低い提示に留まる例もあります。
一方、弁護士が交渉や訴訟で用いる裁判基準では、後遺障害14級の慰謝料相場は約110万円とされており、自賠責基準と比べ約3.4倍もの開きがあります。つまり、同じ14級でも基準によって示談金額は大きく異なるのです。
ポイント
保険会社から提示された示談金額が自賠責基準の75万円前後であれば、それは最低限の補償額に過ぎません。
弁護士基準で算定すれば遥かに高額になる可能性があるため、提示額の内訳が妥当か慎重に検討する必要があります。
不当に低いと感じる場合は、その根拠を確認し、交渉によって適正額への増額を求めるべきです。
関連記事:肘の負傷で後遺障害14級に該当する症状とは?認定基準や非該当の理由を解説
後遺障害14級の慰謝料と逸失利益の相場・計算方法
慰謝料(後遺障害慰謝料)と逸失利益は、後遺障害等級14級の示談金の主要な構成要素です。それぞれの相場観と計算方法を押さえておきましょう。
慰謝料の相場
前述のとおり、自賠責基準では14級の慰謝料はわずか32万円ですが、裁判所が用いる弁護士基準では約110万円が適正な相場とされています。
したがって、適切な手続きを踏めば慰謝料部分だけでも数十万円以上の差が生じることになります。
逸失利益の計算
逸失利益とは、後遺症によって将来失われる収入の補償です。計算式は一般に次のとおりです。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害14級の場合、労働能力喪失率の一般的な相場は5%になります。
例えば年収500万円の会社員が14級に認定されたケースでは、逸失利益はおおむね次のように算出されます。
500万円 × 5% × 4.5797 ≈ 114万4,925円
(※4.5797は、症状が残る期間に応じたライプニッツ係数の一例です。)
つまり、この例では逸失利益約114万円に加え、慰謝料110万円を合わせた約224万円が後遺障害部分の損害賠償額となります。
自賠責基準の75万円と比べて約3倍にもなる計算です。
相場の目安
もっとも、逸失利益は被害者の収入や年齢によって増減します。
収入が低ければ逸失利益も小さくなりますし、無職や主婦の場合には算定方法が異なることもあります。
そのため、後遺障害14級の慰謝料+逸失利益の合計相場はおおむね100万~300万円程度と幅があります。
例えば若年で収入が高い人ほど逸失利益が大きくなり、200~300万円台の賠償金になるケースも珍しくありません。
一方、収入が低かったり逸失利益がほとんど発生しない場合は100万円前後にとどまることもあります。
ポイント
保険会社提示額がこの相場レンジに比べて明らかに低い場合、適正額ではない可能性があります。
弁護士に依頼すれば、裁判基準を踏まえた正確な計算によって、本来受け取るべき慰謝料・逸失利益の額を算出してもらえます。
適正な賠償を得るためにも、まずは自身のケースでの適正額を把握しましょう。
示談交渉における保険会社対応の特徴と交渉ポイント

交通事故の示談交渉では、被害者は通常加害者側の任意保険会社の担当者とやり取りを行います。
保険会社との交渉に臨むにあたり、次のような特徴と対策ポイントを理解しておきましょう。
保険会社提示額は低めになりがち
保険会社は自社の支出を抑えるため、提示する示談金額を意図的に低く見積もる傾向があります。
特に後遺障害14級程度の比較的軽い後遺症の場合、前述の自賠責基準75万円をそのまま「相場」として提示してくることも少なくありません。
例えば「14級の後遺症なら慰謝料と逸失利益合わせて75万円程度が相場です」といった主張で早期の示談成立を図ってくる可能性があります。
被害者に法的知識がないと、この提示額が妥当なのか判断しづらいため、そのまま受け入れてしまうケースもあります。
安易に応じず、根拠を確認する
保険会社から示談金を提示されたら、すぐに了承せず金額の内訳や根拠を確認することが重要です。
「治療費○○円、休業損害○○円、後遺障害慰謝料○○円…」といった具体的な項目を明示させましょう。
提示額が低い場合、その理由として「過失相殺(被害者にも過失がある)」「症状は軽微で後遺障害は認められない」「他の要因による症状(素因)がある」等を挙げてくることがあります。
そうした主張が事実と合致しない場合は、医学的・法律的根拠に基づき反論する準備が必要です。
被害者請求の活用
後遺障害等級の認定手続きにおいて、保険会社任せの「事前認定」ではなく、被害者自身で必要資料を揃えて提出する「被害者請求」を選ぶことも交渉上有利に働く場合があります。
被害者請求なら、保険会社に遠慮せず自分に有利な証拠を全て提出できるため、適正な等級認定につながりやすいとされています。
実際、被害者請求では被害者の症状を正確に伝えるために資料を精査・補充でき、結果的に適正な後遺障害等級を獲得できるケースが多いと報告されています。
等級認定が適正になれば、示談交渉でも正当な土台の金額を主張しやすくなるでしょう。
交渉のスタンス
保険会社とのやり取りでは、常に記録(会話メモやメール保存)を残し、感情的にならず冷静に対処することが大切です。
担当者によっては高圧的な態度で「これ以上は出せません」「弁護士に依頼しても同じですよ」などと言ってくる場合もあります。
しかし、それが真実とは限りません。むしろ弁護士が代理交渉に入ることで、裁判所基準の適正額をベースに話し合いが進み、結果的に慰謝料が増額されるケースが多いのです。
保険会社の言い分をうのみにせず、必要に応じて専門家の意見を仰ぎましょう。
ポイント
保険会社との示談交渉では、「提示額は本当に適正か?」を常に疑う姿勢が重要です。提示額の根拠を確認し、不当に低ければ毅然と増額を要求します。
また、後遺障害等級の認定結果や過失割合に争いがある場合は、闘う姿勢を見せることも時に必要です。
保険会社が誠意ある対応をしない場合には、弁護士を通じて交渉したり、必要なら訴訟も辞さない構えで適正な賠償金を追求しましょう。
早期解決も大事ですが、焦って不利な示談に応じてしまうと取り返しがつきません。
診断書と専門医の意見書の違いと画像診断の重要性
後遺障害等級の認定や示談交渉を有利に進めるには、医療面の証拠や書類を適切に整えることが不可欠です。
中でも「後遺障害診断書」と「専門医の意見書(医学意見書)」は重要な役割を果たします。
また、MRIやCTなどの画像診断による客観的所見も等級認定に大きく影響します。
それぞれの違いとポイントを見ていきましょう。
後遺障害診断書とは
これは主治医(通常は事故後の治療を担当した医師)に作成してもらう書類で、症状固定時点での後遺症の状況を詳細に記載したものです。
自賠責保険の調査事務所(損害保険料率算出機構)は、この後遺障害診断書と提出された画像資料(レントゲン、CT、MRIなど)をもとに後遺障害等級の認定判断を行います。
したがって、診断書に後遺症の症状や検査結果が的確に記載されているかどうかが、適正な等級認定の第一関門となります。
診断書の不備が招くリスク
主治医が作成した診断書の内容が不十分だったり、医学的裏付けが弱い場合、後遺障害等級が認められない(非該当になる)ことがあります。
例えばむち打ち症(頚椎捻挫等)による神経症状で他覚所見(画像上の異常所見)がないケースでは、等級認定上は「他覚的所見がないこと」が14級の前提条件なので一応14級9号に該当し得ます。
しかしその一方で、客観的な異常所見がなければ12級は認定されないのも事実です。
つまりMRI画像などで明らかな神経圧迫所見などが示されない限り、等級は14級止まりになってしまいます。
このように画像所見の有無が12級と14級の分かれ目になるため、症状に見合った適正な等級を得るにはMRIやCT検査を適切なタイミングで受けておくことが重要になります。
専門医の意見書(医学意見書)とは
意見書とは、提出済みの診断書や画像所見を補完し、医学的見地から後遺障害の存在や因果関係を詳細に説明する書面です。
通常、後遺障害認定基準に精通した各分野の専門医が、診療記録・画像検査結果・神経学的検査結果・後遺障害診断書などを総合的に分析し作成します。
意見書では後遺症が交通事故に起因することや症状の医学的妥当性について、論理的な説明が加えられます。
必要に応じて関連医学文献の引用や検査データの図示なども行い、後遺障害が認定される蓋然性を専門的観点から主張してくれます。
診断書と意見書の役割の違い
簡単に言えば、診断書は事実の報告書、意見書は専門家による解説書です。
診断書には医師が認めた症状や検査結果が書かれますが、そこから一歩踏み込んで「その症状は事故による後遺障害といえる」「これだけの痛みや機能低下が残存している」という評価・意見までは記載されません。
また診断書のフォーマット上、書ける情報には限りがあります。
そこで意見書を活用することで、診断書だけでは伝えきれない医学的事情や因果関係を詳細に補足し、等級認定者や保険会社を説得する材料とするわけです。
特に、他覚所見に乏しく14級相当と判断されやすいケースでも、専門医の意見書によって症状の一貫性や事故との関連性を丁寧に主張すれば、非該当の回避や等級認定の可能性向上が期待できます。
画像鑑定・セカンドオピニオンの重要性
必要に応じて、別の医療機関でMRI検査を受けたり、専門医にセカンドオピニオンを依頼することも検討しましょう。
画像専門医による医用画像鑑定サービスを利用すれば、既存のMRIやレントゲン画像を精査して見落とされていた異常所見を指摘してもらえる可能性があります。
医学的な裏付けが強化されれば、等級認定や示談交渉を有利に進められます。
例えばMRI上は異常なしと言われたむち打ち症でも、専門家の目で見ると微細な椎間板の変性が確認でき、それが神経症状と合致すれば後遺障害として認定されるケースもあります。
ポイント
後遺障害14級の認定を確実にし、適正な賠償を得るには、医療証拠の充実が肝心です。
主治医作成の診断書の内容を弁護士にチェックしてもらい、不備があれば補充資料(意見書や検査データ)を用意しましょう。
専門医による意見書は作成に費用がかかりますが、その効果は絶大で、結果的に示談金が数十万円単位で増額されることもあります。
特に、保険会社が後遺障害の存在自体に疑いを示しているような場合には、意見書や画像所見によって医学的に反論することが交渉の切り札となるでしょう。
関連記事:後遺障害が認定されない5つの理由|認定されるための対処法とは
示談金を増額させる具体的交渉術

保険会社提示の低額な示談金を適正水準まで引き上げるためには、法律と交渉のプロである弁護士のノウハウが有効です。
以下に、後遺障害14級の示談金を増額させる具体的なポイントをまとめます。
裁判基準を根拠に交渉する
交渉の場では、最初から弁護士(裁判)基準で算出した適正額を提示し、相手に認識させることが有効です。
例えば「裁判所の基準では後遺障害14級の慰謝料は110万円です。
御社の提示額はそれに比べて低すぎます」といった形で、客観的な基準に基づく増額要求を行います。
保険会社も裁判になれば裁判基準に従わざるを得ないことは承知しているため、こちらが本気で裁判も辞さない姿勢を見せれば、ある程度の増額に応じてくる可能性が高まります。
逆に何も言わずにいれば相手の言い値でまとまってしまうため、主張すべき根拠は遠慮なく提示することが大切です。
過去の判例や解決事例を示す
類似の事故態様・後遺障害のケースでどの程度の賠償金が認められているか、判例データをもとに示すのも有効です。
「過去の裁判例では、同じく14級9号の後遺障害で総額250万円以上の支払いが認められています。
御社の提示額○○万円がいかに低いかお分かりでしょう」と具体的に伝えることで、相手にプレッシャーを与えられます。
実際、ある事例では保険会社から約80万円前後しか提示されなかった14級9号の案件が、訴訟の結果約250万円以上に増額されたケースもあります。
このような判例は枚挙にいとまがありません。
交渉段階で示談がまとまらなければ最終的に裁判で争う意思があることを示しつつ、判例を引き合いに出して適正水準まで譲歩を迫りましょう。
医学的・工学的エビデンスで説得する
示談金の増額交渉といっても、根拠なく「もっと金額を上げてくれ」と要求しても相手は納得しません。
そこで重要なのが前述の医学的な証拠です。
例えばMRI画像や専門医意見書によって「後遺症の深刻さ」や「将来にわたる影響」の裏付けを示せば、慰謝料や逸失利益の増額に説得力が生まれます。
また必要に応じて、事故の衝撃度合いを工学的に分析した報告書(車両の損傷状況や加速度の解析など)を用意し、「これだけの衝撃なら後遺症が残って当然」と技術的に説明することも考えられます。
法医学・交通工学など多角的な専門知識を動員して理詰めで攻めることで、保険会社も安易に反論できなくなるでしょう。
過失割合や素因減額にも目を光らせる
示談金額に影響を与える要素として、被害者側の過失割合や、事故前からある身体の不調(素因)による減額主張があります。
保険会社が過失を過大に評価していたり、「元々あった症状が悪化しただけ」といった素因減額を主張している場合、それが妥当か検証が必要です。
過失割合については事故状況の再現検証や目撃証言の収集などで適正化を図り、素因減額については医学的にその症状が事故と無関係と言えるのか専門家に判断を仰ぎます。
正当な反証ができれば、その分だけ示談金の増額につながります。
保険会社の一方的な主張を受け入れず、争点一つ一つに論拠を持って反論・交渉する姿勢が増額への道となります。
ポイント
増額交渉を成功させるには、法律・医学双方の観点から「こちらが要求する金額がいかに妥当であるか」を示すことです。
弁護士は交渉のプロとして裁判基準や判例を駆使し、医師など専門家の協力を得て客観的資料を揃えることで、保険会社に譲歩を促します。
妥協すべきでない点(慰謝料額や逸失利益の算定根拠など)は断固として主張し、必要なら訴訟も辞さない覚悟で臨むことが、最終的に依頼者(被害者)にとって最良の結果をもたらすでしょう。
YKRメディカルコンサルト:医師によるサポートと意見書作成サービス
後遺障害14級の認定や示談金の増額を目指す際、医学的根拠の充実は不可欠です。
そこで活用したいのが、YKRメディカルコンサルトが提供している「医師による意見書作成・事前相談サービス」です。
YKRメディカルコンサルトとは
YKRメディカルコンサルトは交通事故案件に精通した各診療科の専門医が多数在籍し、以下のようなサポートを提供しています。
| サービス内容 | 特徴 |
| 医師意見書・報告書の作成 | 必要書類や画像検査結果を分析し、後遺障害認定に必要な医学的根拠を整理 |
| オンラインによる事前相談 | 医師と直接オンラインでやりとりし、訴訟戦略・後遺障害認定の方向性を検討 |
| 医療ネットワークの活用 | 複数診療科からの多角的な意見をまとめ、複雑な症状にも対応 |
| 親身なサポート体制 | 弁護士の先生方の要望にきめ細かく応じ、納得のいく資料作成を行う |
医師との直接オンライン相談で安心
YKRメディカルコンサルトでは、ただ意見書を作成するだけでなく、医師と弁護士にて直接オンラインによる事前相談が可能です。
後遺障害診断書の内容や依頼者(被害者)の症状、争点となりそうな医学的ポイントなどを確認しながら、最適な方向性を決めるお手伝いをします。
• 「追加の画像検査が必要か?」
• 「どのような検査結果が後遺障害認定の裏付けになるか?」
• 「素因が疑われる場合の医学的反論はどう組み立てるか?」
こうした専門的な疑問にも、同社在籍の医師が親身にサポートしてくれる体制です。
弁護士の業務を強力にサポート
後遺障害等級の認定や示談金額をめぐる争いでは、医学的証拠の有無が結果を大きく左右します。
YKRメディカルコンサルトが提供するサービスを活用すれば、
• 弁護士が説明・立証しやすい意見書を受領できる
• 事案に合わせた最適な検査や追加資料の用意が円滑に進む
• 弁護士と医師が協力して交渉・訴訟戦略を組み立てられる
といったメリットが期待できます。
後遺障害14級だからといって低い示談金でまとめられてしまわないよう、医療・法律双方の専門知識を結集させることで、被害者にとって納得度の高い成果を得ることができるでしょう。
関連記事:交通事故のリハビリ日数や回数|通院中でも慰謝料はもらえる?
まとめ
後遺障害14級で提示される示談金が「75万円程度」というのは、あくまで自賠責基準に基づいた最低限度の金額にすぎません。
弁護士基準(裁判基準)を用いた正確な算定や、専門医による医学的根拠の補強を行うことで、示談金はさらに増額できる可能性があります。
• 慰謝料・逸失利益の算定根拠を明確にして、保険会社に対して適正額を主張する
• 不当に低い提示に応じる前に、診断書や画像所見の内容を再点検する
• 必要に応じて専門医の意見書を取得し、後遺症の因果関係や重症度を詳細に示す
こうしたステップを踏めば、後遺障害14級であっても十分な示談金を獲得できる可能性があります。
そして、医学的サポートの協力先としてYKRメディカルコンサルトを活用すれば、弁護士の先生方が抱える「医療面の不安や手間」を解消しながら、依頼者にとって最良の結果を導きやすくなるでしょう。
後遺障害14級の示談金を少しでも増額したい場合は、医師との連携が不可欠です。
医学的知見を味方に付け、依頼者の正当な権利を守るために、ぜひ本記事をご参考にしてください。