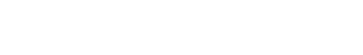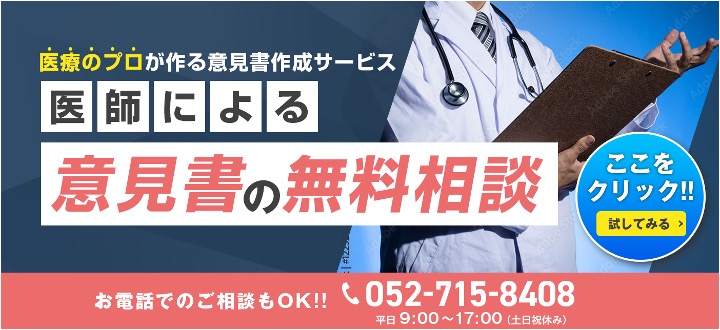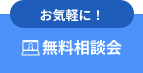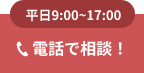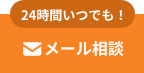後遺障害の慰謝料を増額するために必要な証拠と実務上の注意点

交通事故や労災によって後遺障害が残った場合、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
しかし、慰謝料額は算定基準の違いによって大きく異なります。
加害者側の保険会社は被害者に対し低い金額を提示しがちで、依頼者(被害者)に不利な提案になるケースが多いのが実情です。
適正で十分な慰謝料を得るためには、後遺障害等級の適切な認定や医学的根拠の立証が重要になります。
以下では、後遺障害慰謝料の基準ごとの違いや、慰謝料提示額が低くなる原因、増額のポイント、そして慰謝料請求に必要な証拠について解説します。
目次
後遺障害における慰謝料の算定基準の違い
交通事故の慰謝料には、大きく分けて「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。
同じ後遺障害等級でも、どの基準で算定するかによって金額が異なり、裁判所基準がもっとも高額、自賠責基準がもっとも低額になります。
まず各基準の特徴と等級ごとの慰謝料相場を整理します。
自賠責保険基準
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)はすべての車両に加入が義務付けられた強制保険で、人身事故被害者への最低限の補償を目的としています。
そのため自賠責基準で算定される慰謝料額は必要最小限の水準にとどまり、他の基準より低く抑えられています。
後遺障害等級ごとの自賠責基準による慰謝料額の例(※令和2年4月の基準改定後)は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準の慰謝料額 |
| 第1級 | 1,150万円 |
| 第2級 | 998万円 |
| 第3級 | 861万円 |
| 第4級 | 737万円 |
| 第5級 | 618万円 |
| 第6級 | 512万円 |
| 第7級 | 419万円 |
| 第8級 | 331万円 |
| 第9級 | 249万円 |
| 第10級 | 190万円 |
| 第11級 | 136万円 |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
上表の金額は後遺障害慰謝料のみの額で、自賠責保険から支払われる賠償金には他の損害項目も含め限度額があります。
(例えば別表第2の第1級の場合、後遺障害慰謝料と逸失利益等を含めた総額で3,000万円までなど)
自賠責保険基準はあくまで最低限の補償であり、重い後遺障害でも自賠責だけでは十分な慰謝料が受け取れないことに注意が必要です。
任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が独自に定めている賠償金算定基準です。
各社ごとに基準は非公開ですが、一般的に「自賠責基準よりやや高い程度」で「弁護士(裁判所)基準よりは低い」水準といわれます。
実際、平成10年までは任意保険各社で共通の「旧任意保険基準」が使われており、例えば後遺障害1級は1,300万円と定められていました。
現在は各社が独自算定していますが、大きく逸脱することはなく「自賠責+α」の額にとどまると考えられています。
任意保険基準による等級別の慰謝料額は公表されていませんが、参考までに旧任意保険基準での金額を自賠責基準と比較すると以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(旧基準目安) |
| 第1級 | 1,100万円 | 1,300万円 |
| 第2級 | 958万円 | 1,120万円 |
| 第3級 | 829万円 | 950万円 |
| 第4級 | 712万円 | 800万円 |
| 第5級 | 599万円 | 700万円 |
| 第6級 | 498万円 | 600万円 |
| 第7級 | 409万円 | 500万円 |
| 第8級 | 324万円 | 400万円 |
| 第9級 | 245万円 | 300万円 |
| 第10級 | 187万円 | 200万円 |
| 第11級 | 135万円 | 150万円 |
| 第12級 | 93万円 | 100万円 |
| 第13級 | 57万円 | 60万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円 |
ご覧のように、任意保険基準の額は自賠責基準に少し上乗せした程度であり、裁判所基準とは大きな開きがあります。
保険会社は被害者に対しこの低い基準で示談金を提示してくるのが通常であるため、そのまま鵜呑みにすると重い後遺障害に見合う十分な慰謝料を取り損ねるリスクがあります。
裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準(弁護士基準)は、過去の裁判例にもとづき算定された慰謝料基準で、日弁連交通事故相談センターの『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)等に示された金額を指します。
弁護士が示談交渉や裁判で主張する際に用いられる基準であり、3基準の中で最も高額になります。
以下は裁判所基準による後遺障害慰謝料の相場で、自賠責基準との比較です。
| 後遺障害等級 | 裁判所基準の慰謝料額(目安) | 自賠責基準 |
| 第1級 | 2,800万円 | 1,150万円 |
| 第2級 | 2,370万円 | 998万円 |
| 第3級 | 1,990万円 | 861万円 |
| 第4級 | 1,670万円 | 737万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 618万円 |
| 第6級 | 1,180万円 | 512万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 419万円 |
| 第8級 | 830万円 | 331万円 |
| 第9級 | 690万円 | 249万円 |
| 第10級 | 550万円 | 190万円 |
| 第11級 | 420万円 | 136万円 |
| 第12級 | 290万円 | 94万円 |
| 第13級 | 180万円 | 57万円 |
| 第14級 | 110万円 | 32万円 |
ご覧のように、裁判所基準は自賠責基準と比べ桁違いに高額であり、保険会社提示額(任意保険基準)との差も歴然です。
実務上、保険会社が提示する示談金は任意保険基準によるものですから、被害者にとって適正額とはいえません。
弁護士は「裁判になれば認められるであろう額」を基準に交渉するため、結果的に示談でも裁判所基準に近い増額が期待できます。
関連記事:後遺障害14級の慰謝料費用相場|慰謝料を増額する要因やポイントとは?
後遺障害慰謝料の提示額が低くなる主な原因
保険会社から提示される慰謝料額が低すぎる場合、そこにはいくつかの原因が考えられます。
主な要因として次の4つが挙げられます。
低い基準で算定されている
前述したとおり、保険会社は独自の(低い)任意保険基準で示談金を計算し提示してくるのが通常です。
被害者が専門知識なく提示額を受け入れてしまうと、本来受け取れる裁判所基準との差額分だけ損をしてしまう可能性があります。
例えば後遺障害14級(むち打ち等)の慰謝料ひとつ取っても、自賠責基準32万円に対し裁判所基準は110万円と3倍以上の開きがあります。
基準の違いを知らないままだと、提示額が適正かどうか判断できず適正額を逃してしまうのです。
まずはどの算定基準で計算されているかを確認することが重要です。
後遺障害等級の認定が適切でない
後遺障害等級の有無や高低も、慰謝料額に直結します。
後遺障害等級が認定されなかった場合、後遺障害慰謝料そのものが支払われません。
また等級が実情より低く認定された場合、本来より低い金額しか請求できません。
等級ひとつの違いで慰謝料額は数十万~数百万円変わるため、適正な認定を受けることが極めて重要です。
例えばむち打ち症状で本来12級13号程度の後遺障害が残っているのに認定が得られなかった場合、慰謝料相場は0円になってしまいます。(14級認定でも自賠責32万円程度)
適切な等級認定を逃すと本来得られるはずの慰謝料が大幅に減額されてしまうのです。
認定が適切でない背景として、後述する医学的証拠の不足が影響しているケースもあります。
したがって、妥当な等級を得るための対策を講じることが必要です。(詳しくは「4.後遺障害の慰謝料請求に必要な証拠」で解説します)
医学的根拠(証拠資料)の不足
後遺障害慰謝料の増減には医学的な証拠が強く影響します。
後遺障害の認定手続きは書面審査で行われ、提出書類(後遺障害診断書や診療記録、画像所見など)の内容だけで判断されます。
もし提出資料が不十分だと、調査事務所は「証拠不足」と判断し、本来認定されるはずの障害が見落とされたり低い等級に評価されてしまう可能性があります。
特に客観的な裏付けとなる画像所見(レントゲン、MRI、CT等)は重視されており、後遺障害の多くで画像による立証が不可欠とされています。
例えばヘルニアや骨折による障害では、画像に異常所見が映っていないと「痛みは気のせいではないか」などと疑われ、等級非該当と判断されかねません。
以上のように、医学的証拠の不足は適切な後遺障害等級の認定を妨げ、ひいては慰謝料の低額提示につながる要因となります。
後遺障害診断書の記載を充実させることはもちろん、必要に応じて追加の検査結果や専門医の意見書を用意し、医学的根拠を補強することが重要です。
(※なお、交通事故示談金が低く見積もられる原因としてはこの他に被害者側の過失割合が高いケースも挙げられます。
過失相殺によって賠償額全体が減額されるためですが、本稿の主眼とは性質が異なるため、ここでは詳述を割愛します。)
後遺障害の慰謝料を増額させる実務ポイント
適正な慰謝料額を勝ち取るには、単に交渉するだけでなく増額につながる要素を理解し、立証・主張していくことが重要です。
ここでは、慰謝料増額のポイントとなる考え方を整理します。
増額要素の把握
過去の裁判例を見ると、相場以上の慰謝料が認められる事案には大きく分けて次のようなケースがあります。
被害者の精神的苦痛が著しく大きい場合
通常の事故に比べ被害者やその家族の精神的衝撃・負担が極めて大きい事案では、慰謝料が相場より増額される傾向があります。
具体的には、加害者の悪質な行為(無免許運転や飲酒運転、ひき逃げ、事故後の暴言や無反省な態度など)によって被害者が受ける精神的苦痛が増大したケースや、後遺障害が重度で被害者本人および介護する家族の負担が非常に重いケースが該当します。
こうした場合、裁判所は通常の基準額では被害者の苦痛を償えないとして慰謝料を上乗せすることがあります。
被害者に特別な事情がある場合
被害者固有の事情により、事故の結果生じた精神的苦痛が通常より大きいと考えられるケースです。
例えば「女性被害者が事故のケガでやむなく妊娠中絶した」「外貌に傷が残ったため婚約破棄や職業上の夢の断念を余儀なくされた」「家族が事故によりPTSDなど精神疾患を発症した」等の場合、通常の慰謝料基準では十分でないとして増額が認められる可能性があります。
他の損害項目を補完する必要がある場合
逸失利益や治療費など他の損害賠償項目で十分にカバーできない損害があるケースでは、その埋め合わせとして慰謝料が相場より増額されることがあります。
具体的には「女優が顔に傷を負ったが逸失利益(将来の収入減)を算定しにくい場合」「後遺障害等級には該当しないものの労働に支障が出る怪我を負った場合」「将来手術が必要だが時期や費用が未確定で逸失利益等に反映できない場合」などで、他の項目では補填しきれない分を慰謝料で上乗せして全体のバランスを取る判断がなされます。
上記のような増額事由がある場合、被害者側としてはそれを見落とさず積極的に主張・立証することが肝要です。
裁判所は請求された範囲でしか賠償を認定しませんので、増額の可能性が少しでもあれば、最初から高めの慰謝料を予備的にでも請求しておくのがポイントです。
判例傾向の理解
慰謝料増額の交渉を有利に進めるには、実際に増額が認められた判例の傾向を把握しておくことも有用です。
前項で触れた増額要素に該当する事案では、裁判所が具体的にどの程度増額しているのか、いくつか例を挙げます。
悪質な事故で死亡慰謝料を増額
加害者が無免許・飲酒運転のうえ事故後に被害者を引きずり殺害(殺人罪該当)したという極めて悪質な事案では、通常2,800万円程度の死亡慰謝料が4,000万円と大幅に増額認定されました。
被害者の苦痛や遺族の無念さが筆舌に尽くし難いとして、被害者本人分3,500万円に遺族(妻子)各250万円を加算する判断が示されたものです。
重度後遺障害で後遺症慰謝料を増額
21歳女性が高次脳機能障害1級と片目失明8級の併合1級となった事案で、6度の大手術や若年での重大障害、容貌の醜状、両親の介護負担などを考慮し、本来2,800万円程度の後遺障害慰謝料が4,000万円に増額されました。
本人分3,200万円に両親各400万円を認め、通常基準を大きく上回る慰謝料が認定されています。
特殊事情で生活の夢を絶たれ増額
55歳男性が事故で併合6級(高次脳機能障害7級等)となり、事故前に描いていた再就職や家族との同居生活の希望がほぼ絶たれた事案では、後遺障害6級の基準額1,180万円に対し1,400万円の慰謝料が認められました。
希望を断たれた精神的苦痛を重く見たものです。
以上のように、判例上も増額が認められたケースでは共通して通常基準では救済不十分と評価できる事情が存在しています。
関連判例をリサーチし、依頼案件と類似する増額事例がないか検討してみることも大切です。
判例を示しながら交渉することで、保険会社に増額の妥当性を訴える説得力も高まるでしょう。
裁判所基準での交渉姿勢
実務的に慰謝料を適正額まで引き上げるためには、初めから裁判所基準(弁護士基準)での賠償額を主張・交渉する姿勢が欠かせません。
前述の通り、保険会社提示額は任意保険基準ベースで低額に抑えられているのが通常です。
そこで弁護士が介入し、「裁判になれば認められる水準」(=裁判所基準)で算定し直して示談交渉を行うことで、ほとんどのケースで増額が可能になります。
弁護士基準での金額と保険会社提示額との差額を具体的に示し、「裁判になった場合にはこの額が見込まれる」ことを相手方に認識させることが重要です。
例えば前述のとおり後遺障害等級14級でも任意基準と裁判基準で数十万円の差がありますし、重い障害では差額が数百万円~数千万円に達します。
こうした明確な数字の根拠を示されることで、保険会社も安易に低額のままでは応じにくくなるでしょう。
なお、裁判所基準での解決を目指す場合、弁護士費用特約の利用なども検討されます。
依頼者に経済的負担なく弁護士が介入できれば、結果的に増額分で十分費用が賄えるケースが多いためです。
いずれにせよ、被害者自身が低い提示額に妥協せず専門家に相談し、裁判基準での適正な慰謝料獲得を目指すことが肝心です。
関連記事:後遺障害14級の示談金75万円の内訳と増額のポイント
後遺障害の慰謝料請求に必要な証拠
後遺障害慰謝料を適正に受け取るためには、適切な後遺障害等級認定を確実に得ること、そして裁判所基準で増額を主張するための根拠を揃えることが不可欠です。
そのために押さえておきたい主な証拠を解説します。
後遺障害診断書
後遺障害診断書は症状固定時に主治医に作成してもらう書類で、後遺障害等級認定の申請に必須の書類です。
この診断書に記載された内容に基づき、損害保険料率算出機構の調査事務所が後遺障害の有無や等級を判断します。
したがって、診断書の記載が不十分だと本来認定されるはずの後遺症が認められなかったり、低い等級に評価されてしまったりする恐れがあります。
実際、「診断書に症状が書かれていない=治療終了時に症状が消失した」と見做され、記載漏れの症状は切り捨てられてしまいます。
また、診断書の「他覚所見・検査結果」欄に有利な検査結果が記載されていないと見落とされるリスクもあります。
実務上の注意点として、後遺障害診断書を医師に依頼する際は自覚症状を漏れなく伝えきちんと記載してもらうこと、そしてMRI画像など客観的所見がある場合は「他覚所見」欄に反映してもらうことが重要です。
後遺障害診断書の出来が慰謝料額を左右するといっても過言ではありません。
医師の意見書(医学的専門意見)
医師の意見書とは、主治医とは別の専門医が作成する医学的見解書面で、後遺障害等級の認定申請や異議申立て、裁判などで提出することを目的としたものです。
認定結果に不満がある場合(非該当や等級が低い場合)に、異議申立ての強力な武器となります。
意見書では「後遺症が医学的に存在することの証明」と「その症状が後遺障害等級認定基準に該当していることの説明」という2点を補強できます。
非該当理由に専門的観点から反論し、認定基準に照らして妥当な等級を主張できるため、意見書提出によって認定結果が覆った例も多く報告されています。
例えば、自賠責で「画像所見がない」と判断され非該当になったケースでも、専門医の意見書でMRI画像を精査し「異常所見が存在する」「症状に見合う所見が事故に起因する」と詳細に指摘することで、等級認定に結びつけられた例があります。
特にむち打ち等で14級9号非該当となったケースを意見書で覆す事例は珍しくなく、専門知識による後押しが重要です。
実務上、意見書を依頼する際は後遺症に該当する診療科の専門医に書いてもらう必要があります。
ケースによっては複数診療科にまたがる意見書が有効で、放射線科医による画像分析と整形外科医による機能障害の評価を組み合わせるなど、総合的な意見をまとめることも可能です。
費用は発生しますが、重い障害で数百万~数千万円の慰謝料増額が見込めるなら十分に見合うといえるでしょう。
検査画像・診療記録
MRI・CT・レントゲンなどの画像資料や、医師の診療記録(カルテ)、検査結果のデータも重要な証拠です。
前述の通り、画像所見は後遺障害認定で最も重視される客観証拠であり、例えばヘルニアや骨折の障害では画像による裏付けがないと等級認定は極めて困難です。
したがって、事故後できるだけ早期に必要な検査を受け、異常所見を確認しておくことが重要です。
時間が経ってから撮影した画像だと「事故と無関係な要因での損傷ではないか」と反論され、因果関係を疑われる可能性もあります。
画像以外にも、神経学的検査結果(腱反射の異常、筋力低下の測定値など)や、痛みの部位・程度を示す記録、手術記録なども後遺障害の裏付けとなります。
ポイントは「客観的な異常所見」を示す証拠を揃えることです。
仮に画像に明確な異常が写らない症状(神経症状など)の場合でも、他の検査値や臨床所見を積み上げ総合的に証明する姿勢が求められます。
もちろん、これらの証拠類は後遺障害診断書にまとめて記載され提出されるのが理想ですが、診断書に書ききれない詳細なデータについては写しを取得しておき、必要に応じて弁護士が補足資料として提出・交渉に用いることになります。
証拠が充実していれば保険会社も下手に低い等級や慰謝料でごまかせなくなるため、証拠を集め尽くすことが慰謝料増額への土台となるのです。
関連記事:後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?
医師の意見書に関する相談ならYKRメディカルコンサルトまで
後遺障害に関する医学的証拠を充実させたいときは、専門のコンサルタントに相談する方法もあります。
YKRメディカルコンサルトでは、交通事故案件における医学的意見書作成サービスを提供しており、依頼内容に応じて適切な診療科の医師を選定して意見書を作成してもらうことが可能です。
整形外科医、脳神経外科医、放射線科医など各領域の専門医がチームで関与し、必要に応じ複数の医師による総合的な意見書も作成できる体制を整えています。
実際、「画像上異常なし」とされた事案で専門医チームが詳細に画像鑑定・意見書作成を行い、等級認定に導いたケースも紹介されています。
依頼を検討する弁護士は、まず無料相談で事案の概要を伝え、意見書作成の見込みや適切な専門医のアサインについて提案を受けることができます。
医学的な裏付けが鍵となる後遺障害案件では、このような専門コンサルタントを活用することで依頼者により有利な立証が可能となるでしょう。
まとめ
後遺障害に対する慰謝料を正当に増額させるためには、算定基準の差を理解し適切な基準で交渉することと、十分な医学的証拠で後遺障害を立証することが両輪となります。
すなわち、後遺障害等級こそが重要となるわけです。
保険会社提示額のまま安易に示談してしまうと、本来得られるはずの慰謝料との差額分だけ被害者が泣き寝入りする結果になりかねません。
まずは自賠責・任意・裁判基準の違いを把握し、依頼者にとって最も有利な裁判所基準で算定した慰謝料額を念頭に交渉を進めることが大切です。
その際、後遺障害等級が適正に認定されていることが前提条件となるため、診断書の記載充実や客観的な検査結果の提出によって認定を確実にしなければなりません。
必要に応じて専門医の意見書取得など追加の証拠収集も検討しましょう。
知っているか否かで結果が大きく変わるのが交通事故慰謝料の実務です。
被害者側代理人として最新の基準や判例動向、医学知識に通じ、適切な証拠を揃えて主張立証すれば、依頼者にとって納得のいく慰謝料増額を勝ち取れる可能性が高まります。
弁護士としてしっかりと準備を整え、公平で十分な賠償獲得に尽力しましょう。