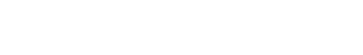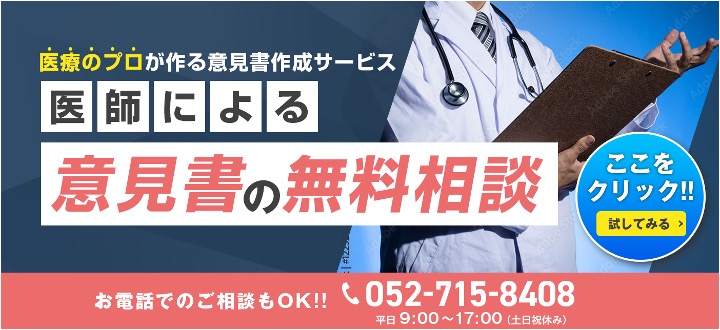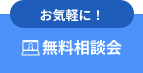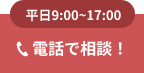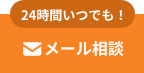交通事故で手のしびれの症状が出る原因とは?後遺障害認定に必要な条件と注意点

交通事故は、一瞬にして私たちの日常を揺るがします。
とりわけ、事故直後は軽いむち打ちと思っていた頚部外傷が、数日~数週間後に「手のしびれ」という形で表面化し、仕事や家事、趣味のすべてに影を落とすケースは少なくありません。
ところが、この“見えにくい”神経症状は画像や検査で裏づけにくく、適正な後遺障害等級の認定が難しい——そう感じる被害者や弁護士の先生が数多くいらっしゃいます。
本記事では、しびれが生じるメカニズム心身・社会生活に及ぼす影響後遺障害等級認定の要件と落とし穴などを体系的に解説します。
被害者の方には「なぜ検査で異常がなくても症状が続くのか」を、弁護士の先生方には「どのエビデンスが等級アップの決め手になるのか」を理解いただける内容を目指しました。
医学と法律が噛み合えば、真に必要な補償が適切に届く。
本稿がその第一歩となり、クライアントの救済や適正な賠償獲得の一助となれば幸いです。
目次
交通事故後に手がしびれる症状が出る理由

頚椎や神経の損傷によるもの
追突事故などで発生するむち打ち(頚椎捻挫)では、頚椎周囲の組織損傷により神経根が圧迫され、肩から腕~手指にかけて痺れが生じる場合があります。
ときには外傷で椎間板ヘルニアが発生し神経根を圧迫したり、脊髄自体が損傷されるケースもあります。
脊髄が圧迫されると手足の広い範囲に痺れや麻痺が及ぶこともあります。
特に神経根が障害されると耐え難い焼けるような痛みや痺れが首・肩甲骨・腕・手指に出現し、首を後屈すると悪化するのが典型です。
これに一致した筋力低下(握力低下など)も起こります。
こうした神経損傷は適切な治療が必要で、放置すると長引く恐れがあります。
一時的な圧迫や血行障害によるしびれ
事故直後の筋肉や靱帯の炎症・腫脹によって神経が一時的に圧迫されたり、血流が悪くなることでしびれが生じる可能性もあります。
例えば衝撃で肩や首周りの筋肉が過度に緊張すると末梢の血行不良を招き、腕を上げたりハンドルを強く握った際に痺れ・だるさが悪化することや、手先の痺れや冷えの原因となります。
これらの場合、圧迫や血流障害が解消されれば改善する一過性のものが多いですが、症状が続くときは神経損傷の可能性も踏まえ医師の診察を受けることが重要です。
症状の遅発性(時間差のある発症)
交通事故によるむち打ち症の特徴として、受傷直後ではなく一定期間経ってから症状が現れるケースが少なくありません。
事故当日は症状が軽微でも、数日後に痛みや痺れが増悪することがあり油断できません。
これは事故による組織の腫れや炎症が時間差で神経を圧迫したり、事故時には検出しきれなかった椎間板の損傷が後から明らかになったりするためだと考えられます。
実際、初診時のレントゲンでは異常がなく数週間後のMRI検査でヘルニアが判明する例もあります。
したがって、事故からしばらく経って手の痺れが出た場合でも、「まさか関係ないだろう」と自己判断せず早めに整形外科を受診しましょう。
2週間以上遅発性になると、事故と相当因果関係を有しないと判断されることもあるので気をつけるべきポイントになります。
関連記事:むちうち後遺障害14級の金額相場は?示談交渉と意見書活用のポイント
手のしびれによる精神的・日常生活上の影響

交通事故後に生じた手のしびれは、被害者の心身に次のような影響を及ぼします。
日常生活動作への支障
手や指先の感覚鈍麻や筋力低下により、細かな作業が困難になります。
例えば「ペットボトルの蓋を開けようとしてもうまく力が入らない」「長時間ハンドルを握っていると指先が痺れてくる」といった状態が続き、家事や仕事に支障をきたすことがあります。
物をつかみ損ねて落としたり、ボタンを留める・字を書くといった動作にも支障が出たりするため、被害者は大きな不便を強いられます。
利き手に障害が残った場合はその影響は特に深刻です。
慢性的な痛み・しびれによるストレス
絶え間ない痺れや痛みの刺激は被害者の精神的負担となります。
思うように手が使えないもどかしさや、いつ良くなるかわからない不安感からイライラ感が募り、家族や周囲に当たってしまうケースもあります。
実際、警察庁の調査でも、治療や補償が思うように進まないことで被害者が怒りっぽくなり、人間関係に悪影響を及ぼす例があるとされています。
このようなストレスは被害者の社会生活の質(QOL)を低下させ、抑うつ状態につながる恐れもあります。
睡眠障害や集中力低下
痺れに伴う疼痛が夜間も続く場合、寝付けなかったり途中で目が覚めてしまったりすることがあります。
むち打ち患者では首の痛みや腕の痺れが就寝時にも残り、不眠や浅い眠りの原因となることが知られています。
睡眠不足になると日中の強い眠気や注意力散漫を招き、仕事や運転に支障が出たりリハビリへの意欲低下にもつながります。
こうした悪循環が続くと精神面の不調(不安障害やPTSDの悪化など)を招く可能性もあり、早期に専門医のケアを受けることが大切です。
被害者にとって、手のしびれは単なる肉体的な症状にとどまらず、生活全般と心の健康に影を落とす問題です。
弁護士に相談する際には、日常生活でどのような困難が生じているか具体的に伝えることが重要です。
そうすることで、後述する損害賠償や後遺障害等級認定において、精神的苦痛や生活への支障も適切に考慮してもらうことができます。
手のしびれが後遺障害と認定される条件

交通事故によるケガが治療を尽くしても完全には治らず、何らかの症状が残ってしまった場合、それは「後遺症」と呼ばれます。
そして、その後遺症が自賠責保険などの基準で後遺障害として認定されると、等級(1~14級)に応じた損害賠償(後遺障害慰謝料や逸失利益)が請求可能になります。
手のしびれが後遺障害として認定されるには、以下のような条件を満たすことが求められます。
症状固定していること
まず大前提として、事故後の治療を一定期間続けた結果、それ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)になっている必要があります。
症状固定と医師に判断された時点で後遺障害診断書が作成され、後遺障害等級の審査が始まります。
それ以前の治療中の段階では、一時的な症状とみなされ後遺障害には該当しません。
しびれが事故後長期間継続し、治療しても改善しないときに初めて「後遺障害」を検討するステップに入ります。
自覚症状の一貫性・連続性
被害者本人が訴えるしびれの症状に矛盾や中断がないことも重要です。
例えば事故直後から一貫して手指のしびれを訴えており、その症状が途中で完全に消失したり他の原因で再発したのではなく、事故から症状固定まで連続して続いていることが求められます。
仮に事故から時間が経って初めて医師に相談した場合や、通院の間隔が不自然に空いている場合は、事故との因果関係が疑われ後遺障害と認められにくくなります。
したがって、事故後少しでも痺れがあれば早期に受診し、症状を訴えて診療記録に残してもらうことが大切です。
医学的に裏付けられた他覚所見があること
後遺障害等級の認定実務では、しびれなどの神経症状について医学的に説明できる客観的な所見(他覚所見)があるかが重視されます。
典型的なのはMRI画像などの画像診断所見と、整形外科的・神経学的検査による神経学的所見です。
具体的には、MRIやCTでヘルニアや骨折による神経圧迫が確認できるか、あるいはスパーリングテストやジャクソンテスト陽性、腱反射の低下、知覚鈍麻の分布、筋力低下など神経障害を示す検査結果が出ているか、といった点です。
これら他覚所見が被害者の自覚症状と整合していることで、より高位の障害等級が認定される可能性もあります。
例えば「首のヘルニアが右手の神経根を圧迫している画像所見」があり「右手の該当領域に一致した痺れと麻痺」が検査で確認できる場合、医学的因果関係が証明されれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当し得ます。
医学的に説明可能な因果関係が立証されていること
後遺障害の審査では、その痺れが本件事故による外傷に起因するものであることの証明も求められます。
仮にMRIで椎間板ヘルニアが見つかっても、それが事故と無関係な加齢変性と判断されれば後遺障害とは認められません。
実際、自覚症状に合致するMRI所見があるため12級13号相当だと考えられても、画像所見が外傷性でなく変性と判断された場合は認定されないことがあります。
したがって、画像上既存の変形なのか外傷性の新たな損傷なのか、医師に慎重に評価してもらう必要があります。
また画像所見がなくとも、受傷状況や症状経過に医学的整合性があり説明可能な場合には「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と認定されることがあります。
要は事故⇒症状発現⇒症状固定までのストーリーに無理がなく、医学的にも矛盾がないことが条件となります。
以上をまとめると、「事故でこれだけのケガを負い、診断・検査でも神経障害が証明され、それによる痺れがずっと続いている」という一連の立証ができて初めて、手の痺れは後遺障害として等級認定されます。
手のしびれが後遺障害として認定されにくい理由

むち打ち症による痛み・痺れは後遺障害等級の中でも認定が難しい分野といわれます。
特に「手のしびれ」は被害者の自覚症状が中心となりますが、他覚症状でも発生することがあるため、適切に対処しないと後遺障害として認められないリスクが高まります。
その主な理由は次のとおりです。
医学的証拠の不足(他覚所見の乏しさ)
むち打ち症状の特徴の一つは、医学的に証明できる他覚的所見に乏しいことです。
骨折や脱臼のようにレントゲンに写るわけではなく、MRIでも明確な異常所見が出ないケースが多々あります。
診断も多くの場合は患者の訴え(愁訴)に頼らざるを得ず、裏付けに欠けるため保険会社や医師から「本当にそんな症状があるのか?」と懐疑的に見られがちです。
実際、他覚所見がない症状は後遺障害の認定対象に含まれないという定めを置く保険約款もあるほどで、客観的証拠に欠けると等級非該当と判断される例も少なくありません。
特に12級認定には画像所見や検査所見が必須ですので、裏付けがなければ大半は14級9号止まりか、場合によっては後遺障害自体が認められないこともあります。
自覚症状の不整合や信用性への疑念
痺れの訴えに一貫性がない場合や、訴える内容が過度に主観的で曖昧な場合も認定は困難です。
例えば受傷直後は何も訴えていなかったのに治療終了間際になって突然「手が痺れる」と言い出したり、痛みや痺れの部位・程度の説明が受診の度に変わったりすると、症状の信用性が低いとみなされてしまいます。
また他覚的所見がない状況下では、保険者側は詐病(仮病)ではないかと疑う傾向すらあります。
実際に「むち打ち症は他覚所見に乏しいがゆえに仮病を疑われやすい」と指摘する専門家もいます。
こうした疑念を招かないためには、日頃から症状を具体的に医師へ伝え記録してもらうこと、整合しない訴え方をしないことが大切です。
検査結果の客観性に対する評価の厳しさ
他覚所見があっても、その証拠能力(客観性)が吟味されます。
例えばスパーリングテストやジャクソンテストは神経根障害の有無を調べる代表的な検査ですが、結果(痛みや痺れの誘発)は被検者の主観申告に依存するため、単独では「客観性が低い」という問題があります。
そのため検査が陽性でも、それだけで後遺障害が認められる保証はなく、画像検査の結果など他の客観的所見と整合して初めて有力な証拠とみなされます。
逆にスパーリングテスト等が陰性(異常なし)だった場合は、被害者が嘘をつくとは考えにくい検査だけに症状自体の存在が否定的に評価されてしまいます。
このように結果の解釈が難しい検査が多い点も、神経症状の等級認定を難しくする一因です。
以上のような理由から、交通事故による手の痺れは「見えにくい後遺症」ともいわれ、適切な証拠集めを怠ると低い等級や非該当と判断されてしまう傾向があります。
しかし裏を返せば、医学的証拠を十分に揃え一貫した症状経過を示すことができれば、適正な等級を得ることも可能です。
次章では、そのために用意すべき資料とポイントを解説します。
関連記事:交通事故のリハビリ日数や回数|通院中でも慰謝料はもらえる?
後遺障害認定に必要な資料と準備すべき検査

手の痺れを後遺障害として認定してもらうには、症状を医学的に証明・裏付ける資料を揃えて申請することが肝心です。
主に次のような資料・検査結果が必要となります。
神経学的検査の結果
整形外科で行われる各種の徒手検査・神経学的検査の所見は重要な他覚所見です。
具体的には、以下のような検査が当てはまります。
- スパーリングテストやジャクソンテスト(頚椎神経根圧迫テスト)の陽性所見
- 深部腱反射テスト(上腕二頭筋反射・橈骨骨幹反射・上腕三頭筋反射)の低下や左右差
- 知覚検査(どの指にどの程度のしびれ・感覚鈍麻があるか)
- 筋力テスト(握力低下や特定筋群の脱力の有無)
医師が客観的に確認できる身体所見(例えば触診での筋萎縮や筋緊張の偏り、圧痛の部位など)も含め、診断医の検査所見全般を後遺障害診断書に詳しく記載してもらいましょう。
なお、これらの検査結果はお互いに矛盾なく整合していることが望ましく、例えば「スパーリングテスト陽性だが反射や筋力は全く正常」だと説得力に欠けるため、追加検査を検討することもあります。
必要に応じて神経伝導速度検査や筋電図検査など専門的検査が実施されることもありますので、医師と相談してください。
MRI・CTなど画像診断の結果
MRI検査は神経圧迫の有無を確認する上で最も重要な検査です。
頚椎のMRI画像で椎間板ヘルニアの突出や脊髄・神経根の圧迫所見が写っていれば、それが強力な他覚所見となります。
CTは骨の異常(骨折や骨棘形成など)を見るのに有効で、MRIと併せて行えば診断精度が高まります。
画像所見は受傷部位の証明だけでなく、外傷性か変性かの判断材料にもなるため非常に重視されます。
できれば事故から症状固定までの間に複数回の画像検査を行い、症状の推移と画像変化を追える資料を残すと理想的です。
例えば「事故直後のMRIでは異常なし→数ヶ月後のMRIでヘルニア像を確認」といった経過があれば、診断遅れで見逃されたが実は事故由来の損傷だったと説明することも可能です。
画像検査結果はフィルムやデータを入手し、後遺障害等級申請時に提出します。
また放射線科医の読影レポートがあればコピーを添付しましょう。
診断書・診療記録
主治医に作成してもらう後遺障害診断書自体が重要な証拠書類となります。
ここには症状固定時点での後遺症の内容・程度、検査所見、画像所見、日常生活への支障度合いなどが記載されます。
不備なく的確に記載してもらうためにも、事前に医師と相談し自分の症状を正確に伝えておくことが大切です。
またそれまでの診療録(カルテ)やリハビリ経過表も、症状経過や一貫性を示す資料として活用できます。
必要に応じてコピーを入手し、等級申請時に提出しましょう。
医師の意見書・鑑定書
より専門的な見地から後遺障害の因果関係や医学的妥当性を補強するために、専門医による意見書を依頼することも有効です。
たとえば神経内科医や整形外科医に、画像所見と神経症状の関連性や、事故としびれとの因果関係について医学的に解説した文書を書いてもらえれば、審査機関への説得力が格段に増します。
特に自賠責の初回認定で非該当や14級止まりだったケースでは、異議申立てに際して専門医意見書を添付することで12級が認められた例もあります。
医師によっては意見書作成に消極的な場合もありますが、後述のような専門コンサルタントを利用して意見書を取得することも可能です。
費用はかかりますが、重い後遺障害が疑われる場合は前向きに検討すると良いでしょう。
その他の資料
症状を裏付けるものなら何でも提出価値があります。
例えば事故直後の救急記録、整骨院などで施術を受けている場合はその経過証明書、仕事や日常生活で支障が出ていることを示す勤務先や家族の証明書などです。
裁判になれば被害者本人の陳述書(事故後の生活状況の説明書)も証拠となります。
後遺障害等級の申請は一度きりではなく、非該当の場合は異議申立てで再審査を求めることもできます。
その際、新たな検査結果や医証が出れば追加提出できますので、諦めずに証拠を掘り起こすことが大切です。
医療と弁護士をつなぐYKRメディカルコンサルトの役割

交通事故の後遺障害案件では、医学知識と法律実務の橋渡しが重要になります。
そこで頼りになるのがYKRメディカルコンサルトのような専門サービスです。
「法と医療の架け橋」となることを理念に掲げ、医師が経営する弁護士向け医療コンサルティング会社として設立されました。
YKRメディカルコンサルトでは、整形外科医・脳神経外科医・放射線科医など各分野の専門医チームが協力し、交通事故や労災案件の医学的鑑定書・意見書を作成しています。
具体的なサービス内容は次のとおりです。
交通事故の医師意見書作成
裁判所や損保に提出するための交通事故に関する医学的意見書をオーダーメイドで作成します。
例えば今回のテーマである手の痺れについても、MRI画像や診療録を専門医が精査し、「どのような神経損傷があり、その後遺症が事故に起因することが医学的に合理的に説明できる」ことをレポートしてくれます。
意見書には関わった複数の専門医の連名で所見が記載されるため、内容の信用性も担保されています。
実際、YKRに依頼して非該当が12級13号に認定されたケースや、14級9号から12級への等級アップに成功した事例も多数公開されています。
医用画像の専門評価
放射線診断専門医による画像評価サービスも提供しています。
事故によるMRIやCT画像を改めて詳細に読み取り、見落とされがちな靱帯損傷や神経圧迫所見を発見してレポート化します。
例えば「レントゲンでは異常なしとされたがMRIでは微細なヘルニア所見がある」「関節面の不整を見逃していた」といったケースで、画像所見を根拠に異議申立てを行い後遺障害14級から12級への変更となった例も報告されています。
専門医の目で画像を再評価することで、後遺障害認定に必要な客観的証拠を強化できるのです。
弁護士向け医療コンサルティング
弁護士が案件を進める中で直面する医学的疑問に、YKRの医師が随時アドバイスを行うサービスもあります。
オンラインで無料相談会を開催し、整形外科や脳外科の専門医と直接ディスカッションできる機会を提供しています。
これにより、たとえば「この痺れは本当に事故が原因と言えるのか?」「症状とMRI所見が一致しないがどう反論すればよいか?」といった法律家の悩みに医療的視点から回答が得られます。
医療知識のアップデートや適切な検査の見極め方についても助言が受けられるため、弁護士にとって心強いパートナーと言えるでしょう。
YKRメディカルコンサルトのようなサービスを利用することで、被害者の訴えを医学的事実として裏付け、正当な後遺障害等級を獲得する可能性が高まります。
法律と医学の専門家が連携することで、被害者救済の質は格段に向上し、泣き寝入りせず適切な補償を得る道が開けるのです。
関連記事:障害によるしびれが残った場合の法的責任と対応について
まとめ
交通事故による手のしびれは、頚椎の神経損傷など様々な原因で生じ、被害者の生活と心身に深刻な影響を及ぼします。
一方で、その症状を後遺障害として認定・賠償してもらうためには医学的・法的な裏付けと戦略が必要です。
まず原因究明と治療を徹底することが出発点です。
事故後すぐに適切な検査(MRI等)を受け、神経症状の有無を調べましょう。
初期に異常が見当たらなくても症状が続く場合、時間を置いて再検査することで後から異常所見が見つかることもあります。
治療中は症状経過を詳細に主治医へ伝え、診療記録に残してもらってください。
痛みや痺れが日常生活に与える支障も遠慮なく相談しましょう。
症状固定と判断されたら、後遺障害等級認定の準備に移ります。
ポイントは2つです。
一つは医学的証拠(他覚所見)の収集。
MRI画像や神経学的検査結果など客観的資料を可能な限り揃え、症状の根拠を示します。
もう一つは症状の一貫性・整合性の確保。
事故との因果関係が疑われないよう、経過に矛盾がないことを示します。
この2点を満たせば、手のしびれも適正な等級(他覚所見ありなら12級13号、なければ14級9号)が認定される見込みが高まります。
認定が容易でない場合でも決して諦めないでください。
むち打ち症状は証明が難しい分野ではありますが、専門医の力を借りて医学的根拠を積み上げることで道は開けます。
実際に異議申立てによって等級が上がったケースも多々あります。
YKRメディカルコンサルトのような医療鑑定サービスを活用すれば、専門医があなたの症状を正しく評価し、法的主張をバックアップしてくれるでしょう。
法と医療の協働によって、被害者の正当な権利回復がより確実なものとなります。
最後に、被害者自身も適切な知識を身につけることが大切です。
本記事で述べたように、後遺障害認定には医学と法律双方の視点が関わります。
定期的な医療機関への受診と、適切なタイミングでの弁護士への相談が鍵になります。
交通事故による手のしびれはつらいものですが、適切に対処すればその苦しみは必ず報われます。
専門家の力を借りつつ、自分の症状と権利をしっかりと主張していきましょう。
それが適正な後遺障害等級の獲得ひいては十分な賠償を得る近道となります。
被害者の皆様が一日も早く安心して暮らせるよう、医学と法律の力を最大限に活用することをおすすめします。