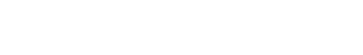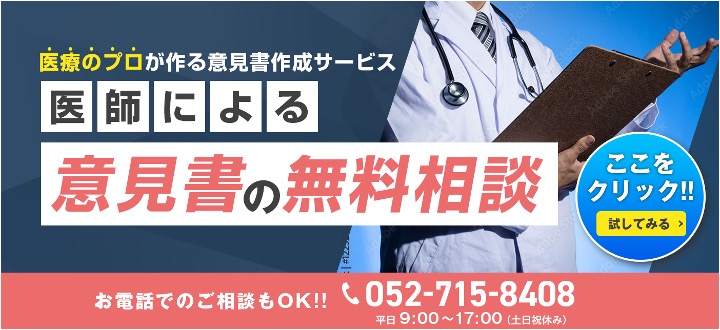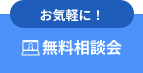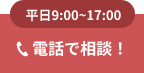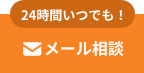肘の負傷で後遺障害14級に該当する症状とは?認定基準や非該当の理由を解説

交通事故による怪我が完治せずに何らかの後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級認定の申請をすることができます。
肘を負傷すると、肘関節脱臼や靭帯損傷などの傷病により、関節部の疼痛や可動域制限などの症状があらわれることがありますが、このような症状も後遺障害等級認定の対象になります。
肘の負傷で認定される後遺障害等級には、第1級~14級までありますが、後遺障害14級に該当する症状にはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、肘の負傷で後遺障害14級に該当する症状や認定基準・非該当の理由などについて、わかりやすく解説します。
目次
肘の負傷で後遺障害14級に該当する症状とは?

交通事故で肘を負傷すると、以下のような傷病名が診断されることがあります。
・肘関節脱臼
・肘内障
・靭帯損傷
・肘頭骨折
・肘部管症候群
肘の負傷は、治療を継続しても完治せずに、関節部の疼痛や腫れ、痺れなどの症状があらわれることがあります。
このような症状があらわれた場合には、後遺障害等級申請を行うことによって、後遺障害14級の認定を受けられる可能性があります。
ただし、必ず後遺障害14級の認定を受けられるわけではありませんので、認定基準などを踏まえた上で、適切な資料を揃えて申請をすることが重要です。
関連記事:後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?
肘の負傷で後遺障害14級に認定されるには
肘の負傷で後遺障害14級の認定を受けるには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
ただし、以下のポイントを実践したからといって必ず後遺障害14級の認定を受けられるわけではありませんので注意が必要です。
症状に重篤性があることを伝える
肘の負傷が後遺障害14級に該当するといえるためには、将来にわたって回復が困難な症状であるといえなければなりません。
症状の程度が軽いと後遺障害とは認められない可能性が高いため、症状に重篤性があることが後遺障害14級の認定を受けるポイントの一つになります。
肘の負傷で後遺障害14級の認定を受ける事案は、肘の疼痛や腫れ、痺れなどがMRIやレントゲンなどの他覚所見からは明らかではなく、もっぱら自覚症状に基づいています。
そのため、事故当初から医師に対して、強い疼痛や腫れ、痺れなどがあることをしっかりと伝え、カルテなどに記載してもらうようにしましょう。
医療機関へ定期的に受診
症状の重篤性を立証するには、自覚症状だけではなく、医療機関への通院実績も重要な要素となります。
通院頻度が低い、途中で通院を中断している期間があるなどの事情があると、症状の継続性・連続性に疑問を持たれてしまい、後遺障害14級の認定が難しくなります。
そのため、肘の負傷で後遺障害14級の認定を受けるには、医師の指示に従って定期的に医療機関を受診することが大切です。
症状が一貫している
肘の負傷で後遺障害14級の認定を受ける事案は、被害者の自覚症状以外に他覚所見が存在しませんので、症状の一貫性や継続性というのも後遺障害等級認定の重要なポイントになります。
疼痛の部位や程度が診察のたびに変わるようだと、症状の一貫性がないことを理由に後遺障害等級認定が非該当になってしまう可能性があります。
そのため、医療機関を受診する際には、肘の疼痛や腫れ、痺れなどの部位・程度を明確に医師に伝えるようにしましょう。
肘の負傷で後遺障害認定で14級に認定されない理由

肘の負傷により疼痛や腫れ、痺れなどの症状が残ったとしても、後遺障害等級認定で非該当になってしまう可能性があります。
それには、主に以下のような理由が考えられます。
症状が軽微
後遺障害14級の認定を受けるには、将来にわたって回復が困難な症状であるといえなければなりません。
肘に疼痛や腫れ、痺れなどの症状が残ったとしても、軽微な症状だと後遺障害14級の認定を受けるのは難しいといえます。
医師への伝え方によっては、カルテなどに軽微な症状である旨の記載がなされてしまいますので、疼痛や腫れ、痺れなどの症状がある場合には、明確かつ具体的に症状を説明するようにしてください。
事故との因果関係が不明確
後遺障害14級の認定を受けるには、事故と残存した症状との間に因果関係があることが必要です。
肘に疼痛や腫れ、痺れなどの症状が残っていたとしても、事故との因果関係が認められなければ非該当となります。
事故との因果関係が否定される可能性のある事情としては、以下のようなものが挙げられます。
・事故発生直後に病院を受診せず、しばらく経ってから治療を開始した
・事故当初は、肘の疼痛や腫れ、痺れなどを訴えていなかった
・事故の程度が軽微
・治療が途中で中断している期間がある
・医師の指示なく、鍼灸院などの非医療機関への受診を行った
このような事情がある場合には、後遺障害等級申請をしても非該当になる可能性が高いです。
治療期間が短い
治療期間が短い、治療日数が少ない、通院頻度が低いなどの事情があると非該当になる可能性があります。
なぜなら、これらの事情があると治療の必要性が乏しく、後遺症が残るような重篤な怪我ではなかったと判断されてしまうからです。
どのくらいの治療期間が必要であるかは、怪我の内容や程度によって異なるため、一概にはいえませんが、最低でも6か月以上は通院している必要があるでしょう。
書類の不備や不足がある
後遺障害等級認定は、基本的には書類審査による方法で行われますので、提出書類の不備や不足があると非該当になる可能性があります。
後遺障害等級申請の際に提出する書類の中でも特に重要になるのが「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書には、医師に伝えた自覚症状の内容や検査結果などが記載されていますので、提出前に被害者自身でも内容をしっかりとチェックするようにしましょう。
診療録内容が不十分である
通院頻度や画像検査などの情報が十分だとしても、14級獲得に至らない事があります。それは通院中の診療録内容が乏しい場合です。
多忙な外来でどうしても診療内容が乏しくなってしまうことは往々にしてあります。
症状の訴えをきちんとしない場合、例えば「症状はしっかり残っていますが、日常は問題ありません」と訴えたとしても、診療録に「日常は問題ない」と切り取られてしまえば、一見症状が軽快しているようにも見えます。
また「特に変わらないですね(特に変わらず症状が続いている)」と訴えても「変わりなし」としてよくも悪くもわからない記載になります。
この場合、概ね症状が安定している良好な状況と受け取られがちです。
また「普通にしていれば問題ないですが、電話が長引くととつらいことも」と伝えた場合「普通にしていれば問題なし」と記載されることもあります。
訴え自体は、『特定の肢位により症状が増悪する』という典型的な理学所見(ストレス検査)ではあるものの、症状自体の訴えが曖昧の為、本来なら重要な「電話が長引くと~」という重要な訴えが埋もれてしまいます。
また実際診療録に「電話が~」と記載されていても、証拠能力として不十分となります。
医師が取得する「理学所見・徒手ストレステスト」として記載される必要があります。
この例の場合は「肘関節の屈曲テスト」という神経障害を診断するために重要な理学所見です。
「電話が長引く=肘関節屈曲状態が続く」と状態としては同じなのですが、医師が記載する「理学所見」と訴えと記載される「主訴」では大きく証拠能力に差が出ます。
ですので、受診に際しては、「どのような症状が」「どのようなときによくなる(悪くなる)」「受傷時と現在で症状がどうなったか」などを手間ではありますが、毎回の受診に際し、症状の正常や、それによりどれほど困っているかを曖昧な表現はさけ具体的に、端的に伝え、医師に「所見をとる必要がありそうだ」と理解させる事が大切です。
医師も訴えの無いところからは疾患を見つけることができません。
乏しい訴えや曖昧な表現は症状の本態を不明瞭にしてしまい、正確な診断がなされないため、後遺障害非該当となるケースも珍しくありません。
画像所見による異常がわかりづらい
MRI、CT、レントゲンなどの画像所見で異常がみられたとしても、異常がわかりづらいと非該当になる可能性があります。
特に、MRIは、テスラと呼ばれる磁束密度の単位によって画質の程度が変わってきます。
0.5~1.5テスラのMRIでは、はっきりと異常所見が映らない可能性もありますので、1.5テスラ以上の解像度を有するMRIを設置している医療機関を受診するとよいでしょう。
関連記事:後遺障害認定のデメリットとは?|診断書を書いてもらえない時の対処法も解説!
肘の負傷での後遺障害等級認定事例

以下では、肘の負傷で後遺障害等級が認定された事例を紹介します。
橈側手根伸筋損傷と残存血腫による神経障害(非該当→14級認定)
概要
加害車両のミラーが被害者の腕に接触した事故。その結果、被害者はしびれ、疼痛、筋力低下を訴えた。
しかし、相手方からは事故と残存症状の因果関係を否定され、訴訟となった。
依頼内容
事故と残存症状の因果関係について、医師意見書による裏付けが求められた。
意見
MRI画像では、橈側手根伸筋内に血腫が認められた。
また、周囲の損傷を伴わず橈側手根伸筋のみに外傷が生じるとは考えにくく、脱神経による変化と考えられる。
受傷機序、臨床経過、画像所見の3点から、事故と症状の因果関係を主張。
一定期間が経過後も画像から血腫が存在していることは明らかであり、圧迫によって生じた神経症状は今後改善する見込みはないとして、症状の永続性についても主張した。
鑑定結果
画像所見から陳旧性の血腫および橈側手根伸筋の支配神経が障害されており、他覚所見が存在すると判断。
また、血腫を生じるような外力を受けた記録は事故以外になく、受傷箇所も符合するため、本件事故に関連した受傷であると判断した。
慢性化した血腫の自然消退は期待しにくく、永続的に症状が残存すると意見した。
結果
14級該当の認定を受けることができた。
交通事故意見書(非骨傷性頸髄損傷)⇒非該当から14級認定
停車中の被害車両に、制限速度を超えた加害車両が追突した玉突き事故。
被害者は事故後から一貫して、頸部痛、右肘関節から右手指にかけてのしびれなどを訴えた。
自賠責は、画像や診断書から「有意な神経学的所見に乏しい」と判断し、また「経年性の変性所見」とも認定できるため、後遺障害非該当と判断した。
争点
MRI画像から認められる第5頚椎、第6頚椎間の椎間膨隆が本件事故を起因とするものか。
被害者が訴える頸部痛、右肘関節から右手指にかけてのしびれが「将来においても回復が困難と見込まれる障害」、すなわち「後遺障害」に該当するか。
意見
第5頚椎と第6頚椎に椎間板膨隆が認められ、右上肢の疼痛及び右手指のしびれ等の神経症状は本件事故以降に一気に発生しており、当該神経症状と画像所見との整合性が認められた。
被害者は、右上肢の疼痛及び右手指のしびれを訴えており、事故態様から頸椎が過伸展されヘッドレストに強く頭をうちつけたと考えられる。
受傷当初から後遺障害診断書作成時まで被害者の症状は一貫しており、当該症状は、末梢神経性頸椎捻挫の症状に合致するものであり、将来における回復は困難な症状、後遺障害に該当すると言える。
鑑定結果
本件事故以降、それ以前なかった神経症状が発生していることから、MRI 画像から認められる第5頚椎、第6頚椎間の椎間膨隆は本件事故を起因とするものであるといえ、この椎間膨隆が被害者の上肢神経症状を呈した可能性は否定できない。
この上肢神経症状は、整形外科医であれば必ず考慮に入れるべき、末梢神経性頸椎捻挫よる症状と合致する。
末梢神経性頸椎捻挫は上肢の症状、特に手のしびれが残存する例が多いことは参考文献においても認められているところ、本件被害者の症状もこれにあたる。
よって、本件被害者の症状は、「将来においても回復が困難と見込まれる障害」にあたる。
以上のことから、後遺障害非該当とする本件自賠責の判断は誤りであると意見した。
結果
この意見書を付して異議申立てを行った結果、後遺障害等級の認定が「非該当」から「14級」に認定された。
後遺障害等級に関する相談ならYKRメディカルコンサルトまで
肘の負傷を理由に後遺障害等級認定を受けるには、専門的な経験や知識を有する専門家のサポートが不可欠です。
特に、後遺障害等級認定の手続きは、基本的には書類審査になりますので、適切な資料や証拠を提出できるかどうかによって認定結果が大きく左右されます。
YKRメディカルコンサルトでは、交通事故分野を専門とする意思が意見書の作成や画像評価を通じて、適正な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしています。
肘の負傷に関して後遺障害14級が認定された事例も数多くありますので、肘の負傷に関する後遺障害等級認定をお考えの方は、YKRメディカルコンサルトまでお気軽にお問い合わせください。
後遺障害等級14級や12級の認定を受けられた事例も数多くありますので、膝の負傷に関する後遺障害等級認定でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事:後遺障害が認定されない5つの理由|認定されるための対処法とは
まとめ
交通事故により肘を負傷し、疼痛や腫れ、痺れなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害14級が認定される可能性があります。
後遺障害等級認定の可能性を高めるためには、専門家のサポートが必要になりますので、後遺障害等級申請をお考えの方または後遺障害等級申請の結果、非該当になってしまった方は、ぜひ一度YKRメディカルコンサルタントまでお問い合わせください。