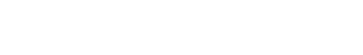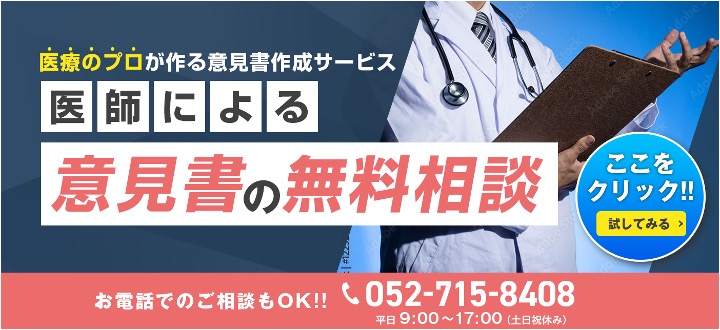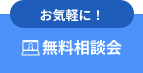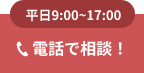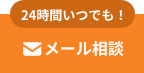交通事故における靱帯損傷診断 ~ MRIとCTを使い分ける理由と法的評価への影響 ~

交通事故では、骨折などの目に見える外傷だけでなく、関節を安定させる「靱帯(じんたい)」の損傷も多く発生します。
例えば追突事故によるむち打ち(頚椎捻挫)や、正面衝突で膝を打ち付けた際の前十字靱帯損傷などが典型例です。
ところが、これら靱帯の損傷はレントゲン(X線)では映らないため見逃されやすく、事故直後の診察では異常が確認できないケースも少なくありません。
実際、事故直後の急性期には画像上明らかな損傷所見がなく、診断が遅れてしまうことがあるのです。
交通事故の被害者にとって、靱帯損傷が適切に診断されるかどうかは、その後の後遺障害等級の認定や賠償金に直結する重要なポイントです。
自覚症状(痛みや不安定感など)だけでは客観性に欠けるため、MRIやCTといった画像検査による裏付けが必要になります。
本記事では、医学的視点と法律的視点の両面から、交通事故による靱帯損傷の診断でMRIとCTをどう使い分けるべきかを解説します。
交通事故案件を扱う弁護士や法律家の方々に向けて、画像診断の重要性とその実務への活かし方を分かりやすく紹介し、適正な後遺障害評価・賠償獲得につなげるヒントを提供します。
目次
靱帯損傷とは何か

靱帯とは、関節で骨と骨をつなぎ関節の安定性を保つ、丈夫な線維性の組織です。
過度の力が加わると靱帯は伸ばされるか断裂し、いわゆる捻挫(ねんざ)や靱帯断裂となります。
靱帯損傷が起きると、以下のような症状が現れます。
痛みと腫れ
損傷部位には激しい痛みが走り、ほどなく腫脹(はれ)が出現します。周囲に内出血が起これば皮下にアザが出ることもあります。
関節の不安定感
靱帯が断裂すると関節をしっかり支えられなくなり、「関節が外れそう」「力が入らない」といった不安定感が生じます。ひどい場合は関節がガクガクして正常に動かせなくなります。
可動域制限
痛みや腫れ、あるいは関節内の出血の影響で、その関節を動かしにくくなります。
軽度の損傷(部分断裂)では動かせる範囲が多少狭まる程度ですが、重度(完全断裂)では関節が思うように動かせなくなります。 靱帯損傷にも程度があります。
軽いものはⅠ度(軽度:靱帯が若干伸びている状態)とも呼ばれ、靱帯が伸びただけで断裂はありません。
中程度はⅡ度(部分断裂)、重度になるとⅢ度(完全断裂)で靱帯が完全に切れてしまった状態です。
部分断裂では痛みは強いものの関節はある程度安定していますが、完全断裂では関節が著しく不安定になります。
交通事故では、日常生活では起こりにくい強い衝撃やねじれが加わるため、身体の様々な部位の靱帯損傷が発生します。
代表的な例として次のようなケースが挙げられます。
膝の靱帯損傷
シートに膝を打ちつけたり、急激なねじれが生じたりすると、膝関節の前十字靱帯(ACL)や後十字靱帯(PCL)が断裂することがあります。
特に後十字靱帯は曲げた膝をダッシュボードに強打する機序で損傷しやすく、実際に「ダッシュボード損傷」とも呼ばれる典型的な事故形態です。
これにより膝がぐらついて歩行困難になるケースもあります。
足関節の靱帯損傷
車内で足首をひねったり、踏ん張った際に足関節の靱帯(外側靱帯複合体など)を損傷することがあります。
足関節捻挫の延長で靱帯が部分断裂し、後に走ったり踏み込んだりすると足首が不安定になるといった後遺症を残す場合があります。
手関節の靱帯損傷
ハンドルを強く握った状態で衝撃を受けたり、手を突いてしまった場合、手首の靱帯(手関節の靱帯複合体)や三角線維軟骨複合体(TFCC)を傷めることがあります。
初めは単なる捻挫と診断されても、実は手関節の支持組織が断裂していて手首の可動域や握力に影響が出るケースもあります。
頚椎・腰椎の靱帯損傷
いわゆるむち打ち症(頚椎捻挫)では、首の後ろ側の靱帯や筋が伸展・損傷します。
レントゲンでは骨に異常がなくても痛みや可動域制限が残るのは、靱帯や軟部組織の損傷によるものです。
腰椎でも、シートベルト着用時の急激な前傾や後傾で脊椎周囲の靱帯が傷つき、慢性的な腰痛や不安定性につながる場合があります。
このように、交通事故による靱帯損傷は身体の各部で起こり得ます。
適切に診断し治療しなければ、関節の不安定による軟骨損傷や二次的な障害(例えば膝靱帯断裂を放置した結果の半月板損傷や変形性関節症など)を招く恐れがあります。
そのため、早期発見・対処が重要ですが、事故直後の現場では見逃されることも多いのが現状です。
関連記事:肘の負傷で後遺障害14級に該当する症状とは?認定基準や非該当の理由を解説
交通外傷における靱帯損傷の特徴と問題点

交通事故直後の緊急診療では、命に関わる外傷の有無や骨折の確認が優先されます。
レントゲンや場合によってはCTで骨の異常をチェックし、明らかな骨折や脱臼がなければひとまず「捻挫」「打撲」といった診断で経過を見ることも少なくありません。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。靱帯損傷は骨の異常ではないため、初期検査で発見されにくいのです。
実際、ある研究でも「靱帯や骨の損傷が事故当初の画像検査では特定できず、診断の遅れや不適切な治療につながることがある」と指摘されています。
交通外傷において靱帯損傷の診断が遅れがちな理由として、次のような点が挙げられます。
画像検査で映らない初期段階
靱帯損傷はX線では見えず、CTでも捉えにくい軟部組織の損傷です。
MRIで確認できるとはいえ、事故直後すぐにMRI撮影が行われることは稀で、多くは痛み止めや安静といった保存療法で様子を見ます。
その間に腫れや痛みが一時的に引いてしまい、「大したことない」と見過ごされる恐れがあります。
特に頚椎捻挫(むち打ち)は、受傷直後は興奮状態で痛みを感じにくく、翌日以降に症状が出現・悪化するケースもあります。
腫脹や疼痛で診察が困難
事故直後は患部が腫れて痛みも強いため、整形外科的テスト(関節の動揺性を見るテスト等)が十分に行えません。
「疑わしいが痛みが強く検査できない」というまま時間が経ち、腫れが引く頃には受傷から数週間経ってようやく詳しい評価ができる、ということもあります。
他の重傷に隠れる
交通事故では多発外傷のこともあり、命に関わる怪我や明らかな骨折の治療が優先されます。
その結果、靱帯損傷は二の次になり、退院後やリハビリ中になって「関節の不安定に気づく」といった事態も起こり得ます。
被害者側の見落とし
被害直後は本人もパニックになっており、痛みや不調をうまく伝えられないことがあります。
例えば膝や足首の違和感があっても、その場では全身打撲の痛みで気づかず、数日後に歩けないほど膝が不安定になって発覚するといったケースです。
以上のように、事故による靱帯損傷は「その場では見えない怪我」として潜在化しやすいのです。
その結果、診断が遅れるだけでなく、適切な治療開始が遅延し症状が悪化するリスクもあります。
例えばACL(前十字靱帯)断裂が見逃されて放置されると、膝の不安定性から軟骨や半月板を傷め、将来的に変形性関節症へ進行する可能性があります。
また、診断の遅れは法的にも不利に働きかねません。
事故から時間が経ってから「実は靱帯が切れていた」と判明すると、保険会社から「本当に事故が原因か?」と因果関係を疑われる要因にもなり得ます。
こうした問題を防ぐためには、MRIやCTによる早期診断が極めて重要となります。
次章から、靱帯損傷の診断におけるMRIとCTそれぞれの役割と特徴を詳しく見ていきましょう。
靱帯損傷の診断におけるMRIの役割

MRI(磁気共鳴画像)は強力な磁石と電波を利用して体内の詳細な断面画像を得る検査で、軟部組織の描出に非常に優れています。
レントゲンやCTが主に骨の情報を映し出すのに対し、MRIでは靱帯・腱・筋肉・軟骨・椎間板などの水分を多く含む組織を鮮明に描写できます。
そのため、靱帯が切れているかどうか、部分的な断裂か、周囲に炎症や出血(血腫)があるかなどを直接観察することが可能です。
実際、MRIは靱帯損傷の検出に最も優れた方法とされ、微細な損傷の有無を確認する上で他の画像検査より有用であると報告されています。
MRI画像上で靱帯損傷を診断する際には、以下のような所見(サイン)が重視されます。
靱帯そのものの状態(一次的所見)
正常な靱帯はMRIでは黒く細い帯状に映りますが、断裂するとその部位に液体が溜まるため高い信号(白く写る部分)として描出されます。
また靱帯が連続していない(途中で途切れている)所見や、本来の走行からずれて不自然な位置にある所見も断裂の証拠です。
完全断裂では靱帯の線が消失し、部分断裂では靱帯内に部分的な高信号域(損傷による浮腫)が見られます。
間接的な所見(二次的所見)
靱帯そのもの以外にも、周囲組織の変化から靱帯損傷を推測できます。
例えば関節内に液体が溜まる関節血腫(effusion)や、骨の微細な損傷による骨挫傷(こつざしょう)です。
靱帯が断裂するほどの外力が加わると、骨同士がぶつかりあって骨内部に微小な損傷が生じることがあります。
これはMRIでは骨髄内の浮腫(むくみ)として白く映り、骨挫傷(Bone bruise)と呼ばれます。
骨挫傷はX線や通常のCTでは映らず、MRIでのみ確認できる所見です。
このような間接所見があると、靱帯損傷の可能性が高いと判断されます。
以上のように、MRIは靱帯そのものの断裂状態を直接描写できる唯一の検査です。
例えば膝ACL断裂では、MRIで靱帯の連続性消失や「empty notch sign(大腿骨側付着部の靱帯欠損に伴うノッチ部の高信号域)」が認められますし、足首の靱帯損傷でも周囲の腫れや靱帯の不整像から診断が可能です。
加えてMRIは放射線被曝がないため、被曝を避けたい若年者や妊婦の検査にも適しています。
このように、MRIであれば靱帯断裂そのものと、それによる骨への影響まで一度の検査で把握できるのです。
靱帯損傷が疑われるケースでは、MRI検査を行うことで診断の確実性が飛躍的に高まります。 もっとも、MRIも万能ではありません。
撮影時期によっては損傷がはっきり映らない場合もあります。
例えば事故直後すぐのMRIでは、炎症や出血が十分に広がっておらず「偽陰性(見逃し)」となる可能性があるとされています。
むち打ち症のケースでは「初診時にMRIは必ずしも有用でない(偽陰性が多い)」「慢性期に症状が残る場合に検査する」といった考えもあります。
したがって、MRI検査は適切なタイミングで実施することが重要です。
受傷直後に異常がなくても症状が続く場合、時間をおいて再度MRIを撮影する、あるいは造影MRI(MRI検査時に造影剤を用いて微小な損傷を強調する手法)を検討するといった対応も有効です。
実際、初回MRIで見落とされた手首のTFCC損傷が、造影MRIで判明し後遺障害等級の認定が上がったケースも聞いています。
このようにMRI検査を的確に活用することで、見逃されていた靱帯損傷を拾い上げ、適切な治療・補償につなげることが可能となります。
靱帯損傷の診断におけるCTの役割

CT(コンピュータ断層撮影)はX線を利用して体の断面を撮影する検査で、主に骨構造の詳細な評価に優れています。
MRIと異なり放射線被曝がありますが、撮影時間が短く広範囲を素早くスキャンできるため、交通事故の初期診療では全身のCTチェックが行われることも多いです。
CT画像では骨折の有無や位置関係を立体的に把握でき、微細な骨片やわずかな骨のずれも見逃しにくいという利点があります。
では、靱帯損傷の診断にCTはどのように関与するのでしょうか。 まず押さえておきたいのは、CTでは靱帯そのものは鮮明に写らないという点です。
靱帯は軟部組織でありX線をほとんど通してしまうため、CT画像上ではコントラストが付きにくく判別が困難です。
したがって、MRIのように「靱帯が途切れている」と直接描写することはできません。
しかしCTは、靱帯損傷に伴って生じる骨の異常所見を捉えることで間接的に診断に寄与します。
例えば以下のようなケースです。
剥離骨折の検出
靱帯が骨に付着する部分で断裂した場合、骨の一部を引き剥がしてしまうことがあります。(骨片付着型の靱帯断裂)
CTはこうした小さな剥離骨折を高精細に描き出せます。
レントゲンでは見落とすような数ミリの骨片でもCTなら検出可能で、その骨片の存在が「ここに靱帯断裂があった」ことを示す有力な手がかりとなります。
関節のズレ(脱臼・亜脱臼)の評価
靱帯が切れると関節が通常とは異なる位置関係になります。
CTでは関節の各骨の位置を3次元的に評価できるため、骨同士の隙間の拡大や位置ずれを確認できます。
例えば足のリスフラン関節靱帯損傷では、第一・第二中足骨と楔状骨の位置関係に微妙なズレが生じますが、CTで健側と比較することでそのズレを定量評価できます。
このズレが靱帯損傷の間接所見となります。
軟骨・骨盤の損傷確認
関節内の骨折(関節軟骨ごと骨が割れる骨軟骨骨折)や、骨のひび(亀裂骨折)はCTの方がMRIより全体像を把握することが可能です。
一方で極めて小さな損傷は捉えられません。
靱帯損傷に合併してそうした骨損傷が起きている場合、手術適応の判断など治療方針にも関わるためCTによる評価が不可欠です。
要するに、CTは「骨を見る検査」として、靱帯損傷に伴う骨の変化を捉える役割を果たします。
MRIが靱帯断裂のソフトサイン(軟部組織サイン)を映し出すのに対し、CTはハードサイン(骨のサイン)を提供すると言えます。
両者を組み合わせることで診断の精度が一層高まります。
特に脊椎などでは、MRIで脊髄や靱帯の損傷を確認すると同時に、CTで骨折や変形をチェックすることが望ましいとされています。
このように、CTはレントゲンでは見逃すような微細な骨損傷を発見することができ、結果的に「靱帯が切れるほどの外力が加わった証拠」を示すことができます。
交通事故直後の救急診療では、まずCTで生命に関わる損傷や骨折の有無をスクリーニングし、その後MRIで軟部組織の精査を行うという手順が取られることも多いです。
CTで骨の異常が見つかった場合は速やかに処置し、骨に異常がなくても痛みが強ければMRI検査を追加して靱帯や軟部組織のダメージを評価するといった流れになります。
まとめると、MRIは靱帯・軟部組織の評価に優れ、CTは骨の評価に優れるという役割分担があります。MRIとCTそれぞれのメリット・デメリットを簡単に整理すると以下のようになります。
MRIのメリット
靱帯・腱・軟骨・神経など軟部組織の状態を直接確認できる。骨挫傷や椎間板損傷なども描出可能。
放射線被曝がない。
MRIのデメリット
撮影時間が長く(20~40分程度)、閉所が苦手な人には苦痛を伴う。
金属が体内にある患者(ペースメーカー等)には使用不可。急性期の検査では偽陰性の可能性がある。検査費用が高価。
CTのメリット
撮影が迅速(数分以内)であり、重症外傷患者でも短時間で全身のスキャンが可能。骨折や骨片の位置関係を高精度で把握できる。
医療機関に広く普及しており利用しやすい。
CTのデメリット
放射線被曝がある。軟部組織の損傷は捉えにくく、靱帯断裂の直接診断には向かない。
小さな骨折は描出されないことがある。MRIに比べて軟部の描出コントラストが劣るため、椎間板ヘルニアや脊髄損傷の様に軟部組織の評価には不向き。
実際の臨床では、まずレントゲンで骨折の有無を確認→靱帯損傷の疑いあればMRI→必要に応じてCT追加という順で検査が行われることが多いです。
重度の衝撃が加わった事故では最初からCTとMRIの両方を行うケースもあります。重要なのは、症例ごとに適切な検査を選択することです。
例えば、明らかに関節不安定性があり靱帯断裂が疑われるのにMRIを撮らなかったり、逆に骨折の疑いが強いのにMRIだけで済ませてCTを撮らない、といった判断ミスは避けねばなりません。
医師と相談しつつ、必要な画像検査を適宜組み合わせることで、診断の精度と治療・証明の万全さを両立させることができます。
次章では、こうした画像検査の結果を後遺障害の等級認定や裁判でどう評価・活用するか、法律的観点から掘り下げます。
画像診断と後遺障害認定

交通事故による後遺症が残った場合、日本の自賠責保険などでは後遺障害等級の認定を受けることで賠償額(逸失利益や慰謝料)が算定されます。
等級認定にあたっては、被害者の症状がどの程度残存しているかを医学的に評価する必要がありますが、ここで重要になるのが医学的客観性、すなわち他覚所見の有無です。
単に「痛い」「しびれる」といった本人の訴え(自覚症状)だけでは等級認定は困難であり、レントゲン・MRI・CTなどの画像所見や検査所見による裏付けが求められます。
実務上、MRIやCTで確認された異常所見があるかどうかが後遺障害等級を大きく左右します。
例えば頚椎捻挫(むち打ち症)の場合、MRI画像上で椎間板ヘルニアや神経根の圧迫所見が認められると、それが他覚的所見となり12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当し得ます。
逆に画像上明確な異常がない場合は、一段低い14級9号(局部に神経症状を残すもの)にとどまるか、症状が軽微だと等級非該当となる可能性もあります。
実際の認定実務では「痛みの程度」よりも「画像所見の有無」に重きが置かれており、MRI画像上で靱帯損傷やヘルニアがはっきり確認できれば12級が認定されやすいのが実情です。
交通事故による靱帯損傷でも同様で、例えば膝や足関節の靱帯断裂がMRIで確認でき、それによって関節の可動域制限や不安定性が残存している場合には、12級13号が認定されるケースが多く見られます。
反対に、靱帯損傷が疑われても画像上所見が乏しい場合には、「医学的に裏付けられた後遺障害」と評価されず等級非該当と判断されたり、本来なら12級相当の症状でも14級にとどめられたりするリスクがあります。
ある専門弁護士の解説でも「客観的な画像が不十分だと後遺症の存在が証明されないとして、妥当な等級が認定されない場合や、非該当になる恐れすらある」と指摘されています。
以上を踏まえると、後遺障害の申請においてMRI・CT画像を提出することは今や必須と言えます。
自賠責の等級認定実務では、提出資料の中でも画像所見が特に重視される傾向があります。
実務では、主治医に後遺障害診断書を書いてもらう際にMRIやCTの検査結果を添付し、その所見を診断書本文中にも記載してもらうよう依頼することが重要です。
「○○靱帯断裂後の手術痕あり」「MRIにて△△靱帯の部分断裂を認む」など具体的な記載があれば、調査事務所(認定機関)も判断を下しやすくなります。
実際、脊髄損傷の後遺障害認定では「MRI画像が欠かせない。
MRIがない場合、適切な等級認定は極めて困難」とまで言われています。それほどまでに医学的客観性=画像証拠が重視されているのです。
裁判や示談交渉の場面でも、MRI・CTの画像所見は大きな説得力を持ちます。
裁判官や保険会社にとって、写真で示された損傷は言葉による主張よりも直感的に理解しやすいものです。
「このMRIで白く写っている部分が骨の中の損傷(骨挫傷)です」「ここに写る黒い筋が途切れているのが靱帯断裂の所見です」と専門的に説明すれば、事故による損傷の実態が明確に伝わります。
また、画像所見があれば医師の意見書(事故との因果関係についての所見)も書いてもらいやすくなります。
例えば「事故○ヶ月後のMRIで確認された靱帯損傷所見は、本件事故による急性期損傷と医学的に矛盾しない」等のコメントをもらえれば、時間が経って発見された損傷でも事故との関連性を補強できます。
結論として、交通事故における後遺障害の主張には「画像が語る証拠力」が不可欠です。
MRI・CTを適切に活用し、その結果を医学的証拠として残すことで、公平な後遺障害等級の獲得や妥当な賠償金の算定につなげることができるのです。
関連記事:後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?
弁護士が画像診断を評価するときの注意点

交通事故案件を扱う弁護士にとって、MRIやCTの画像所見を正しく理解し評価することは極めて重要です。
しかし、医学の専門家でない弁護士が画像を読み解くのは簡単ではありません。
経験が浅いと、画像の見方や所見の意味を誤って判断してしまう恐れもあります。
そこで、弁護士が画像診断結果を扱う際のポイントをいくつか挙げます。
放射線科レポートの入手と精読
まず、MRIやCTを撮影した際には、放射線科医による読影レポートが作成されます。
このレポートには、検査で認められた所見(異常所見の有無や内容)が詳細に記載されています。
弁護士は必ずこのレポートを取り寄せ、記載内容を確認しましょう。
専門用語が並びますが、「tear(断裂)」「sprain(捻挫)」「effusion(関節液貯留)」「fracture(骨折)」「no abnormality(異常なし)」といったキーワードを押さえるだけでも大まかな状況は把握できます。
もし内容が難解な場合は、医師に解説してもらったり、医学に詳しい弁護士に意見を求めることも有益です。
必要な検査が実施されているかチェック
治療経過の中で、本来行うべき検査が省略されていないかを確認します。
例えば膝に明らかな不安定性が残っているのにMRIを撮っていなかったり、脊椎に強い痛みや神経症状があるのにCTしか行っていなかったりする場合です。
そうした場合には、主治医に依頼して追加検査を検討してもらう、あるいは専門医にセカンドオピニオンを求めることをクライアントに提案するべきです。
適切な検査を怠ると、前述のように後遺障害等級で不利益を被る可能性があります。
弁護士自身が医学的見地から検査の必要性を指摘できれば理想ですが、難しい場合は信頼できる医師と連携し判断することが大切です。
医療照会で不明点を解消
診断書やレポートに専門的な所見が書かれていて理解が追いつかない場合や、事故との因果関係について医師の見解を明らかにしたい場合は、医療照会制度を活用しましょう。
具体的な質問を箇条書きにして主治医に回答してもらうものです。
「MRI所見に記載の○○とはどのような意味か」「この所見は事故による急性期損傷と整合するか」といったポイントを尋ねることで、医学的争点をクリアにできます。
医療照会の回答は証拠書類としても利用可能であり、裁判になった際にも医師の口頭意見より証明力が高い場合があります。
画像そのものの活用
近年はデジタル画像(JPEGやDICOMデータ)を入手しやすくなっており、裁判資料としてMRIやCTの画像を提出する例も増えています。
弁護士は主治医や放射線科に依頼して画像データをもらい、自分でも所見箇所を確認してみるとよいでしょう。
明らかな断裂や骨折が写っている場合は、パワーポイント資料などに貼り付けて視覚的資料として示すことで、示談交渉でも相手保険会社にインパクトを与えられます。
ただし、素人判断で画像を解釈するのは危険なので、画像に注釈を入れる際は必ず医師の確認を取りましょう。
専門知識のアップデート
交通事故案件を扱う以上、弁護士も一定の医学知識を身につけておく必要があります。
特に画像診断については日進月歩で、新しい撮影技術や評価方法が登場しています。
裁判例でも医学的知見の不足から不利な展開になることがあります。
継続的に勉強会や専門書で知識をアップデートし、少なくとも典型的な画像所見(ヘルニア像、靱帯断裂像、骨挫傷像など)は理解できるよう努めましょう。
難しい場合は、医療専門の弁護士と協働したりコンサルタント医師に助言を仰ぐなど、チームで知識を補完するのも有効です。
以上の点に留意しながら画像診断と向き合えば、弁護士として事故被害者の後遺障害を適切に主張・立証する力が格段に高まります。
経験豊富な弁護士ほど「画像所見のどこを見れば等級が見込めるか」「どの検査を追加すれば有利な証拠が得られるか」を把握しており、実際の賠償交渉でもその差が結果に表れます。
クライアントのためにも、医学と法律の架け橋となる知識・スキルを磨いていきましょう。
交通事故の実務で頻繁に問題になる事例と対処法

Q1: 「MRIなどの画像所見で異常なし」と言われたが痛みが残る場合、後遺障害は認められる?
A1: 画像に明確な異常所見がなくても、症状が客観的に証明できないだけで後遺障害が一切認められないわけではありません。
例えば頚椎捻挫(むち打ち症)では、MRIでヘルニア等が確認できなくても、他の神経学的検査や整形外科医の診断所見から14級9号が認定されるケースも存在します。
ただし、等級はやはり低く抑えられがちで、「画像上異常なし=重症ではない」という先入観を覆すのは難しいのが実情です。
こうした場合の対処法としては、次のようなものがあります。
追加検査の検討
初回のMRIで異常が見られなくても、症状が強い場合には造影MRIや高磁場MRI(1.5〜3テスラMRI)など、より精度の高い検査を検討します。
実際に、初回MRIで所見がなく14級と判定されたケースで、造影MRIにより靱帯損傷(手首のTFCC断裂)が判明し、異議申立てで12級13号に等級が上がった例があります。
このように二度目の検査で証拠を掴むことも可能です。
他覚所見の蓄積
画像以外の他覚的検査も総動員します。
整形外科的テストでの陽性所見(関節の不安定性テストや徒手検査の結果)、神経学的所見(腱反射の減弱や筋力低下)、電気診断(神経伝導速度検査の異常)など、第三者から見て確認できる異常を記録します。
それらを組み合わせて総合的に後遺障害を裏付ける戦略です。
一つの所見だけでは説得力に欠ける場合でも、複数の所見を積み上げれば認定の可能性が高まります。
症状経過の整合性
受傷直後から現在まで、一貫して同じ部位の痛みや不調を訴えていることを医療記録に残すのも重要です。
事故後しばらく経ってから「やっぱり痛い」と言い出したのでは、保険会社も因果関係を疑います。
症状固定までの間、定期的に通院してその都度症状を訴え、カルテや診断書に記録してもらいましょう。
画像に異常が写らなくとも、症状の一貫性と持続性が証明できれば後遺障害が認められる余地は十分あります。
Q2: 事故からかなり経って靱帯損傷が判明した。保険会社に「事故と無関係では」と言われているが?
A2: 診断の遅れによって因果関係を疑われるケースは確かに存在します。
しかし、事故後の経過を丁寧に辿れば、受傷当初からの症状の連続性や医学的な蓋然性を示すことが可能です。
まず、事故直後から該当部位の痛みや機能障害があり、それが治まったり別の要因で再発したりしたわけではなくずっと続いていたことを主張します。
その上で、医師の意見書などで「当初画像所見に乏しかったが、〇〇の理由で見逃されていた可能性が高い。
現在確認された△△靱帯損傷は本件事故起因と考えるのが合理的である」旨の説明を添えると効果的です。
医学的には、先述のとおり事故直後に画像に写らない靱帯損傷が後から明らかになることは珍しくありません。
例えば膝ACL損傷でも初期は腫脹が強くMRIで評価しきれず、時間経過後にようやく確定診断に至ることがあります。
このような医学的事例を示し、「診断が遅れただけで事故との因果関係は明白」というロジックを組み立てましょう。
保険会社も医学的な説明には反論しにくいため、有効な反証がなければ最終的には認めざるを得なくなります。
なお、診断遅れ自体によって症状が悪化した場合(例:靱帯断裂の放置により関節変形が進んだ等)は、適切に治療していれば避けられた二次被害として過失相殺や損益相殺の議論になる可能性もあります。
しかし基本的には、被害者に落ち度なく医師側の判断で経過観察となった結果の遅れであれば、被害者に不利に扱われることはありません。
重要なのは、「事故から発覚までの医学的ストーリー」をきちんと示すことです。
Q3: 時間の経過とともに症状(障害の程度)が悪化しているが、それを証明するには?
A3: 後遺障害認定は原則として症状固定時点の状態で判断されますが、症状が徐々に悪化するケースでは経時的変化を示すことも大切です。
例えば、事故後半年のMRIでは部分断裂に見えた靱帯が、その後完全断裂状態になり関節の変形が進んだ場合などです。
これを証明するには、複数時点の検査結果を比較するのが有効です。
事故直後、症状固定直前、症状固定後といった具合にMRI画像を時系列で並べると、靱帯の状態や関節の変化が視覚的に示せます。
医師に所見を書いてもらう際も、「初回MRIでは○○であったが、△ヶ月後のMRIでは明らかに状態が悪化している」などと記載してもらうと良いでしょう。
また、痛みや可動域制限といった機能面の悪化については、リハビリ記録や経過診断書にその旨を詳細に残してもらいます。
例えば「膝関節の可動域:当初120度→現在90度」「徒手検査:〇月には陰性だったLachmanテストが△月には陽性」といった記録があれば、説得力のある経時変化の証拠となります。
裁判では、症状固定後であっても症状が変化している場合には、その後の資料提出も許されることがあります。
症状悪化に応じて再度後遺障害等級の見直し(異議申立て)を行うことも検討すべきでしょう。
実際、前述のTFCC損傷の例では、症状固定後に造影MRIで新たな所見を得て異議申立てを行い、等級が14級から12級に変更されたケースがあります。
このように粘り強く新証拠を提示し再評価を求めることで、より適切な補償を勝ち取れる場合もあります。
関連記事:膝の負傷で後遺障害14級に認定されるケースとは|12級に該当するケースも?
おわりに
交通事故における靱帯損傷の診断と、その法的評価への影響について解説してきました。ポイントを振り返ると以下のようになります。
靱帯損傷は見逃されやすい
レントゲンに写らない軟部組織の損傷であり、事故直後には発見困難なことが多い。
しかし放置すると関節の不安定や二次障害を招くため、注意深い診察と経過観察が必要。
MRIとCTを使い分け
靱帯や軟部組織を見るにはMRI、骨の微細損傷や位置関係を見るにはCTが有効。
両者のメリットを活かし、適切なタイミングで検査を組み合わせることが早期診断・治療につながる。
画像所見が後遺障害認定を左右
後遺障害等級の認定ではMRI・CT等の客観的所見が重視され、画像に靱帯損傷が写っていれば適正な等級が得られやすい。
逆に画像証拠が不十分だと低い等級や非該当となるリスクがある。
法律家も医学知識を
弁護士は画像所見を理解し、必要な検査を見極める目を養うべき。医師との連携や専門知識の蓄積によって、依頼者の後遺障害を最大限擁護できる。
諦めず追加立証
初回に所見がなくても症状が続く場合、再検査や他の検査法で証拠を探す。
診断遅れや症状変化にも医学的説明を付し、適切な補償を逃さないよう粘り強く対応する。
MRI・CTなどの画像診断を上手に活用することで、交通事故による靱帯損傷の「見えない後遺症」を可視化し、医学的に裏付けることができます。
それは被害者にとって適正な後遺障害等級の取得や妥当な賠償金の確保につながり、泣き寝入りを防ぐ大きな武器となります。
医学と法律の架け橋として画像証拠を位置づけ、専門家同士が連携することで、被害者救済の質は格段に向上するでしょう。
交通事故の被害に遭われた方は、症状を軽視せず適切な検査を受けること、そして弁護士の先生方は医学的視点を踏まえて戦略を立てることが肝要です。
双方の協力によって、事故による損害と後遺症に対する正当な補償を勝ち取りましょう。