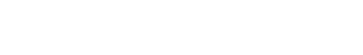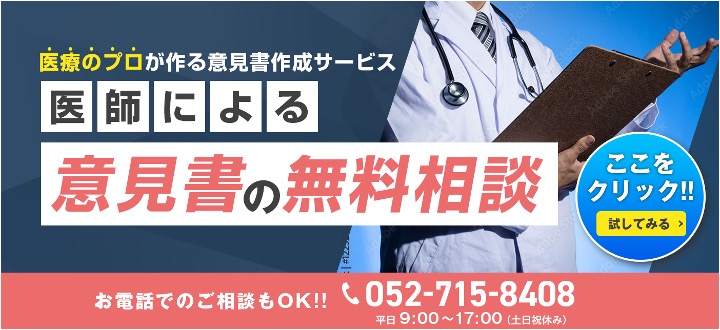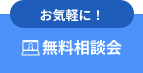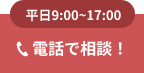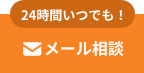頭部外傷と認知機能障害の概要、法的評価の重要性

交通事故や労働災害などで頭部に強い衝撃を受けると、頭部外傷によって脳が損傷し、その後遺症として認知機能障害が生じる場合があります。
外見上は怪我が治っていても、記憶力や注意力の低下、判断力や計画力の障害、感情のコントロールの困難といった症状が残ることがあり、これらは被害者の生活や就労に深刻な影響を及ぼします。
医療の現場では、こうした障害は高次脳機能障害とも呼ばれ、専門的なリハビリテーションや支援が行われます。
法的な場面でも、頭部外傷後の高次脳機能障害は極めて重要な検討事項です。
損害賠償の請求や労災補償、障害年金の申請などにおいて、脳の認知機能低下が事故による後遺障害として正式に認定されれば、被害者は適切な補償を受けることができます。
しかし、頭部外傷後の高次脳機能障害客観的な測定が難しく、周囲から理解されにくい障害でもあります。
そのため、法律実務では、医学的なエビデンスに基づいて高次脳機能障害を証明し、後遺障害として認定してもらうことが不可欠です。
本記事では、弁護士向けに、頭部外傷後の高次脳機能障害について、MRI検査の医学的な役割と後遺障害等級認定におけるポイントを解説します。
医学的知識に裏付けられた内容とし、医師が読んでも納得できる情報を盛り込みつつ、法的観点から詳細に論じます。
弁護士が依頼者の権利を守るために、医学的証拠としてのMRIをどのように活用すべきか、具体的な裁判例も交えて考察します。
目次
頭部挫傷後の認知機能障害の医学的背景(MRIの役割、診断方法)

脳へのダメージと認知機能障害の症状
頭部に衝撃が加わると、脳組織に物理的損傷が生じ、これが認知機能の低下を引き起こします。
脳損傷には局所的な損傷(例:脳挫傷、硬膜下血腫など)とびまん性の損傷(例:びまん性軸索損傷)があり、損傷のタイプによって症状も異なります。
例えば、前頭葉が損傷すれば計画力や注意力の障害、海馬の損傷では記憶障害、右脳の損傷では半側空間無視(片側の空間を認識できなくなる)が起こることがあります。
重度の頭部外傷では昏睡(意識不明)の時間が長引くほど、高次脳機能障害が生じる可能性が高くなることも知られています。
頭部外傷後の高次脳機能障害として典型的に見られる症状には
- 記憶障害(新しいことが覚えられない、物忘れが激しい)
- 注意障害(集中力が続かない、ミスが多くなる)
- 遂行機能障害(物事を計画的に進められない、段取りよく行動できない)
- 社会的行動障害(状況に合った適切な行動ができない、怒りっぽくなる)
などがあります。
これらの症状は日常生活において本人だけでなく周囲にも負担を与えるため、医療的なリハビリと適切な評価が重要です。
なお、重度の昏睡状態を伴わない軽度外傷性脳損傷(MTBI)、いわゆる脳震盪のようなケースでも、受傷後に高次脳機能障害が生じることが近年明らかになってきました。
外見上は軽症に見えるものの、時間の経過とともに集中力の低下や情緒不安定が続く場合があり、医学・法律双方において見落としに注意が必要です。
このようなMTBIのケースではMRI画像に異常が写りにくいため、診断や立証に一層の工夫が求められます。
MRI検査と神経心理学的検査
認知機能障害の原因となる脳の損傷を客観的に捉えるために、画像検査が大きな役割を果たします。
中でもMRI(磁気共鳴画像)検査は、脳の構造を詳細に描出できるため、頭部外傷後の評価に不可欠です。
急性期には頭部外傷や脳内出血、急性硬膜下血腫などの病変がMRIで確認でき、慢性期には脳萎縮(脳組織の減少)や脳室拡大(脳室=脳内の液体腔の拡大)といった変化が現れ、過去の損傷の痕跡として読み取ることができます。
MRIは脳内の微細な損傷や出血痕を検出する能力に優れ、CTでは見逃されるような小さな脳損傷を発見できる場合があります。
特に、びまん性軸索損傷では脳深部の軸索(神経線維)が広範囲に損傷しますが、その特徴所見である点状出血(小さな出血斑)はMRIのT2*強調画像や磁化率強調画像で捉えられることがありますが、画像異常がみられないケースもあります。
高次脳機能障害の評価のためには、神経心理学的検査が重要です。
ただし、MMSEなど認知症の評価に主に使われるような検査では異常がみられないことがあります。
頭部外傷後の高次脳機能障害の評価には、記憶力や注意力、問題解決能力などを専門のテストで評価するべきです。
具体的には、ウェクスラー記憶検査やウィスコンシンカード分類検査(WCST)などが用いられます。
MRIによって原因となる脳の器質的損傷を確認し、神経心理学的検査によって認知機能の障害を定量的に把握することで、医学的には「頭部外傷による高次脳機能障害」であることの診断が可能となります。
言い換えれば、MRI検査は認知機能障害の原因が外傷による脳損傷であることを裏付ける客観的証拠を提供するのです。
関連記事:交通事故のリハビリ日数や回数|通院中でも慰謝料はもらえる?
後遺障害認定におけるMRI所見の重要性(法的基準と医学的根拠)

頭部外傷による認知機能障害が後遺障害として法律的に認定されるためには、医学的所見と法的基準の双方を満たす必要があります。
自賠責保険では平成13年(2001年)より頭部外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定制度が整備されており、見落とされやすい障害であることから専門家による審査会で検討される運用がなされています。
その認定基準においては、頭部外傷による高次脳機能障害の後遺障害等級認定に際し、次のようなポイントが重視されています。
意識障害の程度と持続時間(急性期)
受傷直後の意識混濁や昏睡の有無、その深度と継続時間です。
例えば、JCS(ジャパンコーマスケール)で3桁の重症昏睡やGCS(グラスゴーコーマスケール)で8点以下の重度意識障害が6時間以上続いた場合、深刻な脳損傷を示す一指標となります。
日常生活上の問題の存在
家族や介護者など周囲の人が、被害者の日常生活で記憶障害や人格変化など明らかな問題に気づいていること。
客観的な第三者の観察により、単なる「気のせい」ではなく実生活に支障が出ていることを裏付けます。
画像上の脳損傷所見
CTやMRIなど画像検査で脳に外傷による器質的損傷が確認できることです。
具体的には、急性期であれば点状出血や外傷性くも膜下出血などの異常所見、慢性期であれば局所的な脳萎縮、特に脳室拡大の進行といった変化が該当します。
これらは頭部外傷による脳ダメージを客観的に示すもので、MRI所見はこの要件を満たす上で極めて重要な証拠となります。
発症時期と他原因の鑑別
頭部外傷後すぐに症状が出ず、一旦通常の生活に戻ってから数ヶ月以上経って認知症状が現れたケースでは、外傷との因果関係が慎重に判断されます。
特に、慢性硬膜下血腫の発生もなく脳室拡大も見られない場合には、「加齢や別の脳疾患による認知症ではないか」と疑われ、外傷起因の後遺障害としては認められにくくなります。
なお、受傷直後には目立たなかった症状が、復職・復学など環境の変化によって後から顕在化する場合もあります。
発症のタイミングのみで外傷との因果関係を早計に否定すべきではないとの指摘もされています。
上記のように、画像所見(MRI等で確認される脳損傷の証拠)は後遺障害等級の認定における重要な要素の一つです。
裏を返せば、画像所見に乏しい事例では、たとえ本人が記憶障害や性格変化を訴えていても、後遺障害として認定されないリスクが高まります。
事実、交通事故の裁判例でも「意識障害とCT・MRIの画像所見の2つを重視して、高次脳機能障害の有無を判断する傾向」が指摘されており、客観的証拠のない主観的訴えのみでは立証が困難なのが現状です。
なお、SPECT(脳血流シンチ)やPET(陽電子断層撮影)などの機能画像検査は脳の代謝・血流異常を可視化できるものの、自賠責実務では「補助的な検査所見」に留まるとされており、MRIによる形態的異常所見ほど重視されない傾向があります。
もっとも、医学の進歩により画像検査技術は年々向上しており、かつては発見できなかった微小な脳損傷も最新のMRIでは可視化できる可能性があります。
また、必ずしも画像所見が得られなくとも、高度の意識障害や明確な神経心理学的な異常所見が揃えば、総合的判断で後遺障害が認定されるケースも存在します。
実際、近年の判例には「CT・MRIで所見がないことのみで高次脳機能障害を否定すべきではない」として、様々な証拠を総合考慮した結果、頭部外傷による認知機能障害を認定した例もあります。
とはいえ、このような例はまだ少数であり、一般的にはMRIで確認できる脳の器質的損傷が後遺障害認定の鍵となることに変わりはありません。
弁護士がMRIを活用するためのポイント(証拠収集、書類の準備)

頭部外傷による認知機能障害の案件を扱う弁護士にとって、MRI所見を含む医学的証拠を的確に収集し、後遺障害認定や裁判で効果的に活用することが重要です。
以下に、実務上押さえておくべきポイントを解説します。
早期のMRI検査と経過に応じた追跡検査
外傷直後に異常が見られなくても、時間経過とともに脳萎縮などの所見が現れる場合があります。
受傷直後および受傷後3ヶ月前後にMRI検査を受けて画像所見を確保することが推奨されています。
CTのみでは不十分であり、可能であれば3テスラ級の高解像度MRIを用いるのが望ましいとされています。
意識障害の記録と証拠化
医療記録に当初の意識障害の程度・継続時間が明確に記載されているか確認します。
救急搬送時や入院中の記録に昏睡の深さや覚醒までの経過が漏れなく書かれていれば理想的ですが、現実には必ずしも詳記されていないこともあります。
不足があれば、担当医に症状経過について所見を書いてもらう、看護記録や救急隊の記録を取り寄せる、家族から事故直後の状況を聞き取り陳述書にまとめるなど、意識障害の存在を裏付ける資料を可能な限り集めます。
なお、自賠責の後遺障害審査においては、主治医に対し「頭部外傷後の意識障害についての所見」という専用の報告書提出が求められます。
この報告書もカルテの記載をもとに作成されるため、医療記録に情報が残っていないと正確な評価が難しくなります。
専門医の関与
脳神経外科医やリハビリ医など、頭部外傷の後遺症に詳しい医師に診断・評価を依頼することも重要です。
主治医が高次脳機能障害の知見に乏しい場合、MRI画像上の微小出血痕を見落としたり、認知機能の低下を十分評価せずに「後遺症なし」と判断してしまったりするケースもあります。
必要に応じて、高次脳機能障害の専門外来や支援センターを紹介し、専門的な検査・診断を受けてもらうことで、的確な所見を得られます。
神経心理学的検査結果の収集
医師による診断書だけでなく、臨床心理士等が実施した神経心理学的検査の結果報告書も重要な証拠となります。
知能検査(WAIS-Ⅳなど)や記憶検査、遂行機能検査(例:WCST)などで明らかな低下が示されれば、日常生活での障害の具体的な証明になります。
これらの検査結果は、後遺障害診断書に添付したり、裁判では鑑定書・意見書として提出したりすることで、MRI所見と相まって説得力のある主張につながります。
後遺障害診断書や意見書の充実
後遺障害等級の認定申請時には、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
その際、MRIの異常所見や神経心理検査の結果を具体的に記載してもらうよう依頼します。
画像所見は「MRIで〇〇部に慢性期の低信号域(微小出血痕)を認める」等、専門的記載になりますが、これが等級認定者や裁判官にとって重要な判断材料となります。
また、裁判になった場合には、主治医や専門医に意見書を作成してもらい、MRI所見と認知機能障害との因果関係について医学的に説明してもらうことも有効です。
これらのポイントを踏まえ、弁護士は医学的証拠を漏れなく収集・整理することが求められます。
特にMRI画像については、現像フィルムやデジタルデータを入手し、必要に応じて専門医に読影・評価を依頼するなど、証拠価値を高める工夫が有用です。
医学的裏付けの充実した主張を行うことで、後遺障害等級の認定や裁判での立証の成功率が格段に高まるでしょう。
もしMRIが存在しないような場合は医師の意見書が重要な役割を担うことになります。
その場合は診断した医師や脳神経内科、脳神経外科、精神科などのうち、特に認知症を専門とする医師へ相談することが重要になってきます。
関連記事:労災の休業補償の計算方法とは|会社負担はどれくらい?
関連する裁判例

MRI所見と認知機能障害との関係については、裁判例でも度々争点となっています。ここでは、関連する主な判例をいくつか紹介します。
大阪地方裁判所平成29年2月8日判決(交民集50巻1号139頁)
47歳女性の被害者につき、高次脳機能障害(記憶障害・遂行機能障害)による後遺障害等級3級3号が認定された事案です。
被害者は介護サービス会社でケアマネージャーとして勤務していましたが、事故による障害で終身労務不能となり、ADLの一部に介助が必要な状態でした。
裁判所は、平均余命39年にわたり職業介護人による介護が必要と判断し、日額6,500円(総額約4,037万円)もの将来介護費の賠償を認めました。
重度の認知機能障害が残存した場合、被害者の生活には長期の介護負担が生じるため、その費用が大きな損害項目となることを示しています。
最高裁昭和50年10月24日判決(ルンバール事件)
後遺障害の因果関係立証に関し、「科学的に一点の疑義も許さない証明まで必要とするものではない」と判示しました。
この最高裁判決は、医学的証明に多少の不確実性が残っても、全証拠を総合して合理的な蓋然性が認められれば因果関係を肯定できると示したものです。
頭部外傷による認知障害の事案でも、完全な画像証拠がなくとも他の証拠を積み上げることで認定に至る可能性があるという原則的な支えとなります。
大阪高等裁判所平成28年3月24日判決
被害者が事故後に記憶障害等を訴えたものの、MRIで明確な器質的病変が確認できなかった事案です。
大阪高裁は、自賠責の診断基準を参考に「単にCT・MRI所見がないという理由だけで高次脳機能障害を否定するのは相当でない」と指摘し、意識障害や神経心理学的所見など様々な要素を慎重に考慮すべきとしました。
その結果、本件では頭部外傷による高次脳機能障害(認知障害)が認定され、後遺障害等級7級相当と判断されています。
この判決は、MRI所見がなくても総合評価で認定に至った例として注目されます。
大阪地方裁判所平成30年9月10日判決(自保ジャーナル2033号掲載)
原告(被害者)が自賠責で高次脳機能障害5級2号と認定された事案について、裁判所がその等級を検討したものです。
裁判所は、事故による脳損傷自体は認めつつも、遂行機能検査(WCSTなど)の未実施により認知機能障害の程度を十分に評価できていない点に言及しました。
もし検査を実施して異常所見が確認されていれば、自賠責認定の5級2号が維持され得た可能性があると示唆されています。
このケースは、MRI所見のみならず神経心理学的エビデンスを含めた総合的証拠の重要性を示すものといえます。
ちなみに、2013年から2017年にかけて提起された交通事故訴訟67件を分析した研究では、高次脳機能障害の主張が裁判で認められたのは16件(約24%)に留まり、25件の軽度外傷性脳損傷(mTBI)の事案では一件も認容されなかったと報告されています。
これは、画像所見や意識障害の記録といった医学的裏付けが欠如したケースでは、裁判所も後遺障害を認定しなかった傾向を示すものと言えます。
これらの裁判例から明らかなように、裁判所は医学的証拠の充実度を重視しています。
特に高次脳機能障害の有無・程度については、画像所見、臨床経過、検査結果などを総合して判断する姿勢が取られています。
裏を返せば、医学的証拠が不足している場合には、自賠責で認定された等級が裁判で引き下げられたり(上記大阪地裁H30.9.10判決など)、そもそも後遺障害と認められなかったりするリスクがあります。
逆に、十分な証拠を揃えて主張・立証がなされれば、自賠責で非該当だったものが裁判で後遺障害と認定されるケースもあり得ます。
医療と弁護士の連携による後遺障害認定の質向上

頭部外傷後の認知機能障害という複雑な問題に取り組むには、医療と法曹の綿密な連携が欠かせません。
医師と弁護士が互いの専門性を理解し協力することで、後遺障害認定の精度と公平性が高まります。
医療側から見れば、診療の際に後遺障害認定を意識することは容易ではありません。
例えば、急性期のカルテに意識レベルの経過が詳細に記録されていなかったり、MRI画像の所見が専門外の医師には見逃されてしまったりするケースがあります。
しかし、弁護士から事前に後遺障害認定に必要な情報を共有してもらえれば、医師は必要な検査や記録により注意を払うことができます。
一方、弁護士にとっても、医学的知見を持つことで、どのような証拠が有用かを見極めやすくなり、医師に適切な協力を依頼できるようになります。
具体的には、主治医に後遺障害診断書を依頼する際に必要な検査結果や画像を提供してもらえるよう相談したり、専門医から医学的な意見書を取り寄せて法的主張に活かしたりすることが挙げられます。
場合によっては、法廷で医師に証人として証言してもらい、MRI所見や検査結果について専門的見地から説明してもらうこともあります。
これらは弁護士単独では難しい領域ですが、医療側の協力があって初めて実現できるものです。
医療と法律の連携により、被害者にとって最善の結果を引き出すことが可能になります。
前述のように、裁判では提出された証拠に基づき判断が下されますが、充実した資料が揃えば、本来認められるべき後遺障害が見逃されるリスクは大きく減少します。
逆に、連携不足で証拠が不十分な場合、適正な等級認定が得られず被害者が泣き寝入りしてしまう恐れもあります。
医師と弁護士が二人三脚で事案に向き合うことで、医学的妥当性と法的妥当性を兼ね備えた結論を導き出すことができるのです。
関連記事:後遺障害が認定されない5つの理由|認定されるための対処法とは
【まとめ】適切な医療的根拠を備えた後遺障害認定の重要性
頭部挫傷後の認知機能障害とMRI検査の重要性について、医学と法の両面から解説してきました。
MRI所見は、脳の見えないダメージを「見える化」する手段として、診断と後遺障害認定の橋渡しをする極めて価値の高い証拠です。
認知機能障害という目に見えにくい障害こそ、客観的な画像所見や検査結果に基づく丁寧な立証が求められます。
弁護士にとっては、医学的知識を踏まえて証拠収集と主張展開を行うことが不可欠であり、それによって依頼者の正当な権利を守ることができます。
一方、医師にとっても、自らの所見が法的に適切に評価されることで、患者の社会復帰や補償に繋がる支援となります。
適切な医療的根拠を備えた後遺障害認定は、被害者の生活の質を守るのみならず、医学的妥当性と法律的公正さの双方を実現するものです。
頭部外傷後の高次脳機能障害は、誰にとっても対岸の火事ではなく、突然巻き込まれうる身近な問題です。
そのようなとき、医学と法律の協調により、公平で十分な後遺障害認定がなされることが社会にとって重要です。
本記事の内容が、弁護士の先生方が医学的知見を活用し、適切な補償と支援を勝ち取る一助になれば幸いです。
本稿で述べたように、医学的根拠に基づく正確な後遺障害認定は被害者の人生を左右する重要な問題です。
弁護士はMRIをはじめとする客観的証拠を最大限に活用し、医療専門家と協働して依頼者の権利擁護に努める必要があります。
高次脳機能障害という見えにくい障害に光を当て、適正な補償につなげるために、医学と法の知見を融合させた対応が今後ますます求められるでしょう。
参考文献(判例等)
最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻10号1554頁)
大阪高裁平成28年3月24日判決(自保ジャーナル1989号)
大阪地裁平成29年2月8日判決(交民集50巻1号139頁)
大阪地裁平成30年9月10日判決(自保ジャーナル2033号)
交通事故オンライン『高次脳機能障害の診断基準』
阿部ら「交通事故による頭部外傷後高次脳機能障害の認否が争われた裁判例の検討」神経外傷 Vol.41(2018) No.2