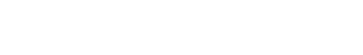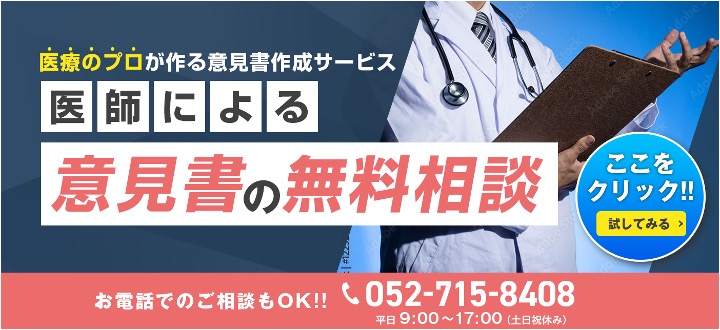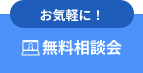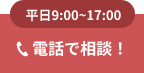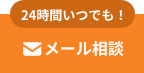後遺障害14級の認定率を左右する要素や認定が難しい理由について詳しく解説
後遺障害14級の認定率は、実際どのくらいなのでしょうか?
交通事故や労災による後遺障害の中で、14級に該当する場合は比較的軽度な障害として扱われますが、認定を受けることは決して簡単ではありません。
実際、認定率はケースバイケースであり、思った以上に厳しい審査が行われることも少なくないため、多くの人が「本当に認定されるのか」と不安を抱いているのが現状ではないでしょうか。
本記事では、後遺障害14級の認定率に焦点を当て、どのような基準で判断されるのか、認定を受けるために注意すべきポイントについて詳しく解説します。
後遺障害の申請を考えている方、またはすでに申請中の方にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
後遺障害の認定率について

そもそも後遺障害とは
交通事故における後遺障害等級は、自賠法施行令によって規定されています。
自賠法施行令では後遺障害等級を1級から14級という等級が定められており、等級の数字が小さいほど後遺障害の程度が重いことを示しています。
その中でも、本記事で説明する14級については以下のとおり規定されています。
号 | 症状 |
1号 | |
2号 | |
3号 | |
4号 | |
5号 | |
6号 | |
7号 | |
8号 | |
9号 | |
10号 | |
11号 | |
12号 | |
13号 | |
14号 |
引用元:国土交通省「後遺障害等級表」
後遺障害14級の認定率
結論からいうと、後遺障害14級の認定率は、交通事故事案全ての件数から見ると約2.5%、後遺障害が認められたケースのみを分母とするならば約58%ほどとなっています。
損害保険料率算出機構が発表している「自動車保険の概況」によると、A:自賠責保険への請求件数/B:後遺障害等級の認定件数/C:後遺障害等級14級の認定件数は以下のとおりです。
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
A | 自賠責保険への請求件数 | 1,226,754 | 1,041,737 | 972,281 |
B | 後遺障害等級の認定件数 | 52,541 | 49,267 | 42,980 |
C | 14級の認定件数 | 30,675 | 28,593 | 24,417 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |
請求件数/等級認定件数(B/A) | 4.28% | 4.73% | 4.42% |
請求件数/14級認定件数(C/A) | 2.50% | 2.74% | 2.51% |
14級認定件数/等級認定件数(C/B) | 58.38% | 58.04% | 56.81% |
引用元:2022年度_自動車保険の概況|損害保険料率算出機構
請求件数の中にはありとあらゆる人身傷害事案が含まれています。
そもそもすべての人身事故事案の約2.5%しか後遺障害等級の認定は受けられていないことから、後遺障害等級の認定は比較的難易度が高いことが見てとれます。
さらにその内訳について見てみると、後遺障害等級の認定事案の中で14級が認定された事案件数は最も多く、後遺障害等級の認定件数の約60%が14級認定事案です。
すなわち、後遺障害に認定されるケースのほとんどが14級になっていると言って良いでしょう。
また、後遺障害14級認定事案のほとんどが、次に説明する9号「局部に神経症状を残すもの」に該当します。
後遺障害14級9号について
後遺障害14級9号は事故が原因で発生した症状について、医療画像・症状の一貫性・主訴の内容や程度等を踏まえて神経症状が残ると医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されることとなります。
要件 | 神経症状の内容が将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもののうち、他覚的所見(画像など検査結果など客観的な証拠を伴う所見)がみとめられないもの ※ 他覚的所見が認められれば12級13号が認定される |
認定内容から見えるもの | 痛みは、常時疼痛を残すものである必要がある いずれの神経症状も、画像上明確ではないが、当該部位に症状が発生することの医学的根拠が存在し、かつその症状が一貫して訴えられている必要がある |
認定要素 | 事故規模、事故態様、通院期間、通院頻度、治療の経過・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像上の所見の有無などを考慮して判断されている。 |
このように、神経症状の根拠を画像によって明確にし、医師に神経症状の内容を各種書面に具体的かつ的確な症状内容を記載してもらう必要があります。
そこで、以下の点が重要となります。
|
関連記事:後遺障害14級の認定を左右する通院日数|認定率を上げるには?
後遺障害14級の認定率を左右する要素

通院日数・頻度・期間
後遺障害14級の認定を受けるためには事故や事件などで怪我を負ってから、ある程度の長期間に渡って通院し、治療を受けることが必須要件となります。
14級9号の場合は治療期間は最低でも6か月以上が必須となっており、その間、合計の通院日数として60日以上が必要です。
整骨院などにも通う場合は病院と合わせて80日程度が目安とされます。
注意しなければならないのは、上記の条件を満たすことで初めて認定されるかどうかのステージに上がれるに過ぎず、例えば通院日数が多いからといって認定率が高いわけではありません。
通院日数・頻度・期間の条件を満たしていない=認定率0%という捉え方が正しいでしょう。
まとめると下記のようになります。
【後遺障害14級9号の認定要件】
- 通院期間:最低6か月(必須)
- 通院日数:60日以上(望ましい)
- 通院頻度:週3~4回(望ましい)
症状の一貫性
治療中の診断や症状の記録が一貫しているかどうかは、後遺障害14級に該当するか否かの判断において非常に重要です。
特に画像所見では判断できないむちうちや、画像に残らない程度の軽微な神経症状は被害者自身の主訴と医師が記録しているカルテのみが手がかりとなります。
後から主訴が変わってしまうと、後遺障害認定を受けるために嘘をついていると判断される可能性があり、そうなると認定率は著しく下がってしまうでしょう。
仮に嘘ではなかったとしても、初めから訴えていなければ一貫性という点で不利になってしまうため、どんなに小さな症状や、あるいは違和感程度でも気になることは全て主治医に伝えることが大切です。
医学的な証拠
画像をはじめとした各種検査結果は後遺障害14級の認定率を上げるポイントとなり得ます。
また、後遺障害14級の判定には事故の規模や受傷状況、神経学的テストの結果などが総合的に考慮されます。
万が一医学的証拠が乏しい場合は、こうした客観的事実と照らし合わせた際に矛盾しない主張を事故直後から一貫して展開することで、認定率を上げることにつながるでしょう。
関連記事:むちうちの症状や外傷に伴う頭痛を呈する疾患について
後遺障害14級の認定率が低い理由

後遺障害14級の認定率が、交通事故全体の3%にも満たない数字であることは先ほどお伝えしたとおりです。
しかし、実際に交通事故に遭ってから後遺症に悩まされている方は決して少なくありません。
なぜ認定率が低いのか、その要因を考えてみましょう。
被害者本人の知識不足
まず、被害者本人に医学的あるいは法的知識がなく、当然のことながら後遺障害等級に関する知識を持ち合わせていないケースがほとんどでしょう。
弁護士でも症状の内容や程度が後遺障害等級に該当するものなのかについての判断をすぐに下せるわけではないため、一般人が、しかも事故の被害者本人が妥当な判断をできないのは致し方ないことです。
とはいえ、被害者側に知識がなく本来受けられるはずであった後遺障害14級の認定を受けられていないケースが多々あるため、これが認定率の低さの一因となってしまっている現状があります。
医師の後遺障害に関する知識不足
はじめに申し上げておくと、医師の職責は診断等により患者の症状を緩和ないし緩解させることにあり、後遺障害等級獲得をフォローすることではありません。
そのため後遺障害診断書の記載やカルテの記載、ひいては主治医による医師意見書の作成にあたって、後遺障害が認定されるか否かまでは考慮されないことが多いでしょう。
後遺障害等級の認定を得るためには、医師が適切な方法により各種医療画像を撮影し、本人の訴える症状を適切に聴取した上で、聴取結果をカルテにそのまま残しておくことが肝要です。
治療段階において後遺障害等級に精通した医師の判断が介在していないケースが多いことも認定率が低い要因のひとつであるといえます。
医療に精通した弁護士の不足
弁護士は法律のプロであり、医療に関しては専門家というわけではありません。
そのため弁護士業務を医学的知見によりバックアップする必要がありますが、残念ながらこれができていないことが後遺障害の認定率が低い原因となってしまっています。
後遺障害14級の中で最も判断が難しいのが9号です。
特に画像上の異常が見られないむちうち症状において、症状の内容や程度を証明するための情報を提供するのは被害者本人のみとなります。
そして、その被害者本人の訴えに医学的妥当性を持たせることができるのが主治医のみとなります。
現状、後遺障害等級をめぐる協議において医師サイドと法律家サイドのパイプが確立されていないことが大きな課題であると言えるでしょう。
関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、下記の法律事務所へご相談ください。
後遺障害14級の認定率を少しでも上げるには?

後遺障害14級は客観的事実や医学的・法的観点などから厳格に判断されます。
そのため、被害者が何とか認定率を上げようとしたからといって簡単に上げられるものではありません。
しかし、いくつかのポイントを押さえておくことで有利になる要素はあるので、ここで確認しておきましょう。
早期の受診と適切な治療
事故後、なるべく早く(3日以内)に整形外科を受診し、症状が固定するまで医師の指示に従って通院することが大切です。
診察や検査で一貫した症状の記録を残すことで認定されるかどうか協議される際の信頼性が高まるでしょう。
さまざまな検査を受ける
特に多い神経症状が残るケースでは外見的な判別がつきませんが、MRIやCTなどの画像所見で異常が見つかれば強力な証拠になります。
また、簡単な神経学的検査などの結果もカルテに記録されれば医学的証拠として残るため、症状を詳細に伝え、その症状の有無や程度を判断する検査やテストを受けるようにしましょう。
症状固定後の通院
症状が固定された後に通院を止めてしまう人もいますが、後遺障害14級の認定を受けるという観点で見ると得策ではありません。
真摯に治療を続けていることを示すために継続的に通院することが推奨され、これにより痛みやしびれの訴えに信憑性が増し、認定率を高める要素となるでしょう。
医療に強い弁護士への相談
もし一度、後遺障害14級が非該当となっても諦める必要はありません。
医療分野に明るい弁護士へ再度相談することで、別角度からのアプローチによって認定を勝ち取れるケースも少なくありません。
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、下記の法律事務所への相談をご検討ください。
【Q&A】後遺障害14級の認定率に関するよくある質問
ここでは、後遺障害14級の認定率に関連した疑問にお答えしていきます。
後遺障害14級に認定された場合の慰謝料は75万円?
賠償額の基準としては、大きく【自賠責における保険金支払基準】と【訴訟となった場合に裁判所が認定する損害賠償基準】があります。
- 自賠責の保険金支払基準・・・75万円
- 訴訟における損害賠償基準・・・110万円
事故による保証は慰謝料と逸失利益に分けられ、慰謝料は事故に遭ったことに対する精神的苦痛への補償、逸失利益は事故に遭ったことで労働などで得るはずだった収入に対する補填として支払われます。
慰謝料は一定の範囲内に収まる場合がほとんどですが、逸失利益は人によって所得が異なるため大きく上下します。
後遺障害14級にデメリットはある?
結論からいうと、後遺障害14級の認定を受けること自体には特にデメリットはないと言えるでしょう。
ただし、後遺障害認定を受けるためには下記の2つの方法があり、それぞれ手続き上のデメリットがないわけではないので、そちらについて紹介します。
- 事前認定
- 被害者請求
事前認定のデメリット
事前認定とは、簡単にいうと加害者側の任意保険会社が手続きから何からすべてやってくれるため、被害者自身の手間がほとんどかかりません。
これだけ聞くと悪くないような気がしますが、被害者が手続きに関与しないことで下記のようなデメリットが考えられます。
- 手続きのプロセスが不透明
- 被害者の求める等級が認定されない可能性がある
- 支払いまでに時間がかかる
被害者請求のデメリット
被害者請求とは、被害者が必要な書類を手配して手続きを行う方法です。
事前認定と比較して、メリットとデメリットがそっくりそのまま入れ替わるイメージで差し支えありません。
本記事のテーマである後遺障害14級の認定率を上げるという点でいえば、手続きの手間はかかかるものの被害者請求の方がおすすめの方法と言えるでしょう。
関連記事:交通事故裁判に提出する医師の鑑定書はどこに依頼すれば良い?作成費用の目安も解説
まとめ
後遺障害14級の認定率は2.5%程度であり、これは低い数字であると言わざるを得ません。
認定率が低い理由は、後遺障害14級の中でも事案の多い9号の定義が曖昧であり、医学的証拠の提示が難しいことが挙げられるでしょう。
しかし、認定率を左右する他の要素として症状や治療の一貫性、通院日数・期間・頻度といったものもあります。
本記事で紹介した認定率を少しでも上げるためにできることを実践して、絶対に悔いを残さないようにしましょう。
弊社ではそういった方々のサポートをさせていただいております。
この記事の監修者
不破 英登

経歴
| 2009 | 愛知医科大学医学部医学科 津島市民病院 |
| 2011 | 名古屋第二赤十字病院 放射線科 |
| 2016 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教 |
| 2018 | 豊田若竹病院 放射線科 YKR medical consult設立 |
| 2018 | 家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師 |
| 2021 | YKR medical consult 代表就任 |
| 【資格】 産業医・放射線科診断専門医 |