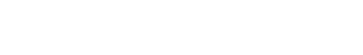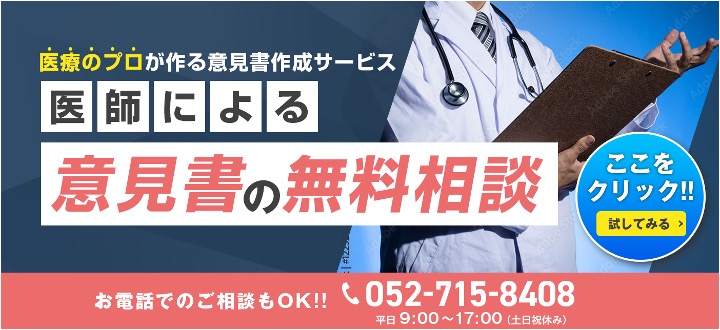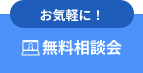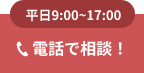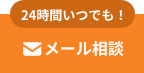後遺障害14級の認定を左右する通院日数|認定率を上げるには?
交通事故等で後遺障害14 級に認定される要因のひとつとして通院日数があります。
本記事では、後遺障害14級の認定に通院日数がどのように関連するのか、補償額や適切な治療の進め方について詳しく解説します。
また、通院日数が補償額にどのような影響を及ぼすかについても言及するので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:後遺障害の診断書は書いてもらえる?|メリット・デメリットについて
目次
後遺障害14級の認定に必要な通院日数

後遺障害14級が認定されるかどうかの判断において通院日数は重要であり、一般的には通院日数が60日以上であることが認定の目安とされています。
ただし、通院日数が条件を満たしていれば認定はされるわけではなく、症状の一貫性や治療内容がより重要視されることも覚えておきましょう。
また、整骨院や接骨院のみの通院ではなく、医療機関(病院など)での診察が不可欠です。
医療機関への通院が最低15〜20日程度必要であり、整骨院と併用する場合には合計80日以上の通院が推奨されることがあります。
関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
後遺障害14級の認定には通院「期間」も重要

後遺障害14級が認定されるための通院期間は、一般的に6ヶ月以上が目安とされています。
症状が安定する「症状固定」の状態まで治療を続けることが重要です。
また、通院頻度も大事なポイントで、週3日程度の通院が理想的とされています。
上記のような期間とペースで通院することにより、後遺障害14級の認定に関わる、事故後の治療や症状の一貫性を証明できるでしょう。
関連記事:交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
後遺障害14級の認定に関わるその他の要素

通院日数や通院期間以外の後遺障害14級の要件に「局部に神経症状を残すもの」とあります。
これは交通事故などで体の一部分に神経が損傷し、その結果として痛みやしびれなどの症状が残る状態を指します。
具体的には首や腰、手足に痛みやしびれが生じ、例えば首が動かしにくくなったり、関節に違和感がある場合などが該当。また、この状態が医学的に説明できる場合に後遺障害14級として認定されることがあります。
画像上で異常が確認されなくても、事故の状況や症状の一貫性が認められれば認定されるケースはあるようです。
後遺障害14 級の認定率
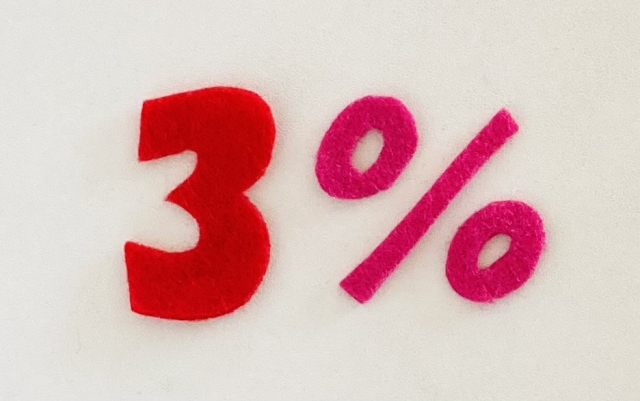
そもそも後遺障害14級は簡単に認定されるものなのでしょうか?結論からいうと交通事故全体の約3%、後遺障害が残ったケースでは約60%で認定されています。
損害保険料率算出機構の公表している「2022年自動車保険の概況」によると、2021年に自賠責保険で保険金が支払われた全体の件数は「837,390件」でした。
そのうち何らかの後遺障害が認められたケースは「42,980件」となっており、後遺障害14級が認定されたのは「24,417件」です。
よって後遺障害14級が認定されたのは交通事故全体の件数をもとにすれば3%を下回りますが、後遺障害が認められたケースでは58%が認定されたということになります。
後遺障害14 級の認定率を上げるためにできること

後遺障害14級は簡単に認定されるものではありません。
後遺障害が残ったことが医学的に証明されることが大前提であり、さらにその後にとった行動が重要となります。
先述した内容と重複する部分もありますが、改めて少しでも認定率を上げるためにできることを確認しておきましょう。
定期的な通院
いわゆる「症状固定」の状態になるまで通院を続けることが必要で、週に2~3回の通院は必須となるでしょう。
通院日数と通院期間の条件を満たしていることは後遺障害14級の認定を受ける上ではベースに過ぎず、条件を満たしていなければ認定されるかどうかの協議に上がることすらありません。
また、医療機関での診察も重要で、整骨院だけではなく病院にも定期的に通うことが推奨されています。
後遺障害診断書の適切な作成
医師によって作成される「後遺障害診断書」が認定の基準となるため、診断書の内容はきわめて重要です。
内容が不十分だったり、症状が詳細に記載されていないといった場合はまず認定されないと言って良いでしょう。
医師にしっかりと症状を伝え、裁判や協議の場で突っ込まれる余地がないくらい正確な診断書を作成してもらうことが理想です。
症状の一貫性と連続性
事故後の症状が一貫しており、治療の経過がはっきりしていることが後遺障害14級の認定において大きなポイントとなります。
後遺障害等級が認められるということは、受傷後から現在、そして未来までその後遺症が被害者の人生に影響を及ぼすと認められたのと同義です。
そのため、途中で訴える症状が変わったり主訴が二転三転する場合は認定が難しくなるでしょう。
医療的な証拠の確保
レントゲンやMRIなどの画像検査も重要な証拠となります。
特に神経症状は外傷のように見た目でわからないため客観的に確認できる症状が求められ、各種神経テストや検査結果を確保することが必要です。
関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
後遺障害14級の認定を受けるための手続きについて

後遺障害の申請手続きには、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。それぞれの手続きの流れと特徴を簡単に説明します。
また、申請に必要な書類の一例は下記のとおりです。
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況説明書
- 入院・通院交通費明細書
事前認定
この方法では加害者側の任意保険会社が手続きを代行します。後遺障害診断書を医師に依頼して作成してもらい、それを保険会社に提出します。
保険会社が残りの書類を用意して審査機関に申請するため手間が少ないのが特徴です。
しかし保険会社が主導して進めるため、被害者側からすると申請内容に対する透明性が低いと感じることがあるかもしれません。
被害者請求
こちらは被害者が自ら必要書類を集めて申請する方法です。交通事故証明書や診断書などを収集し、加害者の自賠責保険会社に提出します。
事前認定に比べて手間はかかりますが、申請内容をすべて自分で確認できるため透明性が担保されるのがメリットです。
また、認定が下りた場合は補償金が直接振り込まれます。
後遺障害14級の補償について
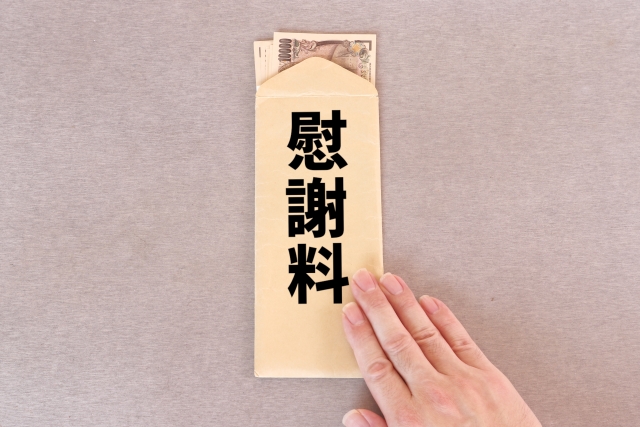
後遺障害14級の補償は、基本的に慰謝料と逸失利益に分けて計算されます。
先にこの2つを合計した額をお伝えすると、後遺障害14級では一般的に約178万~224万円程度の補償を受けられることが多いです。
慰謝料
慰謝料は後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する補償として支払われます。
後遺障害14級の場合の慰謝料は裁判基準で110万円が相場です。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残ることで労働能力が減少した場合に支払われる補償金です。
後遺障害14級での労働能力の喪失率は5%とされており、通常は労働能力の喪失期間を5年として計算。具体的には、基礎収入に労働能力喪失率(5%)をかけ、その結果に対応するライプニッツ係数(※)を使って算出します。
例えば年収が450万円の場合の逸失利益は約103万円となります。
※:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
交通事故の後遺障害診断書はYKRの医師にお任せください
後遺障害診断書に精通している医師が見つからない場合には、YKRまでご相談ください。
YKRには交通事故の鑑定に詳しい後遺障害認定においても定評のある医師が在籍しています。
転院により、これまで他院に通っていた方であっても後遺障害診断書を書ける可能性があります。
今の通院先の医師に後遺障害診断書の作成を拒否された、今の医師があまり後遺障害診断書に詳しくないなどの事情があれば、お気軽にお問い合わせください。
関連記事:交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
関連記事:交通事故裁判に提出する医師の鑑定書はどこに依頼すれば良い?作成費用の目安も解説
関連記事:各種裁判における医師の鑑定書・意見書のメリットや役割
まとめ
交通事故で後遺障害14級の認定を受けるには、一定以上の通院日数と通院期間が必要です。
交通事故に詳しい医師に後遺障害診断書を書いてもらうことが重要です。
YKRでは後遺障害認定の支援にも取り組んでおりますので、良い医師をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
福谷陽子

- 京都大学法学部に現役合格
- 在学中(大学4年時)に司法試験に合格
- 法律事務所の設立経験あり 元弁護士
不破 英登

経歴
| 2009 | 愛知医科大学医学部医学科 津島市民病院 |
| 2011 | 名古屋第二赤十字病院 放射線科 |
| 2016 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教 |
| 2018 | 豊田若竹病院 放射線科 YKR medical consult設立 |
| 2018 | 家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師 |
| 2021 | YKR medical consult 代表就任 |
| 【資格】 産業医・放射線科診断専門医 |