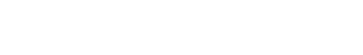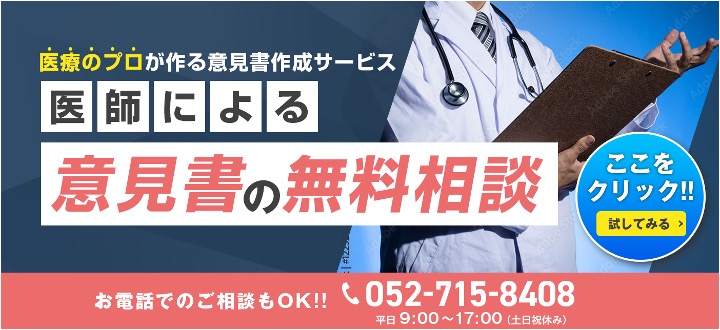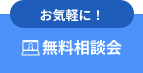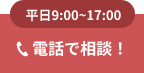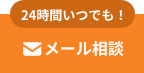肩の後遺障害等級の内容と認定を受けるためのポイントを解説

交通事故などで肩を負傷した場合、治療を終えた後も何らかの後遺症が残り日常生活に支障をきたすことがあります。
このようなケースでは後遺障害に認定され、保険金を受け取れる可能性がありますが、後遺障害にもさまざまな等級が存在します。
また、申請をしたからといって必ずしも認定されるとは限りません。
そこで本記事では、肩の後遺障害等級の内容や認定を受ける際に押さえておきたいポイントを詳しくご紹介します。
目次
肩の後遺障害が発生する主な要因

肩の後遺障害はさまざまな原因で発生し、生活や仕事に支障をきたすことがあります。後遺障害をもたらす主な原因を解説します。
交通事故
交通事故によって肩に大きな衝撃や圧力が加わると、骨折や関節の損傷を引き起こすことがあります。
具体的には鎖骨骨折や上腕骨頚部骨折、肩関節脱臼、肩腱板断裂などが挙げられ、これらが引き金となり治療後も肩の可動域が制限されたり、痛みが慢性化し後遺障害が残る場合があります。
スポーツ中の怪我
激しいスポーツによって肩に外傷を負ったり、オーバーユース(肩の酷使)も後遺障害を引き起こすことがあります。
たとえば、ラグビーや空手、相撲などは相手と接触した際に大きな力が加わるため肩関節を負傷するリスクが高いほか、野球やテニスなど肩を酷使するスポーツでは肩の腱を損傷することもあります。
治療を終えたとしても、慢性的な肩の痛みや違和感に悩まされるケースが少なくありません。
手術後の影響
軟骨組織の損傷によって関節機能の低下が著しい場合には、外科手術による治療が行われることもありますが、治療を終えたからといってもとの状態に戻るとは限りません。
たとえば、手術の部位によっては難易度が高く、神経の一部を傷つけ麻痺が残る可能性があります。
また、術後のリハビリ不足によって十分な回復が見込めなくなることもあるでしょう。
長時間の同じ動作の繰り返し
仕事や日常生活において、長時間にわたって同じ動作を繰り返すことが多いと障害の原因になることもあります。
たとえば、重い荷物の持ち上げ作業や、無理な姿勢での長時間にわたるPC作業などが挙げられます。
関連記事:障害によるしびれが残った場合の法的責任と対応について
肩の後遺障害で見られる主な症状

肩に後遺障害が発生すると、具体的にどういった症状が見られるのでしょうか。
上記でも簡単にご紹介しましたが、代表的な症状の例を詳しく解説します。
肩の可動域制限
可動域制限とは、腕の上げ下げや腕を回すといった動作の範囲が極端に狭くなる状態を指します。
可動域制限は関節を支える筋肉や腱が損傷したり硬くなったりすることで生じるケースが多く、服を着たりモノを持ち上げるといった日常的な動作が困難になります。
痛みやしびれ
肩の慢性的な痛みや、肩から腕にかけてのしびれが見られることもあります。
痛みは肩の筋肉や腱の損傷、炎症などが原因で生じることが多く、しびれは肩や腕の神経が何らかの理由で圧迫されたり、損傷したりすることで起こります。
痛みやしびれが重症化すると、肩を動かすことができなくなったり、思うように力が入らず日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
肩の変形
肩の骨折や脱臼を放置していたり、適切な治療が行われないと骨や関節の形が変形することもあります。
アンバランスな見た目になることはもちろんですが、形状が変わることで本来の関節の役割を果たすことができなくなったり、慢性的な痛みの原因につながる可能性もあります。
肩から先の欠損
重度の外傷を負ったり、必要な治療をせず放置しておいた結果、最悪の場合肩や腕の一部が失われることもあります。
たとえば、交通事故などで外傷を負ったものの放置しておくと、傷口から細菌が侵入し重度の感染症となり、手術によって腕を切断するといったケースも考えられます。
その結果、義手の装着を余儀なくされ日常生活にもさまざまな支障が生じます。
肩に適用される後遺障害等級
スポーツや事故によって重度のケガを負い、何らかの後遺障害が残った場合、保険金を受け取れる可能性があります。
一口に後遺障害といってもさまざまなケースに分類され、その等級によっても保険金の金額は変わります。
肩に適用される後遺障害等級は以下の通りです。
- 1級4号:両方の腕が全く使えない状態
- 5級6号:片方の腕が全く使えない状態
- 6級6号:片方の腕の3つの主要な関節(肩、肘、手首)のうち2つが全く使えない状態
- 8級6号:片方の腕の3つの主要な関節のうち1つが全く使えない状態
- 10級10号:片方の腕の3つの主要な関節のうち1つに著しい障害がある状態
- 12級6号:片方の腕の3つの主要な関節のうち1つに障害がある状態
上記の中で「全く使えない状態」と「著しい障害がある状態」、「障害がある状態」という表現がありますが、これはそれぞれどういった状態を指すのでしょうか。
「全く使えない状態」とは、肩から先のすべての関節が強直、麻痺、あるいは切断された状態を指します。
「著しい障害がある状態」とは、関節の可動域が2分の1以下に制限されている状態、「障害がある状態」とは可動域が4分の3以下に制限されている状態を指します。
関連記事:交通事故のリハビリ日数や回数|通院中でも慰謝料はもらえる?
肩の後遺障害が認定されるまでのプロセス

肩の後遺障害は事故後に即座に認定されるものではなく、さまざまな手続きを経る必要があります。
今回は交通事故によって肩に後遺障害を負ったケースを想定し、大まかに7つのプロセスに分けてご紹介しましょう。
1.症状固定の診断を受ける
症状固定とは、今後治療を続けても症状が改善する見込みがない状態を指します。
症状固定であるか否かは医師による診断が必要であり、後遺障害等級を認定してもらうためには6ヶ月以上の治療期間が必要とされています。
2.後遺障害診断書の作成
症状固定の診断を受けたら、担当医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
レントゲンやMRIの所見などの資料をもとに、具体的な症状や可動域制限の程度などを記載します。
3.後遺障害等級認定の申請
必要書類や資料が用意できたら、後遺障害等級認定の申請を行います。
申請には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があり、以下のような違いがあります。
- 事前認定:後遺障害診断書のみを保険会社へ提出
- 被害者請求:後遺障害診断書とその他必要な資料をあわせて保険会社へ提出
被害者請求は本人がさまざまな資料を集める手間がかかるものの、検査結果などの資料も添付できるため有利に進めやすいといったメリットがあります。
4.後遺障害等級の認定結果の受領
書類一式を受け取った保険会社は、損害保険料率算出機構という団体に申請します。その後、個別に審査が行われ後遺障害等級の認定結果を通知します。
5.損害賠償請求の準備
後遺障害等級が正式に認定された後は、加害者側に対する損害賠償請求の準備に入ります。
一般的には加害者本人ではなく加害者が加入している保険会社に請求するケースが多いです。
ただし、加害者が業務中に事故を起こした場合には勤務先の会社にも賠償責任が問われる可能性があります。
6.示談交渉
損害賠償額を決定するために、加害者側との示談交渉を行います。
損害賠償請求の対象となるのは主に治療費や入院費、通院費などの実費のほか、慰謝料も含まれます。
後遺障害が認定された場合には、精神的損害として後遺障害慰謝料も加算されます。
7.合意・示談成立
加害者側との示談交渉が成立した後は、所定の手続きを行い賠償金が支払われます。
肩の後遺障害が認定されるためのポイント

交通事故などによって肩に何らかの障害が残った場合、後遺障害として認定を得るためには以下のポイントに留意しながら手続きを進める必要があります。
下記をすべて満たしているからといって、必ずしも認定を受けられると保障できるものではありませんが、最低限のポイントとして押さえておきましょう。
医学的証拠を確保すること
後遺障害の有無は客観的な証拠に基づいて判断されることが多いため、医学的な証拠となる資料やデータを準備しておくことが大切です。
具体的にはレントゲンやMRIといった画像診断の結果や、可動域検査の記録などを揃えておきましょう。
症状に一貫性と継続性があること
診察や治療の記録に矛盾がなく、一貫して同じ症状が継続していることを証明しなければなりません。
たとえば、治療の過程において一時的に症状が良くなったり悪化したりすることもありますが、そのような場合でも詳細な経緯を記録しておくことが必要です。
事故との因果関係が証明できること
後遺障害の認定を受けるためには、その症状が交通事故によるものであることを明確に証明できなければなりません。
たとえば、事故の直後は痛みが軽度であったものの、数週間後に症状が悪化し初めて診察を受けたという場合、事故との因果関係が証明しにくくなります。
そのため、事故後はできるだけ早めに医療機関を受診し、精密検査や医師の診察を受け記録として残しておく必要があります。
後遺障害診断書が適切に作成されていること
後遺障害が認められる症状があったとしても、後遺障害診断書にその内容が適切に記載されていないと客観的な証拠が不足し、認定を却下される可能性もあります。
診断書の作成時には、医師が後遺障害等級認定の基準をしっかりと理解していることはもちろんですが、症状や機能障害について明確かつ具体的に記載してもらうことも不可欠です。
関連記事:後遺障害が認定されない5つの理由|認定されるための対処法とは
肩の後遺障害のことならYKRメディカルコンサルトへご相談ください
後遺障害は申請したからといって必ずしも認定されるとは限らず、書類や資料の不足、客観的な証拠に乏しいなどの理由で却下される可能性もあります。
そのため、交通事故などによって肩を負傷し治療を行っているものの、後遺障害が認定されるか不安に感じている方も多いでしょう。
そのような場合には、YKRメディカルコンサルタントへご相談ください。
当社では診断書や各種検査結果、資料などをもとに医学的見地の高い専門家による意見書の作成を代行しています。
たとえば、「これから後遺障害認定の申請をするにあたって説得力のある資料を準備したい」あるいは「後遺障害認定の結果に対して異議申し立てを検討している」という場合にお役立ていただけます。
まとめ
肩の後遺障害にはさまざまな等級があり、比較的軽度の症状であっても認定の対象となる可能性があります。
しかし、後遺障害認定には客観的な証拠や資料を揃える必要があり、これらが不足していると認定が却下される可能性も否定できません。
交通事故などによって肩を負傷したら、まずは早めに医療機関を受診し診断書を作成してもらい、治療の経過に応じて後遺障害認定の申請を検討してみましょう。