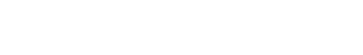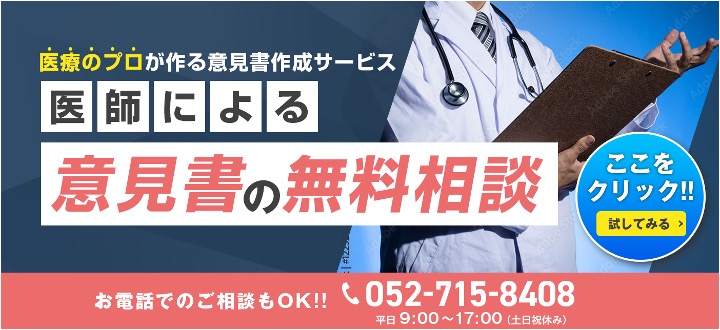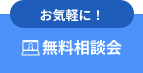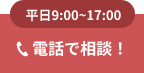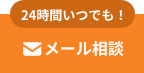高齢者の遺言能力と認知症:生前鑑定を用いた医師による評価とトラブル回避のポイント

遺言者(遺言をする人)の判断能力、いわゆる「遺言能力」は、遺言書の有効性を左右する非常に重要な要素です。
もし遺言者に遺言能力がなければ、どんなに形式を整えた遺言書でも無効になってしまいます。
そのため、高齢者や認知症の疑いがある方の遺言では医師による遺言能力の評価が重要な役割を果たします。
精神科医や神経内科医といった専門医による客観的な評価は信頼性が高く、遺言能力を巡る紛争の予防や解決に大きく寄与します。
本記事では、弁護士の皆様向けに、遺言能力判断における精神科・神経内科医の役割を詳しく解説し、その医学的判断の信頼性について考察します。
遺言能力の適切な判断がなぜ重要なのか、そして医師との連携によってどのように遺言作成をサポートできるのかをまとめていきます。
遺言能力の基本と背景

法的定義と民法の規定
遺言能力とは、「有効に遺言を行うことができる能力」のことです。
民法には遺言能力に関する明確な規定があり、まず年齢要件として満15歳以上であれば単独で遺言をすることができます。(民法961条)
また、民法963条で「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められており、遺言をする瞬間に意思能力(事理を弁識する能力)が備わっていなければ遺言は無効になります。
つまり、たとえ15歳以上であっても、遺言内容およびそれによる法的効果を理解できる判断能力が欠けていれば遺言は成立しません。
なお、民法962条により、未成年者の同意や成年後見制度の制限(制限行為能力者に関する規定)は遺言には適用されません。
このため、成年被後見人(判断能力が著しく低下し後見人が付いている人)であっても、一時的に判断力を回復すれば医師2名の立会いと証明により遺言をすることが可能です。(民法973条)
医学的観点からの遺言能力
医学の立場では、遺言能力は主に認知機能と精神状態によって評価されます。
遺言を理解し判断するためには、自分の行為が法的にどんな結果をもたらすかを理解する知的能力(意思能力)が必要です。
例えば「自分の財産をAさんに遺贈する」という遺言をした場合、その結果として自分の死後にその財産がAさんのものになるといった因果関係を理解できる能力が求められます。
認知症や精神疾患などでこの理解力・判断力が失われていれば意思能力なしと判断され、遺言は無効となります。
一方で、軽度の認知症であっても遺言内容が本人にとって理解可能な範囲であれば意思能力が認められるケースもあります。
医学的には、遺言者が記憶力や判断力を保ち、自分の財産状況や相続人関係を把握できているかが重要であり、これらが遺言時に保たれているかどうかを専門医が評価します。
結果として、法的な遺言能力の有無は、医学的な判断要素に大きく影響されるのです。
関連記事:遺言書作成時の認知症の程度の問題について
医師が判断する理由
専門的知見が必要なため
遺言能力の有無の判断には高度な専門知識が求められます。
高齢者や認知症の方の微妙な認知機能低下を評価したり、精神疾患による判断力の影響を見極めたりするには、精神科医や神経内科医の専門性が不可欠です。
これら専門医は日常的に認知症や統合失調症等の脳機能・精神機能の評価を行っており、記憶・思考・判断力の状態を客観的に評価しています。
特に認知症専門医(老年精神科医や神経内科医)は、アルツハイマー型認知症など各種認知症の症状進行度を診断することを専門としているため、遺言者の判断能力を適切に評価できます。
主治医が精神科や脳神経内科等の専門医である場合、その診断書や所見は遺言能力を裏付ける有力な根拠となります。
医師の判断が尊重される
遺言能力をめぐる争いでは医学的評価が極めて重視されます。
裁判所も、遺言者の意思能力について専門医が下した判断を重要な証拠として扱います。
例えば、遺言作成時に主治医が「認知症は軽度で判断能力は十分」と診断していれば、その遺言は有効と認められる可能性が高まります。
実際、権威ある精神科医や神経内科医、脳神経外科医、放射線科医など複数の専門医が協力して遺言者の判断能力を医学的に評価し、鑑定書という形で客観的資料を提供するサービスも存在します。
これは遺言書に専門医の鑑定書を添付してトラブルを未然に防ぐ取り組みであり、近年注目を集めています。
医師の判断は最終的な法的結論を直接決定するものではありませんが、その客観性と専門性ゆえに信頼性の高い証拠として尊重され、裁判官の判断を強くサポートするのが現状です。
認知症鑑定のプロが果たす役割
認知症や精神疾患による判断能力低下の評価には、一般内科医よりも専門医の関与が望ましいです。
認知症の種類(アルツハイマー型、レビー小体型、血管性など)によって認知機能の障害パターンは異なり、その理解には専門知識が必要です。
精神科・神経内科医は遺言者が一時的な混乱(せん妄)なのか慢性的な認知症なのか、あるいは妄想や幻覚によって判断が歪められていないかといった点も含めて総合的に判断します。
例えば統合失調症の患者でも病状が安定していれば意思能力が保たれる場合がありますし、逆に一見元気な高齢者でも初期のレビー小体型認知症で判断力が揺らいでいるケースもあります。
専門医による精密な評価によってこそ、こうした微妙なケースでの遺言能力の有無は専門性が極めて高く、適切な診療科の医師が対応することが重要となってきます。
関連記事:ナットウキナーゼ|ニュートライズ
関連記事:ルンブロキナーゼ|ニュートライズ
医学的評価のプロセス

遺言能力評価の流れ
医師による遺言能力の評価は、一般的に以下のようなプロセスで進められます。
まず問診により遺言者の現在の症状や既往歴、生活状況について詳細に聴取します。
その上で認知機能検査を実施します。代表的な検査にはMMSE(ミニメンタルステート検査)とHDS-R(長谷川式簡易知能評価スケール)があります。
MMSEは世界的に用いられる30点満点の検査で、見当識(日時や場所の理解)、記憶力、注意力、計算、言語能力、視空間認知など幅広い認知機能を短時間で評価できます。
HDS-Rは日本で開発された認知症検査で、16の質問項目からなり、日本の高齢者に適した評価尺度です。
HDS-Rも満点30点で、例えば20点未満であれば認知症の疑いが強いなど、点数が低いほど認知機能低下の程度が疑われます。
こうした検査により記憶力や理解力の客観的指標が得られます。
場合によっては時計描画テストや前頭葉機能検査など追加の神経心理検査を組み合わせることで判断力や実行機能も評価します。
診察・検査と結果分析
認知機能テストに加えて精神状態の診察も重要です。
医師は面接の中で遺言者が自分の置かれた状況を正しく理解しているか、今から作成しようとする遺言の意味を把握しているかなどを観察します。
また、うつ病やせん妄の有無、幻覚妄想の兆候がないかも確認します。
必要に応じて神経内科的な身体診察も行い、片麻痺など脳血管障害の後遺症の有無などを調べます。
さらに客観的な裏付けとして画像診断を活用することもあります。
例えば、MRI検査では脳萎縮や脳梗塞・脳出血の痕跡、水頭症、慢性硬膜下血腫などを確認できますし、必要に応じて脳血流SPECT検査を行えばアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症に特徴的な脳の血流低下パターンを評価できます。
これら医学的検査結果は、遺言者の脳の状態を客観的に示す資料となり、評価の精度を高めます。
実際、裁判においてもHDS-RやMMSEなどの検査結果や画像所見が参考にされることが多く、遺言能力判断の重要な材料となっています。
ただし検査結果の数値だけで遺言能力の有無を断定することはできないため、医師は検査結果と臨床所見の両面から総合判断します。
例えばHDS-Rが10点程度しかないような重度認知症の場合は遺言能力が否定されやすいですが
、15~20点前後の中等度の場合は遺言内容の難易度や日常の様子次第で判断が分かれます。
医師はそうした数値だけでなく、面接で得た印象や家族からの聞き取り情報なども踏まえて評価します。
評価
診察と各種検査を終えたら、医師は評価評価を行い、治療を開始します。
カルテには遺言者の意識レベルや受け答えの様子、検査の結果とその解釈、医学的診断名などが記載されます。
例えば「〇年〇月〇日時点で、長谷川式スケール〇点、MMSE〇点。見当識は良好で自分の財産と相続人を正しく把握。
短期記憶に軽度の障害が見られるものの、遺言内容とその法的効果を理解する能力は保たれていると判断される。」といった具体的な所見と結論を示します。
生前鑑定として医師が関与できる場合はレポートとして診断書や意見書として作成することが可能ですが、もし遺言者の没後に係争の資料として当時の記録を調査するという場合、特に遺言時点での判断能力の有無について可能な限り明確に言及しますが、もし遺言のことを医師へ話していない場合には検査と検査の間で作成されていた場合は注意が必要になります。
非常に難しい判断となるため、専門性が極めて高くなります。
関連記事:労災の休業補償の計算方法とは|会社負担はどれくらい?
判断基準と実例
遺言能力の主な判断基準
遺言能力を評価する際、以下のようなポイントが主要な判断基準となります。
これらは実務上しばしば参照される要素であり、個々のケースで総合的に検討されます。
弁護士の方が遺言能力を検討する際のチェックリストとしても活用できるでしょう。(※具体的な事例は後から追加して適用できる形式です)
認知機能の状態
記憶力・理解力・見当識(時間や場所、人の認識)などが保たれているか。
低下がある場合でも、その程度が遺言内容を理解するうえで許容範囲かどうかが問われます。
判断力・意思決定能力
論理的に物事を判断できるか、自分の意思で取捨選択ができるか。認知症や精神障害による判断力低下があれば慎重な検討が必要です。
例えば重度の認知症で判断能力が期待できない状態なら遺言は無効になりやすいため注意するポイントとなるでしょう。
遺言内容の複雑さ
遺言の内容自体が簡単か複雑かも重要です。
シンプルな内容(例:「全財産を妻に相続させる」等)であれば、遺言者の理解も容易なため、多少認知機能が低下していても有効と認められやすい傾向があります。
逆に多数の受遺者に細かく配分するような複雑な内容だと高い判断能力が求められ、軽度の認知症でも無効と判断されるリスクが高まります。
意思の自由(自発性)
遺言が遺言者本人の自由意思に基づくものかどうかも審査されます。
他人(特に遺言で利益を受ける者)から強制・誘導されていないか、本人の自発的な意思表示であるかが重要です。
遺言作成の経緯で、特定の相続人が主導して内容を決めた形跡があれば遺言能力が疑われます。
反対に本人の強い意志で作成されたのであれば能力が認められやすいでしょう。
動機・理由の合理性
遺言内容が本人のこれまでの言動や家族関係に照らして不自然でないか検討します。
例えば生前ずっと長男を冷遇していた人が急に長男に全財産を譲る遺言を残した場合、不合理であり判断が適切でなかった可能性があります。
一方、介護を担ってくれた子に多めの財産を遺贈するのは合理的動機であり、妥当な判断と考えられます。
日常生活能力と言動
遺言前後の普段の生活状況も判断材料です。
食事や身の回りのことが自分でできていたか、新聞を読んで内容を理解できていたか、人や出来事に対する受け答えに不自然な点はなかったか等を確認します。
これらから遺言時点の精神状態を推測します。
遺言書の体裁
特に自筆証書遺言の場合、遺言書に書かれた文字の状態や訂正の多さなども手掛かりになります。
内容が簡単にも関わらず文字が極度に乱れていたり誤字脱字が多かったりする場合、認知機能低下の可能性があります。
逆に整然と書かれていれば判断力が保たれていた一指標となりえます。
以上の基準を総合して遺言能力の有無が判断されます。
実務では、医学的評価(認知機能・精神状態)と法律実務上の状況証拠(遺言内容や経緯など)を突き合わせて結論づける形になります。
例えば、ある判例ではHDS-Rが15点(認知症の中等度を示唆)だった高齢者について、「短期記憶は障害されていたが長期記憶は保たれ見当識も良好だった」こと等から遺言能力を肯定しています。
逆にHDS-Rが10点以下の重度認知症で日常生活にも支障が出ていた場合は、医師の診断書等がなくても遺言無効と判断された例があります。
このように事例ごとに事情は異なりますが、上記の基準に沿って検討することで、弁護士は遺言能力の有無をある程度予測し、必要な医学的証拠を準備することができます。
関連記事:遺言は録音やビデオメッセージでも有効?書けない場合の対応方法について解説|弁護士法人 東京新宿法律事務所
医師との連携と相談の流れ

専門医との連携方法
遺言能力に不安があるケースでは、早めに医師と連携して対応策を講じることが重要です。
弁護士が医師と連携するには主に
(1) 遺言作成前の事前評価と(2) 遺言作成後(紛争時)の事後鑑定の二つの場面があります。
事前評価の場合、依頼者(遺言者予定者)の同意を得た上で精神科医・神経内科医の診察を手配し、遺言能力の診断書を作成してもらいます。
これは公正証書遺言を作成する際などに、公証人への提示資料として有用ですし、将来の紛争予防にもなります。
一方、事後鑑定の場合は、遺言者の死亡後に相続人間で遺言の有効性が争われた際、当時の診療記録や介護記録を専門医に鑑定依頼し、遺言能力鑑定意見書を作成してもらう形になります。
どちらの場合でも、専門医と弁護士の綿密な情報共有が不可欠です。
医師には遺言者の病歴や当時の状況についてできるだけ詳細な資料を提供し、弁護士は医師から医学的見地の説明を受けて法的主張に活かします。
YKR Medical Consultの活用
医師との連携をスムーズに行うためのサービスとしてYKR Medical Consultがあります。
YKR Medical Consultは弁護士向けの医学コンサルティングサービスで、遺言能力の評価・鑑定を含む様々な専門医意見書作成をサポートしています。
同サービスでは無料のオンライン相談会を随時開催しており、初回利用の弁護士は無料で専門医に相談できます。
具体的な流れとして、まずホームページの問い合わせフォームや電話で連絡し、相談したい案件の資料を事前に送付します。
資料には医療記録や検査結果のほか、遺言者の日常生活状況がわかる情報(認知症の場合は介護記録や本人の手紙など)も含めるとより的確なアドバイスが得られます。
日程調整の上、案件内容に適した専門医がZoom等を用いたオンライン面談で相談に応じてくれます。
この無料相談で医学的観点からの見通しや必要な追加検査項目などについて助言を受けることができ、相談後に正式な意見書作成を依頼するか検討します。
実際の連携プロセス
たとえば、ある高齢の依頼者について「軽い認知症だが遺言を作成したい」という相談があった場合、弁護士はYKRに相談を申し込みます。
事前に送付した資料(認知症の診断記録や最近の様子のメモ等)をもとに、認知症専門医がオンラインで面談し、「現在の認知機能なら公正証書遺言であれば問題なく作成可能だが、内容はできるだけ簡潔にした方が良い」等のアドバイスを提供します。
その後、依頼者本人の診察が必要と判断されれば、面談した医師が実地またはオンラインで本人を評価し、生前意思能力鑑定意見書を作成する流れになります。
一方、遺言無効訴訟で争われているケースでは、YKRに遺言者のカルテや当時の経緯資料を送り、専門医がそれを精査して遺言鑑定意見書(遺言時の意思能力に関する鑑定書)を作成します。
YKRでは医療機関と同等の診断システムを導入しており、Zoom画面共有機能を用いて遠隔地からでも詳細な相談・資料検討が可能です。
このような連携サービスを活用することで、弁護士は自ら医学の専門知識がなくても適切なエビデンス収集と専門的主張ができるようになります。
結果的に依頼者にとって最善の形で遺言を作成・防衛することが可能となるのです。
Q&A
Q1. 認知症と診断された依頼者でも遺言能力はありますか?
A: 認知症と診断されていても、一律に遺言能力が否定されるわけではありません。
認知症には軽度から重度まで段階があり、軽度であれば判断能力が保たれている場合も多いです。
実際、認知症がかなり進行していたケースでも遺言内容が極めて簡単であったために有効と認められた例があります。大切なのは遺言をする時点の本人の状態です。
一時的に調子が良いタイミングであれば意思能力が発揮できることもあります。
依頼者が認知症の場合は、医師による詳細な評価を受けてもらい、専門医の診断書で遺言可能な状態か確認すると安心です。
Q2. 依頼者が「お医者さんに診てもらうのは嫌だ」と言っています。どうすれば良い?
A: 高齢の依頼者の中には医師の評価に消極的な方もいます。
その場合でも遺言の有効性を確保するために医師の関与が有益であることを丁寧に説明しましょう。
例えば「将来、せっかく作った遺言が無効になるとご本人の意思が実現できなくなります。
今のうちに検査を受けておけば安心です」という趣旨を伝えます。
それでも難しい場合には、せめて主治医の簡易な診断書(「〇年〇月現在、意思能力に問題なし」といった内容)だけでももらえないか検討します。
それも困難であれば、公正証書遺言の作成時に公証人へ相談し、状況によっては公証人から本人への質問記録を詳細に残してもらう方法もあります。
将来的に争いになった際、その記録が本人の応答状況を示す間接的な証拠となるからです。
いずれにせよ、ベストは依頼者に安心してもらえるようプライバシーに配慮した形で専門医と面談の機会を作ることです。
対面だけでなくオンライン(Zoom等)で専門医の相談が受けられるところを利用し、病院に行かずに自宅から評価を受けることも可能な場合があります。
Q3. 遺言能力の確認にあたって、どの診療科の医師に依頼すればいいですか?
A: 遺言能力評価では主に精神科または神経内科の医師が適任です。
認知症が疑われる場合は神経内科医や老年精神科医、精神疾患が背景にある場合は精神科医が良いでしょう。
一般内科医でもかかりつけ医であれば事情をよく知っていますが、専門的な検査(長谷川式スケール等)を実施していないこともあります。
その点、専門医であれば適切な検査を実施し、診断書や所見も専門的内容を書いてもらえます。
実務上は、まず依頼者の主治医がいればその医師に相談し、必要なら専門医を紹介してもらうのがスムーズです。
主治医が精神科・神経内科の専門医ならベストです。専門性の高い医師の診断であれば、裁判になった場合でも強力な証拠となります。
Q4. 医師の評価を受けるのに費用や時間はどのくらいかかりますか?
A: ケースによりますが、一般的な認知機能検査と診断書作成であれば数日〜数週間程度で完了することが多いです。
例えば簡易な認知症テスト(HDS-Rのみ)であれば数日で結果が出るケースもあります。
費用については、主治医に診断書を書いてもらう場合は数千円〜数万円、公正証書遺言に医師二人を立ち会わせる場合は各医師への謝礼等が必要になるでしょう。
専門の鑑定医に正式な鑑定書作成を依頼する場合は、内容の複雑さによりますが数十万円規模になることもあります。
しかしその費用対効果は大きく、遺産額や将来の訴訟リスクを考えれば、遺言を無効にさせない保険と考えて依頼者に提案してみる価値があります。
Q5. 成年被後見人になっている人でも遺言できますか?
A: はい、法律上可能です。ただし通常、成年被後見人(認知判断能力が著しく低下し後見開始されている人)は契約など法律行為を単独ではできません。
しかし遺言については例外があり、一時的に判断能力を回復した状況であれば遺言を作成できます。具体的には、公正証書遺言の形式で医師2名の立会いのもと行う必要があります。(民法973条)
2名の医師は遺言者がその時点で意思能力を有することを確認し、遺言書に立会人として署名押印します。
この手続きを経れば、成年被後見人であっても有効な遺言が可能です。ただし実務上、このような医師立会いの遺言は多くありません。
本人が後見人の支援なしで遺言できるほど回復するケース自体が限られるためです。
もし依頼者が現在後見を受けている場合は、公証人や専門サービスと相談し、医師手配を含めた適切な手続きを検討してください。
Q6. 医師の鑑定書があれば遺言訴訟で必ず勝てますか?
A: 医師の鑑定書は非常に強力な証拠ですが、それだけで「必ず勝てる」と断言はできません。
裁判所は最終的に、医師の意見書・診断書だけでなく遺言内容や作成状況、他の証拠も総合的に判断します。
ただし専門医による詳細な鑑定書があることで、少なくとも遺言者の判断能力に関する主張は裏付けられます。
争う側(遺言無効を主張する側)は医学的反証を示すのが難しくなり、弁護士として有利に論じられるでしょう。
特に遺言作成時の診断書や鑑定書が存在するケースでは、相手方も訴訟提起を思い留まる可能性があります。重要なのは鑑定書の内容の充実度です。
簡単に「問題なし」と書かれただけの診断書より、検査結果や経過、医師の所見が詳述された鑑定書の方が裁判官の心証も良くなります。
質の高い詳細な意見書を準備する意味でも専門家に依頼するメリットは大きいと言えます。
Q7. 遺言能力の評価項目について依頼者から質問されたらどう答えるべき?
A: 依頼者(遺言者ご本人やそのご家族)から「どんなことをチェックされるのか?」と聞かれた場合は、できるだけ平易に説明しましょう。
「お名前や今日の日付を正確に答えられるか」「ご自分の財産をどのくらい持っていて、誰に相続させたいかちゃんと考えられているか」といった具体例を挙げると理解してもらいやすいです。
専門的には記憶や判断力テストをする旨も伝え、「算数の問題を少し解いてもらったりしますが、学校のテストではないので心配いりません」と不安を和らげます。
要は今のしっかりしたお気持ちを文章に残すための確認作業という位置づけであることを強調します。
また、「医師に診てもらうのは失礼では?」と気にされる方には「後でご本人の判断力について周りが心配しないよう、お守り代わりにお医者さんのお墨付きをもらっておきましょう」という説明も有効です。
依頼者に安心して協力してもらうため、医師評価の目的とメリットを丁寧に伝えてください。
関連記事:遺言能力の有無に必要な判断基準|医学要素が重要な理由を解説
まとめと今後の展望
遺言能力の判断において、精神科・神経内科医の果たす役割は極めて重要です。
法的には満15歳以上で意思能力を備えていることが遺言成立の前提ですが、その「意思能力」があったかどうかは医学的評価に負うところが大きいということを見てきました。
認知症高齢社会において、遺言能力をめぐる争いを避けるためには事前の医学的確認が有効であり、専門医による判断が遺言の有効性を支える柱となります。
弁護士にとっても、医師との連携により依頼者の真意を確実に実現できる遺言作成をサポートできる点で、大きなメリットがあります。
今後さらに高齢者の遺言作成が増える中で、医師による遺言能力鑑定サービスは一層需要が高まるでしょう。
すでにYKR Medical Consultをはじめ、医学と法律の橋渡しをする専門サービスが登場し始めています。
本記事でも触れたように、専門医の鑑定書を遺言書に添付しておく取り組みは、将来の「争族」(争いになる相続)を防ぐ有効な手段として注目されています。
AI技術の発展により簡易認知機能テストの自動化や遠隔診断の精度向上も期待できますが、やはり最終的な評価は人間の専門医によるきめ細かな判断が不可欠です。
医師と弁護士が協働して依頼者を支える枠組みは、今後ますます発展していくでしょう。
YKR Medical Consultへの相談案内
遺言能力に少しでも不安があるケースに直面したら、早めに専門医の力を借りることをおすすめします。
YKR Medical Consultでは、遺言能力評価に関する無料相談や各種鑑定書作成サービスを提供しています。
専門の精神科医・神経内科医チームがスタンバイしており、オンラインで全国から相談可能です。弁護士の方が抱える「この依頼者で本当に大丈夫だろうか?」という悩みに対し、医学的な視点から明快な答えや方針を示します。
ぜひお気軽にお問い合わせいただき、依頼者の意思実現と円満な相続の実現にお役立てください。専門家の連携によって、より安心・確実な遺言作成をサポートしていきましょう。
お問い合わせや詳細はYKR Medical Consultの公式サイトをご覧いただくか、直接ご連絡ください。きっと力強いパートナーとなれるはずです。