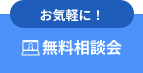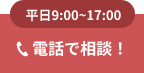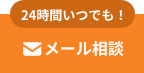遺言能力の有無に必要な判断基準|医学要素が重要な理由を解説
遺言書に法的な効力を持たせるには「遺言能力」が必要です。
裁判で遺言能力が認められるには医学的な判断が重要となってきます。
つまり法的に遺言能力が認められるために医学要素が大きな影響を及ぼすのです。
この記事では遺言能力の判断において重要な医学要素や医学要素を用意する具体的な方法について解説します。
これから遺言書を作成する方や、すでに作成された方はぜひ参考にしてみてください。
目次
遺言能力があると認められるために必要なもの

遺言能力とは、遺言者が自分の遺言の内容を理解する能力です。
遺言は15歳以上であれば作成できますが、年齢がいくつであれ遺言能力が必要です。
遺言能力が失われた状態で遺言を作成しても無効になってしまいます。
遺言能力が認められるには、以下の条件を満たさねばなりません。
遺言者が15歳以上であること
遺言を行うには、遺言者が15歳以上でなければなりません。
反対に、15歳以上になっていれば未成年者であっても遺言ができます。
民法961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
本人が遺言したこと
遺言は代理ではできないので、必ず本人がしなければなりません。
たとえ未成年者の親であっても子どもを代理して遺言はできません。
遺言者に遺言内容を理解するだけの意思能力があること
遺言者に十分な判断能力が必要です。
自分の遺言の内容を理解するだけの能力がなかったら遺言能力は認められません。
たとえば認知症が進行して意思能力も失われている状態の人が遺言書を作成しても無効になってしまいます。
医学要素が遺言能力の有無の判断に重要な理由

遺言能力の有無を判断する際には、医学要素が重要となってきます。
医学要素とは、医学的な観点から本人の精神状態などを判断するための材料です。
たとえば医師による検査結果や診断内容、カルテや看護日誌などが医学要素になります。
遺言が行われた当時においてご本人の精神状態について検査が行われ、その結果を記録しておけば後で遺言能力について争われた際に有効な判断の指標になります。
たとえば医師による診断書で「遺言が行われた当時、本人は認知症にかかっていなかった」「認知症は軽度で十分に判断能力があった」などと書かれていた場合、遺言書は有効になる可能性が高いでしょう。
遺言能力の判断基準

遺言能力が認められるかどうか判断するには、以下の3つの要素が重要な材料となってきます。
- 医学的に遺言の内容を理解できるだけの判断能力があると認められること(精神医学的観点)
- 遺言内容が遺言者の精神状態からして理解できる内容であること(遺言内容の複雑さ)
- 遺言の動機や理由
①医学的に遺言の内容を理解できるだけの判断能力があると認められること(精神医学的観点)
遺言能力で問題になる「意思能力」は精神的な判断能力の問題です。
よって遺言が行われた当時の遺言者の精神状態を医学的に判断することが必要となります。
たとえば医師による診断書で「認知症が重症であり判断能力は期待できない」とあれば、そういった人の書いた遺言書は無効になりやすいでしょう。
ただし実際には診断書で本人の精神状態を図ることは簡単ではありません。
そこで指標として「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R) 」という検査を利用するケースがよくあります。
長谷川式簡易知能評価スケールでは、20点以下で認証症が疑われます。
ただし認知症だからといって必ずしも意思能力がないという結論にはなりません。あくまでこの後説明する②や③との総合評価になります。
>>【相続トラブル】認知症の遺言能力について|判断基準や事例を解説
②遺言内容が遺言者の精神状態からして理解できる内容であること(遺言内容の複雑さ)
次に「遺言内容の複雑さ」も重要な判断要素となります。
遺言内容が複雑であれば、本人が理解するのも難しくなるでしょう。
そのため高度な意思能力が必要となってきます。
反対に遺言内容が「財産を全部妻に相続させる」などの簡単なものであるなら、判断能力が相当低下していても理解しやすく、認知症がある程度進行していても遺言が有効になりやすいといえます。
③遺言の動機や理由
3つ目に「遺言の動機や遺言する理由」、すなわち普段の言動や相続人・受遺者との関係性も問題になります。
たとえば普段から「長男には遺産をやらない」と言っていた人が突然長男にすべての財産を相続させる内容の遺言を遺すと明らかに不自然といえるでしょう。
動機や合理的でないので判断が適切に行われておらず、遺言能力に欠けると判断されやすいといえます。
一方で、普段から仲良くしていた人や介護などで世話になった方へ多くの遺産を遺す場合には合理的なので遺言能力が認められやすくなります。
医師による診断で遺言能力が有効となった事例

遺言能力が認められるには上記の3つの要素が重要ですが、中でも医学要素はかなり重視されます。
以下では医師による診断(精神医学的観点)が重視されて遺言書が有効とされた裁判例を紹介します。
長谷川式認知スケールが15点だったケース
80代後半の男性が3回遺言書を作成したケースです。
短期記憶に障害がありましたが、長期記憶の障害はなく人や場所、日時はすべてわかる状態でした。
公正証書遺言が作成されており、遺言書は有効と判断されました。
長谷川式認知スケールが27点だったケース
遺言内容が相当複雑だったケースです。
女性はアルツハイマー型認知症と判断されており、軽い実行機能障害の低下や空間認知能力の低下が見られました。
公正証書遺言が作成されていましたが、遺言書は有効と判断されました。
医師が遺言能力の有無を判断するまでの流れと期間
医師が遺言能力の有無を判断するまで、どういった流れになるのか、またどのくらいの期間がかかるのか見てみましょう。
医師が精神状態を判断するまでの流れ
医師に遺言能力の判断をしてもらう場合、まずは医師を探して精神鑑定を依頼する必要があります。
その後医師が鑑定に取り組み、検査等を実施して鑑定書を作成します。
精神鑑定にかかる期間
検査内容や医師の忙しさ、ご本人の状況などによって異なりますが、1か月以内で完了するケースが多いでしょう。
次に紹介する長谷川式簡易知能スケールのみの検査であれば、数日でできるケースもあります。
長谷川式簡易知能スケールは遺言能力の有無を判断できるのか
医師が認知症患者に対する精神鑑定を行う場合、用いられることの多いのが長谷川式簡易知能スケール(HDS-R)という評価指標です。
見当識や記憶などの9つの項目についての検査を行うものであり、満点が30点です。
20点以下の場合、医学的には認知症の疑いがあると考えられています。
裁判所は15点を下回る場合に遺言能力を否定する傾向があります。
裁判でも長谷川式簡易知能スケールの結果が参照されるケースが多く、遺言能力の判定には一定の有用性が認められるといえるでしょう。
遺言能力を明らかにするために医学要素を用意したい場合、長谷川式のみに頼るのではなくもう少し幅を広げた検査が必要となるでしょう。
>>【相続トラブル】認知症の遺言能力について|判断基準や事例を解説
YKRは認知症の種類や重症度、脳機能障害などの判断も可能
死後に遺言書について争いが発生すると、解決するのに何年もかかるケースが多数です。
弁護士費用や裁判費用も発生しますし、家族が喧嘩別れしたり家業がうまく引き継げなくなったりするリスクも発生します。
トラブルを防止するにも適切な医学要素を使って遺言能力を証明することが非常に重要です。
YKRには認知機能や精神機能の専門家が多数います。
死後に遺言作成当時に作成能力があったかどうかの鑑定にも対応していますが、作成時点で遺言能力を専門医が鑑定する方が遺言を作成される方にとっても次の世代の方たちにとっても安心できます。
ここまで主に長谷川式簡易知能評価スケールを中心にお話ししてきましたが、遺言作成能力を測れるのは長谷川式簡易知能スケールだけではありません。
例えば、画像検査においてMRIでは脳萎縮、脳梗塞や脳出血、脳血管性認知症、水頭症、慢性硬膜下血腫などを、SPECTではアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などで見られる特異的な脳局所の血流低下の評価を行うなど、客観的な指標を基に評価します。
それらに加えて過去の病歴や現在の日常生活動作、実際の受け答えがどれくらいできるのかなどを医師の面談によって診察し、それらを合わせて総合的に医学的な診断を行います。
十分に医学要素を用意していれば、死後に万が一遺言書の有効性が問題になっても遺言書の有効性を認めてもらいやすくなるでしょう。
信頼性が高く死後に覆される可能性は低い鑑定方法を採用しているので、医師によって遺言書の有効性にお墨付きを与えることが可能です。
死後に意見書を書いてもらうのと比べて費用も手間もかからず、遺言能力の鑑定を行うとご本人の状況がわかるので、依頼者の健診としての側面も期待できます。
まとめ
遺言の効力を後から争う事例は珍しくありません。
そういったトラブルを起こさせないためにも遺言能力を測ることは重要になります。特に、遺言能力を保証するために医学要素は極めて重要です。
長谷川式簡易知能スケールが広く用いられていますが、それだけでは十分とはいえません。
認知機能や精神状態を丁寧に測れる医師の存在が必要不可欠です。
YKRでは専門医が丁寧に鑑定いたします。
遺言書の効力を確実なものとしたい方はぜひ利用をご検討ください。
この記事の監修者
福谷陽子

- 京都大学法学部に現役合格
- 在学中(大学4年時)に司法試験に合格
- 法律事務所の設立経験あり 元弁護士
不破 英登

経歴
| 2009 | 愛知医科大学医学部医学科 津島市民病院 |
| 2011 | 名古屋第二赤十字病院 放射線科 |
| 2016 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教 |
| 2018 | 豊田若竹病院 放射線科 YKR medical consult設立 |
| 2018 | 家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師 |
| 2021 | YKR medical consult 代表就任 |
| 【資格】 産業医・放射線科診断専門医 |