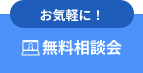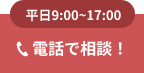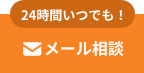具体的な画像評価
Image evaluation
遺言書作成の翌月に施行されたMini-Mental State Examination(MMSE)は11/30点、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は13/30点でした。
MMSE, HDS-Rいずれも遅延再生課題での失点が目立ち、重度の記銘力障害を認めました。進行したアルツハイマー型認知症に典型的なものでした。遺言書作成の翌月の頭部CT検査で「海馬の萎縮あり」と判断されており、これもアルツハイマー型認知症を支持する所見でした。

意見
opinion
診断について
認知症の診断基準に照らして、遺言書作成の月の時点で、Xは認知症であったと判断しました。記銘力障害のエピソードや、海馬の萎縮の存在は認知症のなかでもアルツハイマー型認知症と考えられるものでした。
判断能力について
遺言書が作成された月に記載された介護主治医意見書では、認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」と記載されており、これは日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態に相当します。
遺言書作成の時点でも、アルツハイマー型認知症による重度の認知機能障害を有していたものと判断しました。
遺言書の効力について
以上より、遺言書作成の時点でAさんは契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない状態と考えられ、認知症の診断をした担当医も同様の見解を示していました。
このような状況では周囲からの影響を受けやすく、遺言書が与える影響の範囲・効果を適切に理解して判断を行うだけの能力があったとは考えにくいと判断しました。
遺言書が作成された状況によっては付添人の意向に影響を受けた内容で作成された可能性があり、認知機能が低下する以前からの本人の意思に照らして自然な内容とは言えないと意見致しました。

鑑定結果
Appraisal results
上記のように客観的なデータを医学的に解釈し、認知症の診断、重症度や個別の認知機能障害の評価、精神症状を含む行動心理症状(BPSD)の評価を行った上で、遺言内容と照らして遺言内容は本人の従前の意思とは異なるものであったと鑑定しました。
認知症の遺言鑑定では、日常生活や社会生活状況がわかる客観的資料(診療録や介護保険認定調査記録など)、神経心理学的検査結果、血液検査、頭部画像検査が揃っていると、精度が高くなります(→コラムへリンク)
しかし、場合によっては部分的にしか情報が得られない場合もあります。弊社の遺言鑑定においては、脳神経内科専門医、認知症専門医、放射線画像診断専門医など複数の専門医で評価を行います。
脳疾患や認知機能障害における判断能力などについて、多角的に検証して意見書を作成することができます。正式にご依頼いただく前に相談会を実施することもできますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。