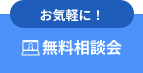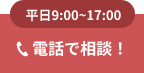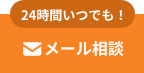足の傷跡による後遺障害等級認定のポイント
交通事故や労災事故で足(下肢)に傷跡(瘢痕・醜状痕)が残った被害者について、後遺障害等級認定の条件や必要な医学資料、慰謝料の目安、留意点を医学・法律の両観点から解説します。
足の傷跡による後遺障害は認定基準が複雑で、適切な準備を怠ると被害者が不利になる可能性があります。
以下では、最新の等級認定基準や裁判例に基づき、専門家が押さえるべきポイントを詳述します。
目次
足の傷跡の後遺障害は部位によって対象が異なる
下肢の露出部位と「手のひら大」基準: 足の傷跡が後遺障害(醜状障害)に認定されるには、傷の場所と大きさが重要となってきます。
自賠責保険(交通事故)の場合は股関節から足の背(足背部)までの下肢全体が対象ですが、労災保険では膝関節から下の部分のみと対象範囲が狭い点に注意が必要です。
認定基準では一般に「人目に付きやすい露出面」に残る傷跡が対象とされ、面積が被害者の手のひら大以上であることが一般的です。
ここでいう「手のひら大」とは被害者自身の手のひらの面積(指を除いた掌部分)を指し、薬指の付け根から手首までの長さと、親指付け根から小指側手のひら端までの長さの積を基準とします。
例えば膝から下の露出部に手のひら大以上の瘢痕や色素沈着が残存すれば、醜状障害として認定される可能性が高まります。
認定されやすい条件/されにくい条件
足の傷跡が後遺障害として認定されやすいのは、傷跡が大きく明らかに目立つ場合です。
具体的には、下肢の露出面に手のひら大以上の瘢痕が1つ以上残っているケースでは14級5号が認定される可能性があります。
複数の傷跡がある場合、その合計面積によっては「手のひら大の3倍以上」と評価され12級相当が検討されることもあります(例:片脚に手のひら3枚分以上の広範な瘢痕が残存)。
実務上、複数の傷が離れていても同一肢内であれば面積を合算して評価されますが、少なくとも1つは手のひら大を超える必要があります。
逆に認定されにくいのは、傷跡が小さい場合や衣服や毛髪で容易に隠れる場合です。
醜状障害の前提として「人目につく程度以上」であることが要求されるため、日常生活でほとんど露出しない部位の傷は等級非該当と判断されがちです。
例えば太ももの高位(ビキニラインより上)にある傷は、自賠責基準上は下肢に含まれるものの日常的には隠れるため、調査事務所の判断で「人目につかない」と扱われ認定から漏れるリスクがあります。
また、傷があっても色素変化や凹凸が軽微で周囲と差異が少ない場合、「醜いあと」と評価されず認定されないこともあります。
醜状障害に該当する傷跡には、熱傷痕や手術瘢痕のほか、皮膚の黒褐色の色素沈着や色素脱失(白斑)も含まれる点を押さえておきましょう。
つまり濃い色素沈着や白斑が手のひら大に残った場合も認定対象となり得るため、単なる瘢痕だけでなく色調の変化も見逃さず評価する必要があります。
足の傷跡を後遺障害として立証するためには
写真撮影の注意点(角度、距離、時期)
醜状障害の立証では傷跡の状態を示す写真資料が極めて重要です。
申請時には傷跡の状況が一見してわかる鮮明な写真を添付しましょう。
撮影時のポイントは、まずフラッシュを使わず自然光で撮影することです。
フラッシュ光は傷跡の質感や色を飛ばしてしまう恐れがあるため、日中の明るい場所で影ができないよう配慮します。
また傷跡のそばにスケール(定規やメジャー)を当てて大きさが一目で分かるようにすることも効果的です。
傷の長さや幅を測定できるようにし、色や凹凸の状態も写る角度で撮影します。
例えば正面からの写真だけでなく、斜めや横から撮って傷の隆起・陥没を可視化すると良いでしょう。
撮影時期については、受傷直後から治癒経過に応じて定期的に撮影しておくことが望ましいです。
症状固定時点で傷跡が残存しているかを判断しますが、事故との因果関係を明確にするため受傷直後や治療過程の写真も保存し、必要に応じ提出します。
早期から経時的な画像記録を残すことで、後遺障害診断書作成時に医師が「事故による創傷」と理解しやすくなり、傷跡の記載拒否を防ぐ効果もあります。
計測方法(大きさ・色調変化)
傷跡の大きさの計測は客観性を持って行います。
写真上で定規と比較して算出するだけでなく、診察時に医師に縦横の長さや面積を具体的な数字で計測してもらうことが望ましいです。
瘢痕の長径・短径や、色素沈着の場合は境界の明確な部分の直径などを測ります。
また、色調の変化も後遺障害の評価要素となるため、周囲皮膚との色差がわかる形で記録します。
写真添付時には傷跡部分の肌の色(赤み、黒ずみ、白斑など)が判別できる状態が理想です。
例えば、日焼けしていない冬季に撮影する、照明やカメラのホワイトバランスを調整する等、実物の色味に近い画像を用意しましょう。
なお、写真への過度な加工は厳禁です。傷跡を強調しようとペンで丸囲みしたり画像ソフトで補正したりすると、証拠としての信頼性を損ねるため注意してください。
診断書の記載内容のポイント: 後遺障害診断書(自賠責様式)の醜状障害欄には、傷跡の部位・大きさ・形状・程度を正確に記載してもらう必要があります。
具体的には、「右下腿前面に長さ○cm・幅○cmの瘢痕1個、左足背部に直径○cmの色素沈着」等、場所と寸法を明記し、可能であれば模式図に描き込んでもらいます。
医師が作成する診断書には主観的な「醜い」という評価は記載されませんので、客観的事実としての寸法・写真を充実させることが重要です。
2016年には「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」という醜状障害専用の追加診断書様式が新設されており、体表図や顔面の図に傷跡をマーキングできるようになっています。
この専用書式を活用することで傷跡の部位・範囲を直感的に示せるためベストですが、多くの臨床医師はこの書式の存在自体を知らないのが現状です。
そのため、弁護士があらかじめ白紙様式を用意して医師に手渡し、「こちらの追加書式にもご記入お願いします」と依頼することが実務上有効です。
専用書式が入手できない場合でも、診断書に別紙として全身の体表図や患部写真を添付し、傷跡の位置・大きさを示す工夫をしましょう。
医師意見書の重要性と記載例
主治医による医学的意見書(医師意見書)は、後遺障害等級認定の審査において強力な裏付け資料となります。
意見書には、傷跡が事故に起因すること、現在も残存していること、将来的にも著明な改善は見込めないことなどを明確に記載してもらいます。
例えば「創傷は受傷から1年以上経過して瘢痕化しており、今後も色調の変化や面積の縮小は僅少と考えられる」等の所見があると、傷跡が恒久的なものであることが伝わります。
また、傷跡が化粧や衣服によって容易に隠せない部位・程度であることも言及できれば理想的です。
実際の裁判例でも、医師意見書で「残存する醜状は化粧等でも隠せない」という指摘を行い、保険会社の反論(「具体的な不利益が生じた証拠はあるのか」といった主張)を退けたケースがあります。
医師意見書には他にも、瘢痕部位の知覚異常や疼痛の有無、ケロイド体質の有無、植皮や手術履歴など、専門的知見から後遺障害の蓋然性を補強する内容を盛り込んでもらうと良いでしょう。
もっとも、多くの臨床医は自賠責の認定基準に詳しくないため、弁護士から医師への事前説明や依頼文書の工夫が欠かせません。
必要に応じて、後遺障害認定に精通した専門医に意見書作成を依頼することも検討すべきです。
その際は、診療録・検査結果・後遺障害診断書などを一式提供し、第三者的な立場から中立的で説得力ある意見書を書いてもらうと良いでしょう。
足の傷跡に対する後遺障害等級と慰謝料の考え方
想定される等級(12級14号、14級5号など)
足の傷跡による醜状障害で認定される等級は、主に14級5号(下肢の露出面に醜いあとを残すもの)が該当します。
これは膝下など通常露出する部分に手のひら大以上の瘢痕が残ったケースで適用される等級です。
14級5号に認定されると、自賠責では後遺障害として75万円(慰謝料等を含む)の支払い対象となり、被害者は加害者側に逸失利益や慰謝料の請求をする法的根拠を得ます。
一方、傷跡の範囲が極めて広範な場合や複数箇所に及ぶ場合には、12級相当として認定される可能性もあります。
公式の後遺障害等級表には下肢醜状で12級とする明文規定はありませんが、例えば片脚に手のひら大の3倍以上の醜状痕が残存したケースでは実務上12級相当と評価された例があります。
その場合、自賠責保険金の上限は224万円(12級全体に対する補償額)となり、等級認定による慰謝料増額効果も大きくなります。
慰謝料の相場(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)
等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料は、算定基準によって大きく異なります。
自賠責基準(最低基準)では、たとえば14級の場合32万円、12級の場合93万円前後が後遺障害慰謝料額として定められています。
任意保険基準(保険会社の社内基準)も自賠責基準と大差ない水準で、14級なら約32万円+α程度とされています。
これに対し、裁判所基準(弁護士基準)では被害者の精神的苦痛を手厚く評価するため、14級で110万円、12級で290万円前後を一応の目安とします。
実際の判例でも14級の後遺障害慰謝料は110万円前後が認められることが多く、個別事情によって100万~150万円程度の幅で調整されます。
以上はあくまで「慰謝料」(精神的苦痛に対する賠償)の金額であり、ここに被害者の収入減に対する補償(逸失利益)が加わったものが最終的な示談金となります。
例えば14級5号が認定された会社員であれば、自賠責では逸失利益を含め75万円の支払いに留まりますが、裁判基準で交渉すれば慰謝料110万円+逸失利益(後述)を合わせて200~400万円程度の示談金が見込めるケースもあります。
なお、労災保険の場合は後遺障害等級に応じた障害補償給付が別途支給されますが、その金額は労災の定型基準によります。
しかし、第三者行為(加害者)の存在する労災事故では、最終的には民事賠償として裁判基準での慰謝料獲得を目指すことが被害者救済の観点から重要です。
足の傷跡の後遺障害で問題となりやすいポイント
労働能力喪失の認定の難しさ
足の醜状障害では後遺障害等級が認定されても、労働能力喪失率(逸失利益)が争点になることが多々あります。
保険会社は「傷跡が残っても身体機能に問題はないのだから、働く能力は失われない」と主張し、逸失利益をゼロまたは低く見積もろうとする傾向があります。
特に男性や、外見が業務に与える影響が小さい職種(工場作業員など)では、「見た目の傷」で収入が減るとは考えにくいとして労働能力喪失を認めない理論構成が用いられます。
実際、醜状障害「のみ」を理由とする逸失利益は裁判上でも否定される例があり、男性被害者が14級に認定されたが逸失利益はゼロと判断されたケースも散見されます。
しかし近年の裁判例では、性別のみで一律に判断せず、傷跡の程度・部位、被害者の年齢や職業、社会生活への影響を総合考慮して労働能力喪失の有無や割合を判断する傾向が強まっています。
例えばサービス業・営業職など対人折衝が重要な職業で、傷跡が顧客対応に心理的支障を及ぼす場合には一定の喪失率を認める判断があり得ます。
また、醜状痕に伴って疼痛や知覚鈍麻、神経症状が残存する場合には、それ自体が機能障害として評価されるため、労働能力喪失の主張がしやすくなります。
現実には瘢痕部に慢性的な痛みや違和感を訴える患者も多いため、そうした医学的付随症状を併発している場合は積極的に主張・立証すると良いでしょう。
総じて、醜状障害による逸失利益の主張はハードルが高いものの、「外見が重視される職業」「傷跡の程度が著しい場合」「傷跡に起因する精神的苦痛が社会復帰を妨げる場合」などでは裁判所も喪失期間や率を認定する傾向が見られます。
依頼者に該当しそうな事情がないか丁寧にヒアリングし、必要なら職業影響について本人や上司の陳述書を用意するなどして、逸失利益の減額に備えておくことが重要です。
社会生活への影響が否定されやすい点
足の傷跡の場合、顔面の傷と比べて社会生活上の不利益が見えにくい側面があります。
裁判例でも、顔や首の醜状と異なり「下肢の瘢痕は日常的に衣服で隠せる」「本人の社会的評価や対人関係に直結しない」として、精神的苦痛の程度を低く見積もる論調が散見されます。
しかし、被害者にとっては容姿コンプレックスや日常生活での支障が現実問題として生じ得ます。
例えば女性被害者が夏場に人前で脚を出せない心理的苦痛や、温泉・プール等で傷跡を見られることへの強い抵抗感から対人活動を制限してしまうケースもあります。
こうした主観的苦痛は金銭賠償で完全に癒せるものではありませんが、慰謝料額の増減事由として主張することは可能です。
実務上は、被害者本人の陳述書やカウンセリング記録などを用いて「傷跡のために日常生活上こうした我慢や制限を強いられている」ことを具体的に示すと、裁判官の心証形成に資するでしょう。
また、婚姻や就職への影響についても検討します。未婚の若年女性であれば「将来配偶者選択に支障を来す恐れ」が論じられることもあり、一部の裁判例では若年女性の外貌醜状につき逸失利益を長期間・高率で認定した例もあります(※顔面のケースですが、論理は下肢にも類推可能)。
もっとも過度な主張はかえって信用を失うため、傷跡の写真や医師の所見と照らして相応といえる範囲で社会生活上の影響を主張することが大切です。
例えば「左下腿の瘢痕は夏季でも長ズボン着用を余儀なくされる程度に目立つ」など、具体的な日常影響を挙げると説得力が増します。
総じて、足の傷跡の後遺障害では外見上の問題が賠償上どこまで評価されるかが争点となりやすいため、法律家としては医療面と心理面の双方から主張を組み立てる姿勢が求められます。
医師の意見書に関する相談や連携の必要性
医師とのコミュニケーションで注意すべき点
後遺障害等級申請においては、主治医との綿密な連携が結果を左右します。
まず診断書作成前に弁護士が主治医へ面談や書面照会を行い、認定基準や留意点を伝えておくことが有益です。
医師には「傷跡の大きさ・部位を具体的に記載していただきたい」「自賠責の追加様式がある」等を丁寧に説明し、協力を仰ぐ姿勢を示しましょう。
医師も多忙な中で診断書を書くため、要点を整理した依頼状(チェックリスト形式など)を渡すと親切です。
また、医師の中立性を尊重することも重要です。過度に結果を誘導しようとすると医師が萎縮したり、記載を拒む恐れがあります。
「事実をありのまま書いていただければ十分です」と伝えつつ、必要情報の漏れがないよう依頼するバランス感覚が求められます。
なお、受傷直後から形成外科や皮膚科を受診しておくこともポイントです。
急性期の治療では整形外科等が主となりますが、瘢痕の専門治療は形成外科領域です。
早期から専門医の経過観察を受けていれば、その医師に後遺障害診断書や意見書を依頼でき、専門的観点からの詳細な記載が期待できます。
仮に主治医が等級認定に非協力的な場合や専門外である場合には、セカンドオピニオン的に別の医師の意見書を取得することも検討しましょう。
例えば形成外科の専門医に写真・診療情報提供書を見てもらい、「瘢痕は広範で整容面の改善余地が少ない」等の所見を書いてもらえれば、調査事務所や裁判所に対する説得力が増します。
実務では、医学鑑定会社に依頼して専門医の意見書を作成してもらう手法もあります。
いずれにせよ医師と相談しやすい環境作りが大切です。
被害者から主治医へのお願いだけでなく、必要に応じ弁護士が直接説明することで、医師も「法律実務上どういう情報が求められているか」を理解し、協力的になってくれるでしょう。
中立的な医学意見の重要性
等級認定の場面では、保険会社側も医学的反論を行ってくることがあります。
例えば「傷跡はあるが社会的影響は軽微」「将来レーザー治療で改善可能ではないか」などといった主張です。
これに対し、中立的な医師意見書で反証することが極めて有効です。医学意見書には診療録や画像データをすべて精査した上で、後遺障害が存在する蓋然性を論理立てて述べてもらいます。
具体的には、「受傷○ヶ月後の時点で瘢痕治癒が完了し、以後1年以上外用療法継続したが瘢痕の大きさ・色調に大きな改善なし」「瘢痕組織には神経障害性疼痛が併発しうることが医学文献Xにも示されている(文献添付)」等、専門知見を織り交ぜた説明を行います。
第三者医師の意見書は調査事務所の心証にも影響を与え、異議申立て時などでは等級が覆る決め手となる場合もあります。
実際、ある事例では下腿開放骨折で植皮を行った被害者について、当初は下肢醜状14級相当と判断されました。
しかし弊所で依頼した専門医が大腿部の採皮痕にも注目し、植皮部と合わせて面積を測定した意見書を提出した結果、後遺障害12級相当が認定されたことがあります。
このケースでは、主治医だけでは採皮部の傷が見逃されていた可能性が高く、専門医の視点が等級アップに直結しました。
このように中立かつ詳細な医学的意見は、被害者にとって大きな利益をもたらし得るのです。
もっとも、意見書はあくまで客観的であることが重要です。被害者側に偏り過ぎた主張はかえって信用性を損なうため、医学的事実に即して正確かつ簡明に論じてもらうよう依頼しましょう。
医師との連携により、法律と医学の双方から万全の書証を整えることが、醜状障害事案で適正な結果を引き出す鍵となります。
まとめ
交通事故や労災で足に傷跡が残った被害者の後遺障害等級認定について、ポイントを総括します。
足の傷跡に関する後遺障害は、傷の部位(露出部か否か)と大きさ(手のひら大以上か)で認定の可否が決まります。
適切に認定を受けるためには、早期から形成外科等の継続治療を受けつつ、写真記録や詳細な診断書で医学的証拠をしっかり残すことが肝要です。
認定されうる等級は主に14級5号(下肢醜状)ですが、重度の場合は12級相当も視野に入ります。
等級に応じた慰謝料は自賠責基準より裁判基準が大幅に高額であり、適正な賠償を得るには弁護士による増額交渉が不可欠と言えます。
もっとも、足の傷跡は労働能力喪失や社会的影響の立証が難しい分野であり、保険会社から逸失利益を巡って争われるケースが多いです。
そこで、傷跡に伴う痛みなど機能面の支障や、対人面での具体的困難を丁寧に主張立証し、裁判例の動向も踏まえて適切な喪失率・期間を獲得する努力が求められます。
最後に、医学的裏付けの充実が何より重要です。
主治医との連携や専門医の意見書取得により、傷跡の存在・程度・永久性を客観的に示すことで、等級非該当や過小評価のリスクを下げられます。
法律家は医学知識にも目配りしつつ、被害者に代わって最善の準備を整える必要があります。
以上のように万全の対策を講じれば、足の傷跡による後遺障害事案でも被害者が適正な補償を受けられる可能性が高まるでしょう。